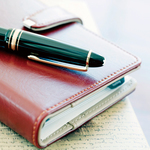指定管理者の方や、これから指定管理者を目指す方のための情報サイト
株式会社指定管理者情報センター
自治体の指定管理者選定・モニタリングの経験者によるサイトだから、
他のサイトでは得られない情報が満載!
本 社:〒770-8063 徳島市南二軒屋町神成831-16
TEL:(088)625-1339 FAX:(088)678-5804
東 京:〒105-0013 東京都港区浜松町2丁目2-15
浜松町ダイヤビル2階 TEL:(03)6690-2685
一昨年くらいから、「自治体と指定管理料の増額を交渉する方法」 についての質問をよくいただくようになりました。指定管理者制度が導入されてからしばらくは、デフレ経済で物価が下落しており、指定管理料が変わらなくてもなんとかやりくりできていたのでしょうが、最近は人件費の高騰が著しく、コスト削減が限界に達していることが要因なのだと思います。
みなさんも実感していると思いますが、多くの自治体は財政難で、指定管理料の増額は非常に困難なのが現実です。募集要項に 「著しい物価上昇」 を自治体負担としているケースが結構ありますが、人件費はともかく、日本全体の物価上昇率は日本銀行が目標としている2%に及ばない状況であり、リスク分担表のみを根拠に指定管理料の増額を求めても、ほぼ間違いなく門前払いされるでしょう。
けれども、だからといって 「あきらめる」 のがよいとは言えません。黙っていると、今までの流れで、次期公募の際に指定管理料の上限額がさらに下がる可能性があるからです。指定管理者が経費アップに困窮していることを正確に伝えることで、少なくとも、担当課が次期公募での指定管理料の上限額引き下げを回避する努力を最大限行うという効果は十分期待できます。
ただ、自治体に要望を行う際は、指定管理者としての評価を下げられないためにも、適正な形で要望を行う必要があり、この手法を簡単にご紹介します。
1.収支を赤字にする。
指定管理業務の収支決算が黒字なのに指定管理料増額を要望しても説得力がありません。経費が増えていることを反映させて収支を赤字にすることが必要です。以前は、収支を赤字にすると、「当初の見積もりが甘かった」 として指定管理者の評価を下げる自治体が結構ありましたが、最近は、明確な理由があればそうでもありません。ただ、前期まで指定管理部門の収支が黒字なのに、いきなり大きな赤字が出れば、収支の信憑性が疑われる可能性があります。 「顧問税理士から部門ごとの収支をできる限り正確に算出するように指導されました」 などの理由を添えて自治体に報告する必要があります。
2.良好な管理運営を行う。
自治体が指定管理者の赤字のみを理由に指定管理料を増額することは困難です。 首長のトップダウンなら話は別ですが、通常は 「良好な管理運営を行っている指定管理者に引き続き応募してもらうため」 という理論構成が求められます。したがって、利用者数の増加や利用者アンケートでの良好な結果が必要になります。(この条件が満たされない場合は、増額要望を行うこと自体で、自治体の評価を下げてしまう可能性があります。)
3.資料を作成する。
口頭での要望は意味がありません(担当者が上司に報告しないことがほとんどです)。資料を作成し、資料をもとに要望を行うことが必要です。資料には、以前 (原則として前回の指定管理期間の最終年度) か、または、募集要項に自治体の積算額が記載されている場合は当該積算額と比較して、経費がどの程度上昇しているかを経費項目ことに記載してください。
4.自助努力を見せる。
「経費増加分をすべて指定管理料で補てんしてください」という要望は無責任というのが自治体の論理です。例えば、経費が200万円増加している場合、「100万円は当社の経営努力で対応しますので、残りの100万円については、指定管理料の増額をお願いします。」というように、自助努力があることが指定管理料増額の大前提です。
自治体職員の感覚からすると、増額できる場合でも 「折半」 すなわち、やむを得ない経費増加額の半分くらいが相場観のように思います。ただし、最初から半額を要望する必要はありません。交渉ですから、経費が200万円増えているのであれば、最初は150万円の増額を要望して最終的に100万円で妥協することを目指すというストーリも十分あり得るでしょう。
経費増加の全額が認められない可能性が強いのですから、例えば、本社で指定管理業務に従事する職員の人件費なども含めて、経費増加額を (虚偽と言われない範囲で幅広く解釈し)増やすことが重要だと思います。(2018.1.29)
→[管理運営に必要な知識・テクニック]に戻る
コラム
指定管理者にとって必要なのは、単なる施設管理の枠にとどまらない、民間ならではの実効性のある運営手法です。当センターでは、成功事例をベースにした実践的なコンサルティングを行い、それぞれの施設や地域性に応じた具体的な運営モデルをご提案しています。公共施設を取り巻くニーズが多様化する中で、柔軟かつ創造的な運営を可能にする支援体制を整えています。形式だけでなく、成果を重視した運営を目指す方に最適なサポートを提供いたします。地域イベントの企画運営や利用者満足度の向上施策など、民間だからこそ実現できる柔軟な運用方法も多数ご紹介可能です。ぜひご相談ください。 2025.12.9
指定管理者制度の導入後、「自治体との調整が難しい」「地域との連携が円滑に進まない」といった課題に直面される方は少なくありません。当センターでは、全国各地の事例を基に、具体的な解決策や改善のヒントを提供しております。自治体担当者との適切な関係構築のためのアプローチや、地域住民との信頼関係を築くための施策など、現場で役立つ実務的なアドバイスを行っています。制度の本質を踏まえた上で、持続可能な運営体制を目指したい方は、ぜひ当センターにご相談ください。初めて指定管理者業務に関わる事業者に対しても、制度の基本的な理解から運営計画の策定、日々のマネジメント手法まで、段階に応じた支援を提供しております。 2025.12.2
今年もいよいよ年末が近づき、全国では冬の訪れとともに新たな年度への準備が始まっています。東京2025世界陸上を経て、社会全体がスポーツ・地域施設の持続的な活用に注目する中、指定管理者制度への期待も高まっています。特にオリンピックをはじめ世界規模のスポーツ大会後はスポーツ施設の運営に人気が出ます。今後の公募選定でも実績や企画力が重要視されるでしょう。指定管理者情報センターでは、自治体や民間事業者の双方にとって最適な連携モデルの構築を支援し、公共サービスの質向上と地域価値の創出に貢献してまいります。また、運営体制の再構築を検討される団体に向けて、事績分析や競合調査も行っております。制度の理解を深める勉強会も開催しており、より高度なマネジメントを目指す方々をバックアップしています。 2025.11.26
指定管理者制度の専門コンサルタントは、自治体や審査委員の視点から、事業計画書の作成や運営方針の策定など、応募企業や団体一つ一つに最適な戦略を提案します。全国の先進事例や仕様書を分析し、事前準備から申請、プレゼン対策まで幅広いサポートが可能です。マニュアル通りのアドバイスではなく、それぞれの施設や法人の特性に合ったオーダーメイドの提案を行うのが強みです。書類づくりに不安がある方も、部分的なサポートだけほしい方も、まずは指定管理者情報センターにご相談ください。 2025.11.19
事業計画書は、指定管理者選定時の重要資料の一つです。指定管理者情報センターでは、提出先である自治体が重視する内容や、記載すべきポイントを詳細に紹介しています。エリアの特性や施設の状況に応じて、的確な計画書を作成することが選定評価を高める要因となります。ノウハウと現場経験を活用し、全国各地の申請・選定支援も行っております。事業計画策定でお困りの法人様はぜひご相談ください。 2025.11.14
令和3年調査では、全国で指定管理者制度導入施設が77,000以上、うち約4割以上を民間企業・法人が担っていることが確認されました。多様なエリアで民間参画が進み、運営の高度化や住民サービス向上に寄与しています。指定管理者情報センターは、企業・法人による応募や選定支援も強みとし、最新動向を踏まえた情報提供・コンサルティングを実践しています。法人向けサポートのご相談も承ります。 2025.11.5
指定管理者情報センターは、かつで自治体で指定管理者の選定・モニタリング等を担当した経験を持つ代表が、独自ノウハウを提供する体制を整えています。自治体運営の最新動向を把握し全国各エリアの施設課題もきめ細かくサポートいたします。コンサルティングでは活きた情報を駆使し、制度や業界の変化にも即応しています。現場経験と情報更新体制が、地域施設運営の成功を導きます。制度の詳細相談は当センターへ。 2025.10.29
指定管理者の応募には、申請書や事業計画書の提出が不可欠です。提出期限ギリギリよりも、十分な準備期間を設けて内容を精査し、万全な状態で提出することが推奨されます。公官庁、自治体案件では、書類の不備が評価に影響することがあります。指定管理者情報センターでは、書類作成から提出までの流れや、トラブル防止のポイントについてアドバイスを行っています。確実な申請書提出で、公募選定の可能性を高めましょう。 2025.10.22
指定管理者制度は、自治体施設で、公的管理業務を民間企業やNPOへ委託することで業務効率化を図る仕組みです。現在は全国でも漸次導入が進み、管理運営の質向上へつなげられています。指定管理者情報センターでは、指定管理者候補や現任法人に向けた運営アドバイスとサポートを提供。地域特性を反映したコンサルティングで、指定管理者の課題解決をご支援します。制度運用に関するご相談も随時受付中です。 2025.10.15
指定管理者の公募時には、現地説明会の開催が多くの自治体で行われています。この説明会が応募の必須条件となる場合があり、参加準備が重要です。エリアごとの施設の特徴や運営方針を把握した上で説明会へ臨むことで、選定評価にもつながります。指定管理者情報センターでは、現地説明会における事前準備や心構えなど、各地の事例をもとにアドバイスをご提供しています。応募書類の精度を高めるご支援も可能です。 2025.10.9
公益財団法人や公益社団法人への移行認定申請は、ニーズの高い業務ですが、書類作成や複雑な手続きが求められます。指定管理者制度の深い理解が不可欠なため、税理士や行政書士の先生でも難しいケースが増えています。指定管理者情報センターでは、豊富な実績と専門知識を活かし、公益法人制度改革のコンサルティングも対応可能です。指定管理者関連の手続き支援も、ぜひご相談ください。 2025.10.1
指定管理者は住民向け公共施設の運営に携わる大切な役割を担っています。選定にあたり、利用者である地域住民だけでなく、自治体からの評価も不可欠です。公募にて高評価を得るための提案内容や運営体制、地域密着の活動も重要となります。指定管理者情報センターでは、自治体公募で評価されるポイントを踏まえ、各エリアの施設運営に関する対策について相談を承っています。指定管理者制度の専門知識で、住民満足度向上を目指した施設経営をサポートいたします。 2025.9.24
指定管理者として業務を行ったあとは、必ず自治体に向けて報告書を提出する義務が生じます。しかし、日々の運営業務と並行して報告書を作成するのは想像以上に大変です。限られた時間の中で、どのように高評価を得られる報告書を作るかが重要になります。指定管理者情報センターでは、報告書の構成方法、評価項目へのアプローチ、伝えるべき成果の整理など、ポイントを押さえた作成アドバイスを実施しています。時間をかけずに、かつ伝わる報告書を目指す方は、ぜひご活用ください。 2025.9.17
地方自治体によって指定管理者の選定基準は異なりますが、共通して言えるのは「提案内容の説得力と実行力」が問われるということです。どれだけ魅力的なプランを描いても、それが自治体の課題に即しておらず、現実味に欠ける場合は選定されることはありません。指定管理者情報センターでは、自治体側の視点を熟知したコンサルタントが、説得力ある提案書の作成をサポートいたします。選定・モニタリングに実際に関わった経験から得られた知見を活かし、採択率を高める支援を行っています。 2025.9.10
指定管理者制度は、単年度契約が基本となる通常の業務委託とは異なり、原則として3~5年といった複数年契約が採用される制度です。そのため、長期的な視点に立った事業運営が求められるとともに、契約終了後には再度公募が行われることもあります。過去の実績が評価されれば、前任者が引き続き選定されるケースも少なくありません。指定管理者情報センターでは、新規で制度に挑戦する事業者はもちろん、契約満了後の再選を目指す現職の指定管理者に対しても、必要な支援やアドバイスをご提供しております。事業継続の可能性を広げたい方もぜひご相談ください。 2025.9.4
地域に根づく「ローカルルール」は、指定管理者が運営に携わるうえで見逃せない要素のひとつです。子どもの遊びの中にも見られるような地域独自のルールは、実は行政の現場でも頻繁に登場します。たとえば、書類の提出様式や決裁の流れ、自治体職員とのやりとりの進め方など、一見すると非公式に見えるものの、その地域での常識となっているルールが存在する場合があります。指定管理者としてスムーズに業務を進めるためには、こうした地域特有の背景や慣習を理解し、尊重する姿勢が必要不可欠です。当センターでは、こうした“見えにくいルール”への対応力を高めるアドバイスも行っております。 2025.8.27
「指定管理者に応募したいが、何から始めてよいかわからない」とお悩みの方は少なくありません。ある方はゼロからのスタートで、事業計画書の書き方自体に不安を感じている一方で、ある程度自社で作成はできるものの、仕上がりをブラッシュアップしたいというご相談も多く寄せられます。指定管理者情報センターでは、こうした多様なご相談に対し、柔軟かつ段階的なサポートを提供しています。応募前の初期相談から、実際の書類作成、プレゼン対策まで、一貫して支援できる体制を整えておりますので、安心してご相談ください。 2025.8.20
指定管理者制度において、公募の現場で高い頻度で行われる「現地説明会」。この場は、単なる施設見学にとどまらず、自治体側が応募者の姿勢や熱意を測る場として大変重要視されています。指定管理者情報センターでは、現地説明会を最大限に活用するための事前準備の方法や実践的なアドバイスを含めたサポートを行っております。応募前にぜひご相談ください。 2025.8.6
指定管理者として自治体に応募する際、必ず提出が求められるのが「事業計画書」です。この書類は、提案内容の実現性や具体性を示すものであり、自治体からの信頼を得るうえでも非常に重要な役割を担います。しかし、単に理想を書き連ねるのではなく、自治体ごとのニーズや課題を十分に理解し、そこに即した内容を的確に盛り込むことが求められます。当センターのウェブサイト内では、事業計画書作成における要点や注意すべき点をまとめたページをご用意しておりますので、まずはそちらをお読みいただき、全体像を掴んでからご相談いただくと、より具体的なサポートが可能となります。 2025.7.30
指定管理者に応募する際に必須となる事業計画書の作成ポイントを、当サイトで分かりやすくまとめています。ご相談前にぜひご覧いただき、理解を深めてください。実際の作成支援やアドバイスも行っておりますので、お気軽にご連絡ください。 2025.7.23
指定管理者制度は応募者だけでなく、自治体担当者にとっても検討すべき課題が多くあります。当センターでは自治体向けのサポートメニューもご用意し、現状の問題意識や疑問点に対して的確なアドバイスを行っています。自治体の方もお気軽にお問い合わせください。 2025.7.16
コンサルティングの依頼時には、依頼者の指定管理に関する理解の状況を把握することも重要です。当センターでは、「事業計画書の書き方から教わりたい」「大枠は自分で作成済みなので細部を修正してほしい」など、お客様の状況に応じた柔軟な対応が可能です。ぜひご相談ください。 2025.7.9
当センターのコンサルティングが高評価を得ている理由は、豊富な情報量にあります。独自に収集した300種類以上の事業計画書や1,000種類を超える募集要項を分析し、自治体ごとの特徴や傾向を把握。競合他社の動向も踏まえた戦略的なアドバイスを提供しています。 2025.7.2
全国で7万以上の施設が指定管理者制度を導入し、そのうち約4割は民間企業やNPO法人が運営しています。これから応募を検討しているものの手順やノウハウに不安がある方は、指定管理者情報センターへご相談ください。経験豊富なスタッフが丁寧にサポートいたします。 2025.6.25
指定管理者には、施設所有者である自治体の意向を踏まえつつ、先進的かつ現実的な運営提案が求められます。むやみに新しいことを推進するのではなく、実現可能な範囲で一歩先を行く提案が重要です。当センターでは、より良い運営のための先進的対応についてもご相談を承っております。 2025.6.18
新たに指定管理者に選ばれた際、前任者からの業務引継ぎが必ず発生します。自治体担当者を交えた引継ぎ会議が設けられることが多く、円滑な協力体制の構築が求められます。引継ぎに関するポイントや注意点についてもアドバイスしておりますので、ぜひご相談ください。 2025.6.11
指定管理者応募に必要な事業計画書の作成は重要なポイントです。特にコスト削減のテーマでは、削減すべき項目と維持すべき項目を適切に見極め、説得力のある内容に仕上げる必要があります。計画書の書き方や作成方法についてのご相談も承っておりますのでご連絡ください。 2025.6.4
指定管理者制度は複雑で分かりづらい部分も多く、疑問を持つ方が少なくありません。当センターでは、個別無料相談会を開催し、Zoomによるオンライン相談にも対応しています。制度について詳しく知りたい方や不安を解消したい方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。 2025.5.28
指定管理者の応募に欠かせない、自治体へ提出する事業計画書。 事業計画書作成に当たって押さえておくべきポイントは様々です。 ご覧のウェブサイトには事業計画書作成のポイントをまとめたページがございます。 実際にご相談いただく前にそちらも併せてご覧ください。 2025.5.21
政府が進める「小さな政府化」の流れにより、自治体も業務を外部に委託するケースが増えています。全国の指定管理者制度を導入している施設の約半分は民間企業が管理しています。見た目には自治体が運営しているようでも、実際には指定管理者が運営していることが多いのです。民間企業にとっては、公共施設への参入が難しく感じることもありますが、指定管理者情報センターでは、応募から運営に至るまでのサポートを行っています。 2025.5.14
指定管理者情報センターは、指定管理者制度の選定において高い成功実績を誇る専門企業です。自治体ごとの公募要件を分析し、貴社の強みを活かした提案内容の策定をお手伝いいたします。選定審査を突破するための具体的な戦略をアドバイスし、応募企業の競争力を強化。確実なサポートをお求めの方は、ぜひお問い合わせください。 2025.5.7
指定管理者制度の公募に応募する際、どのようなポイントが評価されるかご存じでしょうか? 指定管理者情報センターでは、応募企業の強みを活かした戦略的な提案書作成をサポートし、選定通過に向けた準備をお手伝いします。豊富な知識と経験を活かし、確実な公募対策をご提供。成功に向けた第一歩として、ぜひご相談ください。 2025.4.23
指定管理者制度の選定を通過するためには、施設管理の実績や運営計画を的確にアピールすることが求められます。指定管理者情報センターでは、応募書類の作成からヒアリング対策まで、一貫したサポートを提供。自治体の期待に応える提案内容を構築し、貴社の選定通過を強力にバックアップいたします。ぜひご相談ください。 2025.4.16
指定管理者制度の選定を突破するには、自治体の評価基準を理解し、的確な提案を行うことが重要です。指定管理者情報センターでは、過去の選定事例をもとに効果的な応募書類の作成方法やプレゼンテーションのポイントを指導。貴社の強みを最大限に引き出すサポートを行い、選定通過の可能性を高めます。ぜひお気軽にご相談ください。 2025.4.9
指定管理者情報センターは、指定管理者制度の選定に向けたサポートを専門とする企業です。豊富な実績を活かし、応募書類の作成支援やプレゼンテーションの指導を行い、採択率向上を目指します。自治体の評価基準を熟知した専門スタッフが、貴社の強みを最大限に活かす戦略を提案。確実な選定対策をお求めの方は、ぜひご相談ください。 2025.4.2
指定管理者情報センターは、指定管理者制度の選定において豊富な経験と専門知識を持つコンサルティング企業です。自治体の公募要件を的確に分析し、提案書作成やプレゼンテーションの指導を通じて選定通過の可能性を高めます。実績に基づいた具体的なアドバイスで、施設管理の受託を目指す企業や団体を支援いたします。指定管理者制度の選定対策は、ぜひ当社にご相談ください。 2025.3.25
指定管理者情報センターは、公共施設に関する各種コンサルティングを専門とする企業です。豊富な経験と高い専門性を活かし、指定管理者のみなさんに役立つコンサルティングを行います。指定管理者への応募や管理運営に関するコンサルティングは、指定管理者情報センターへお気軽にご連絡ください。
2025.3.18
施設を管理する自治体の方針に影響を受ける部分もありますが、指定管理者には、施設の運営をより良いものにするための先進的な取り組みが求められることがあります。 ただし、新規性だけを重視して闇雲に新しい施策を導入するのではなく、現実的な方向性を見極めながら、一歩先を行く提案を行うことが重要です。 指定管理者情報センターでは、こうした先進的な運営改善に関するご相談にも対応しております。
2025.3.11
状況に応じた柔軟なサポートプランを提案 指定管理者情報センターでは、事業計画書の立案から文書作成まで、さまざまなサポートプランを用意しています。お客様の状況やニーズを伺った上で、最適なプランをご提案いたします。お気軽にお問い合わせください。
2025.3.4
施設運営に必要なルールや知識をサポート 自治体管理施設には独自のルールや慣習があります。これらを理解し、円滑に管理運営を行うための知識や技術の習得は、指定管理者にとって不可欠です。当センターでは、これらのサポートを全面的に行っています。
2025.2.25
指定管理者制度の応募を成功に導く情報提供 当センターは、自治体での指定管理者制度担当経験を基に、応募者に有益な「活きた情報」を提供しています。指定管理者制度への応募を検討中の方は、ぜひ当センターにご相談ください。
2025.2.18
現場の事情に応じたカスタマイズ型コンサルティング 事業計画書は、自治体や施設ごとの特性を反映した内容が求められます。当センターでは、それぞれの状況に応じた戦略的な計画書作成を支援し、成功を導くためのコンサルティングを提供します。
2025.2.12
事業計画書作成のポイントを徹底解説 事業計画書は、指定管理者選定において重要な役割を果たします。当センターでは、計画書に盛り込むべき内容や作成のポイントについて詳しくアドバイスし、採択に向けた最善の準備をお手伝いします。
2025.2.4
管理運営に必要な情報をタイムリーに提供 施設管理や運営には、幅広い知識と技術が求められます。当センターでは、現場の状況に即した情報を的確に提供し、指定管理者業務がスムーズに進むようサポートいたします。
2025.1.31
指定管理者向けの多様なサポートプラン 指定管理者情報センターでは、応募サポート、管理運営サポート、公益法人制度改革コンサルティングの3つのコースをご用意。指定管理者制度に精通した専門家が責任を持って対応いたします。詳細はぜひお問い合わせください。
2025.1.21
自治体に受け入れられやすい提案の立案を支援 自治体では従来の手法を重視することが多いため、新しい提案が受け入れられないケースがあります。当センターでは、進歩的かつ自治体方針に沿った提案の立案をサポートし、効果的な取り組みを実現するお手伝いをいたします。
2025.1.14
経験に基づく「活きた知識」で専門的支援 知識の価値は実務経験に裏打ちされるものです。当センターでは、指定管理者選定やモニタリング業務の経験を基に、実務に役立つ具体的な知識とアドバイスを提供します。疑問や課題解決に向けたご相談もお気軽にどうぞ。
2025.1.10
公募時の「良い質問」の仕方をサポート 指定管理者公募において自治体への質問は重要なプロセスですが、内容次第では評価に影響を与える可能性があります。当センターでは、質問の仕方や適切な内容についてアドバイスを行い、公募成功に向けた準備をサポートいたします。
2024.12.23
全国対応の無料相談会で課題を解消 2025年2月以降に指定管理者制度に関する無料相談会を全国各地で開催する予定です。日程や開催場所の詳細は1月中旬に掲載する予定ですので、ぜひご確認ください。さらに、オンライン相談会にも対応していますので、遠方の方やお忙しい方もお気軽にご利用いただけます
2024.12.20
革新的な運営方法を実現するための支援 指定管理者に求められるのは形式的な運営だけではありません。民間ならではの実効性のある運営手法を検討し、実行することが重要です。当センターでは、先進的な事例を基にしたコンサルティングを行い、より実践的な運営方法を提案いたします。
2024.12.10
指定管理者業務の課題を解決します 指定管理者としての業務において、「自治体担当者とのコミュニケーションが難しい」「地域住民との関係性に課題がある」などのお悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。指定管理者情報センターでは、必要な知識やスキルに関する的確なアドバイスを提供しております。お気軽にご相談ください。
2024.12.3
本年も師走を迎え、残すところ一か月となりました。今年はパリ五輪がありました。東京五輪の時もそうでしたが、指定管理者制度を通して民間事業者の活力を政府や自治体は求めています。大きなスポーツイベント後は、オリンピックレガシーがどう活用されているか否応なく注目が集まります。来期以降の指定管理者の公募にあたって今まで以上に注視されることになるでしょう。
2024.11.26
指定管理者の公募は自治体だけでなく政府の重要政策からも影響を受けます。そのため世論や政権などによって指定管理者に求めるものも大きく変わってくるのです。コロナ禍期間中は公衆衛生、現在ではデジタル化の面からキャッシュレス決済などを取り組んでいる施設も多いようです。自治体が新たに行おうとしている施策に対してどれだけ対応できるかということも選考基準の大きなポイントとなっています。
2024.11.19
施設運営を行う中で地域の方のボランティア活用は重要となります。ボランティアの採用は施設の利用者とは異なった扱いとなります。利用者の場合には平等に利用してもらうという原則が働きますが、ボランティアの採用などの場合には指定管理者側でその人選に関して判断を下す必要があります。地域との連携という側面からもボランティアは重要であることは一目瞭然です。
2024.11.14
指定管理者として施設の運営をされている業者様の中では次回公募に向けて準備を始めている方もいらっしゃると思います。ですが、現在の運営の中で利用者数が伸び悩んでいたり、自治体のモニタリングで良い評価が得られていないというケースもあるでしょう。指定管理者情報センターではより良い評価を得るためのコンサルティングサービスも行っています。指定管理者として運営にお悩みの方は是非ご相談ください。
2024.11.5
指定管理者制度は自治体や住民の状況に応じて利用されるものであるため、応募要項も施設ごとに様々です。期間や内容についてもある程度は過去の慣例もありますが、応募して指定管理者に選定されるためには該当施設ひいては自治体が何を求めているかを読み取る必要があります。
2024.10.30
指定管理者情報センターでは当社代表の自治体での指定管理者制度の担当者としての経験を活かして、指定管理者応募へのコンサルティングを行っております。指定管理者制度は勿論のこと選考過程も知悉しており、他の指定管理者コンサルティング以上のサポートをお約束いたします。
2024.10.24
施設管理を行う上で最重要課題として挙げられるのが安全確保です。自治体が所有する公的施設は一般の施設以上に安全性の確保が重要と考えてくださって差し支えありません。指定管理者に応募する際には、安全確保に配慮を重ねた企画書を提出するようにしましょう。
2024.10.15
自治体が所有している施設をより良く運営するために、民間企業のノウハウを取り入れて住民の皆様に還元するというのが指定管理者制度の趣旨です。しかし民間企業が有効な施策と考えて応募をしても、公募を行っている自治体の考え方と齟齬があれば採用さなれないことは当然の帰結です。指定管理者情報センターでは、代表が指定管理者選定を行った経験から自治体側から見た指定管理者応募への有効な情報を発信しています。
2024.10.12
自治体は指定管理者が適切に運営をしているかモニタリング調査をしています。次回の公募の時にはそのモニタリングの調査結果を利用し次期事業計画書に反映させるのは極めて有効な戦略です。公募の選考対策として非常に高い評価が得られる可能性が高いです。モニタリングは年度末に行われることが多いようですので今の内から事前準備を行っておきましょう。
2024.10.4
日本政府の主導により地方行政は業務と経費のスリム化を行っています。それは受けて多くの公共施設では民力活用と経費節減の観点から指定管理者の公募を行っています。しかし指定管理者制度は複雑で公募のコンサルティングができる企業は限られています。弊社では自治体で指定管理者業務に従事した経験をもとに、どのような考え方や提案が自治体から高い評価を得られるかを包括的にコンサルティングいたします。
2024.9.24
指定管理者契約の更新時期が近づいてくると次の公募のことが気になるのは必然といえます。ほかの競合先がいるのかどうかの不安もあります。該当施設に情報公開資料請求などがあったときには特に注意を要します。「良い管理運営を行っていれば安心」と慢心せず、競合先の情報を集めておくことも引き続き指定管理者を継続して指名してもらうために大切なことです。
2024.9.10
指定管理者になることは法人側にとっても信頼度の向上という大きなメリットがございます。施設管理のノウハウの構築、利用者や近隣地域における知名度の上昇、公的機関との人的パイプの構築など、通常の企業運営では得難い知見を得られます。しかし応募を行うにあたって事前に知悉していなければ、選考に残ることは困難です。指定管理者情報センターでは自治体側からの希望を説明し、これから応募する企業や現在管理を行っている企業へ情報をご紹介いたします。
2024.9.17
今年のパリオリンピック・パラリンピックは大いに盛り上がり、熱狂冷めやらぬ内に無事閉幕しました。さて五輪の開催年や翌年には、体育関連施設の指定管理者の応募が増加する傾向があります。それは五輪でのスポーツ熱の高まりを受けて、自社所属の選手によるスポーツ教室などを開催することが多いからです。しかしオリンピアンを擁する企業が必ずしも指定管理者の公募選考で勝つとは限りません。指定管理者を公募している自治体には公募を行う目的意図が必ずあります。その目的に沿ったプランを提案できれば、中小企業でも指定管理者に選定されることができるのです。
2024.9.10
指定管理者になることは法人側にとっても信頼度の向上という大きなメリットがございます。施設管理のノウハウの構築、利用者や近隣地域における知名度の上昇、公的機関との人的パイプの構築など、通常の企業運営では得難い知見を得られます。しかし応募を行うにあたって事前に知悉していなければ、選考に残ることは困難です。指定管理者情報センターでは自治体側からの希望を説明し、これから応募する企業や現在管理を行っている企業へ情報をご紹介いたします。
2024.8.30
指定管理者の評価を自治体は前年度との比較で行うところが多いそうです。その為、事業計画書の目標数値のクリア、前年同月より良い数値をクリアする等の施策が必要となります。施設を指定管理者として運営していくためには、常に数値を頭の片隅入れクリアしていく必要があります。
2024.8.23
指定管理者の応募にあたっては事前に押さえておかなければならない知識がございます。一見優れたプランをコンペティションに持ち込んだと思われる応募者が敗れるという事は珍しくありません。管理者を指定する自治体には一般企業とは異なる基準があったり、法律面での障壁等がございます。指定管理者情報センターでは、指定管理者の応募・運営をしていくにあたって必要な情報を提供していきます。
2024.8.9
指定管理者の方やこれから指定管理者に応募しようとしている業者様に、指定管理者情報センターは有益な情報を提供することを旨としています。指定管理者は自治体や住民の両方にサービスを提供しなければなりません。自治体の方に伝わりやすい報告書の作成方法、ユーザー様にご満足いただける運営のヒントなど、さまざまな情報を提供しております。
2024.7.31
施設管理を行ううえで大きなトラブルとなりかねないのが設備の故障と修繕です。指定管理者として故障部分の迅速な把握はもちろん、自治体に報告、修繕方法、期間、予算を迅速に相談しなければなりません。施設の不具合を長期間放置することは利用者の不満が溜まるだけでなく、管理者として自治体からも指定管理者不適格の烙印を押されてしまいます。
2024.7.26
指定管理者は施設運営を漫然と運営していは次回の契約はおぼつきません。常に利用者の潜在的ニーズを掬いあげていく努力が必要不可欠です。利用者がその施設に対して信頼をし、使いやすい施設であると判断していただくためには普段からの丁寧な運営が必須となります。民間の得意な部分の見せ所といえるでしょう。
2024.7.18
施設管理をするうえで指定管理者として大切なことは運営業務だけではございません。ほとんどの指定管理者の方が施設をより使いやすく、無駄なコストを抑えることに尽力しているはずです。加えてきちんと運営していることを施設利用者の方に伝わるようにすることが肝要です。
2024.7.12
施設には様々な慣習やルールがあります。自治体によって千差万別といえるでしょう。指定管理者は自治体と綿密な意思疎通を図り、施設ごとの制度を把握したうえで運営をしていく事が求められます。加えて利用者のサービス向上を目指さなければなりません。
2024.7.05
事業計画書の書式は従前の公募と大きく変わること滅多にありません。そのため、公募が開始される前に前回の様式で記載内容をあらかじめ決めたり、必要書類や資料を集めたりと入念な準備を必要があります。過去の書類様式を精査し、その自治体が求めているのはなんなのかということをきちんと把握してから対策を講じなければなりません。
2024.6.28
自治体が指定管理者制度を導入する大きな理由のひとつとして経費削減が挙げられます。自治体が直接管理を行う場合は、その施設に自治体職員を配置する必要があります。それに対し指定管理者制度の場合は包括的な運営を民間企業側が行うため、自治体側は人件費を含めて経費削減することが可能となります。
2024.6.21
指定管理者の公募においては、民間企業のノウハウを取り入れても受け入れられないケースがございます。最大の原因は、自治体と民間企業の考え方のギャップです。企業は主に利益やコスト、そしてサービスの向上を目的としてサービスを展開しているのに対して、自治体は公平性を主眼において考えています。このような違いが指定管理者の公募において問題となることがあります。指定管理者の評価は前年度と比較して行うのが通例となっています。そのため、事業計画書に沿った数値目標のクリア、前年同月との比較などは指定管理者として自治体に評価されるために必要不可欠な要素となります。数値目標への意識は常に持っていることが指定管理者として管理運営継続の重要点となります。
2024.6.14
施設管理を行う上で指定管理者として、自治体の担当者と協力して行くことが肝要です。担当者への連絡や報告はきちんと書面を作成したうえで、資料提出するのが望ましいといえます。自治体は施設の管理運営を委託するために指定者管理制度を利用しています。円滑な対応をしてもらうためにも、担当者に納得して貰う資料作りが必要です。
2024.6.07
指定管理者制度の公募に申し込む際には、自治体が求めている要件を把握してから対策を講じる必要があります。自治体が指定管理者制度を利用する理由は、コスト削減や施設の改善、ノウハウの導入など、施設の課題を解決するために民間の活力を援用したいからです。
2024.5.30
自治体や公的な施設にはそれぞれ異なった固有の事情があり、同じ指定管理者という枠組みにあっても公募で選定されるための取り組み方が異なります。事業計画書やプレゼンにおいては施設を熟知した対策が必要であり、場当たり的な対策ではなく施設運営のクオリティをさらに向上させる施策の提案が鍵となります。
2024.5.23
指定管理者の公募に応募する際には、自治体の理念を理解する必要があります。公的機関と民間企業は異なるため、自治体の担当者の考え方や評価を理解することが重要です。指定管理者情報センターでは、指定管理者に選定されるためのコンサルティングを提供しています。自治体の評価を高めるための支援が行われています。
2024.5.16
指定管理者は自治体の外郭団体と民間(NPO法人を含む)に分かれます。総務省の調査によると、全国の指定管理者制度導入施設の約40%が民間によって運営されており、この割合は増加傾向にあります。指定管理者は選定された後も終わりではなく、指定管理期間の最終年度に再び公募が行われます。再び指定されるためには、住民や自治体から評価される運営を行う必要があります。もし現在問題点がある場合は、次回の公募までにその問題点を解決する必要があります。
2024.5.8
指定管理者制度には問題点も存在します。例えば、公共施設の利用が特定団体に偏ることや、職員の雇用問題が挙げられます。指定管理者が交代時に既存職員の扱いや新職員の立場が不透明になることがあります。また施設使用料については、利用料金制度と使用料制度の2種類があります。多くの場合、指定管理者制度が選択されますが、自治体の歳入となる場合は使用料制度が採用されることもございます。どちらがいいとは一概に言えませんが受託側の想定通りにいかないケースもございます。
2024.4.25
指定管理者は安全確保に細心の注意を払う必要があります。施設にはさまざまな設備や備品がありますので、事故は予期せぬものから発生することもあります。潜在的な危険を事前に回避することで施設の価値が高まり指定管理者の評価も向上します。
2024.4.19
元来、公共施設の管理は自治体によって行われてまいりました。しかし多様化するニー ズに機動的に対応する為に、多くの公共施設では指定管理者制度が導入され、施設管理、 利用者サービス向上、事業実施などを総合的に実施することができる法人に業務委託をす るようになりました。結果的に自治体の経費が圧縮され他の公共サービスに予算を回せる ようにもなりました。
2024.4.10
指定管理者に求められることのひとつが、施設を所有する自治体側で定めたルールや、明文化されていない慣習への理解です。 それらをしっかりと理解・考慮し、できる限り自治体側と歩み寄った管理運営を行うことで信頼関係を築くことができると言っても過言ではありません。 指定管理者情報センターでは、それらの管理運営に必要な知識・テクニックなども紹介しておりますので、ぜひご利用ください。
2024.4.3
指定管理者制度を通じて民間団体が指定管理者を務めることにより、様々な先進事例が生まれています。 そこには、現状の管理運営に躓きを感じている指定管理者の方にとってのヒントとなる要素も多分に含まれています。 指定管理者情報センターでは、そういった先進事例の紹介や、そこから得られる管理運営のヒントなどもお伝えしております。
2024.3.28
自治体や自治体の外郭団体が独占的に運営・管理を行っていた公共施設。 これらを民間企業やNPO法人に委託することによって、管理運営の効率化を図る「指定管理者制度」。 指定管理者への応募や実際に指定管理者を務めていくに当たっての各種コンサルティングのご相談がありましたら、私ども指定管理者情報センターにお任せください。
2024.3.21
指定管理者を採択する自治体側の方にも、今行っている業務に対して問題意識を持ち、改善を実施していきたいとお考えの方は少なくないと思います。 私ども指定管理者情報センターでは、そのようなお考えをお持ちの自治体側の方向けのメニューもご用意しております。 コンサルティングをご希望の際は、お気軽にご相談ください。
2024.3.13
指定管理者制度を採択している施設を円滑に運営していくために必要な知識を身につけるためには、それを適切に指導できるコンサルタントの協力を仰ぐという方法があります。私ども指定管理者情報センターでは、代表者が実際に自治体で指定管理担当者として業務に携わった経験があり、その時に得た知見を提供することができる環境が整っております。指定管理者制度に関するご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
2024.3.6
どのような資料においても取捨選択は肝心です。これは指定管理者選定の際に作成・提出を求められる事業計画書も例外ではありません。提出先が求めている情報をきちんと記載できていることがまず大前提となってきます。指定管理者情報センターでは、事業計画書作成において記載すべき内容のポイントの紹介をはじめ、様々なノウハウを提供しております。
2024.2.28
指定管理者公募のサポート・コンサルティングを行う指定管理者情報センターでは、ご相談いただく方の現状に合わせた支援メニューをご用意しております。事業計画書の企画立案のサポートを主軸としたプラン、プラスアルファで計画書の文書作成までトータルでサポートするプランなど、様々なプランがございます。ご相談いただくにあたって、現在の状況をお聞かせください。適切なプランをご提案致します。
2024.2.21
会社や法人には適切に運営を行っていく上で必要な様々なルールを設けています。それは地方自治体においても同じことで、自治体で管理している施設にもそのルールや慣習などが適用されているケースが少なくないため、それらを把握することが指定管理者を務める側には求められます。そのような施設管理運営のための知識やテクニックのことなら、指定管理者情報センターにお任せください。
2024.2.15
指定管理者の選定に用いられる事業計画書。その中身は提出先によって求める答えの部分が異なるため、一般的な試験問題のような必勝法の類は当然存在しません。しかし、応募を行っている自治体や指定管理者を採択したい施設の固有の事情を加味した上で、最適な内容を記載し、作成することは可能です。指定管理者情報センターは、それそれの個別の事情や状況に応じたオーダーメイド型の戦略を立てたコンサルティングを実施しております。
2024.2.7
私ども指定管理者情報センターにて手掛けている指定管理者応募コンサルティングを、ご相談いただくお客様に自信を持ってお勧めできる理由のひとつが、「活きた情報」を提供できるという点です。実際に地方自治体にて指定管理者制度の担当を務めた経験と実績に基づく知識、そして指定管理者に対しての考え方など、有益な情報を提供することが可能です。指定管理者への応募を検討中の方、またそれに伴うコンサルタント先をお探しの際は、お気軽にご相談ください。
2024.1.31
指定管理者制度選定の際に地方自治体側から提出を求められる「事業計画書」。自治体によって様式に多少の際はありますが、記載すべき内容には当然傾向のようなものが存在します。指定管理者情報センターでは、事業計画書に記載すべき内容など、計画書作成におけるポイントのアドバイスなども行っております。
2024.1.24
指定管理者として施設の管理・運営を実施していくためには、様々な知識やテクニックが必要となる場面が少なくありません。ご自身の技量ひとつでこの局面を乗り切るのは不可能とも言い切れませんが、やはり何かしらのサポートがあった方が安心できるのは間違いありません。指定管理者情報センターでは、管理・運営に必要な情報を現在の状況に照らし合わせ、適切にご案内させていただきます。
2024.1.17
指定管理者情報センターのご案内しているサポートは、3つのコースで構成されています。ひとつはこれから指定管理者制度に応募される方向けの応募サポート、もうひとつは今現在指定管理者を務めていらっしゃる方向けの管理運営にまつわるサポート、そして最後は指定管理者向けに特化した公益法人制度改革に関するコンサルティングのサポートです。いずれも指定管理者制度に関する深い知見を持った弊社代表が責任をもって対応致しますので、お気軽にご相談ください。
2024.1.10
決まりきった手順に沿った運用を是とすることが少なくない自治体においては、指定管理者を務める外郭団体等から提案された手法等を承認しないケースもそれなりにあるものです。進歩的な内容でありつつ、自治体からの承認も得やすい、自治体側の考えにも沿った落としどころのある提案や取り組みの立案などに関するノウハウの提供も、私ども指定管理者情報センターで行っております。
2023.12.20
「実のある知識」についての考え方・捉え方は人によって異なりますが、知識を有する人の持つ経験がその礎になっているものは、実のある知識と言って差し支えないのではないでしょうか。指定管理者情報センターは、指定管理者選定やモニタリングに従事した経験から得た、まさに実のある知識をご相談いただく方々に提供することができます。疑問点に対して尋ねたいこと、どのように対策を打てばよいかなど、指定管理者制度に関することでしたら何でもお気軽にお問い合わせください。
2023.12.13
指定管理者公募の場面において、募集をかけている自治体側に質問ができる期間というものが必ず設けられます。分からないこと・疑問に思うことはこういった機会を使ってどんどん質問したいところですが、この質問制度に関しても指定管理者制度独特のルールがあるために、質問の内容によっては良い印象を抱かれなくなってしまう恐れがあります。指定管理者情報センターでは、質問の尋ね方からそもそもの「良い質問」とは、という基本的な考え方までしっかりとアドバイス致しますので、お気軽にご相談ください。
2023.12.6
指定管理者情報センターでは、指定管理者制度に関する個別無料相談会を全国各地で開催しております。開催予定日や地域の情報は、予定が定まり次第随時ご案内しておりますので、こまめにチェックいただけると幸いです。また、zoomを活用してのオンライン相談会などにも対応しておりますので、ご希望の際はお気軽にご相談ください。
2023.11.29
指定管理者として施設を運営するに当たって求められるものは、格式ばった運営だけではありません。民間から業務に携わることによる、先進的、かつ実利的な運営方法を検討・立案し、それを実際に行うことも重要なポイントのひとつです。指定管理者情報センターでは、様々な先進事例を元に今現在管理の現場で何が求められているか、何をすべきかを伝えるため、確かな目線でのコンサルティングを行っております。
2023.11.22
現在指定管理者の任を務められている方の中にも、「自治体の担当者とうまくコミュニケーションがとれない」「地域の人々と施設との間に距離を感じる」といった様々なお悩みをお持ちの方がいらっしゃると思います。指定管理者情報センターでは、今現在務められている指定管理者業務における必要な知識やテクニックに関するアドバイスなどもお教えしております。お気軽にお問い合わせください。
2023.11.15
平成30年に行われた調査の結果、75,000を超える数の施設で指定管理者制度が導入されていることがわかりました。そしてその中の実に4割の施設で株式会社や各種法人といった民間企業等が指定管理者を務めていることもわかりました。私ども指定管理者情報センターでは、指定管理者への応募を検討されている企業・法人への情報提供やコンサルティングを行っております。
2023.11.8
コンサルティングにおいて重要なのは、どれだけ活きた、実のある情報を提供できるかということです。指定管理者情報センターは、かつて指定管理者として現場に従事し、その時の経験を元にしたノウハウを提供できる環境が整っております。また、時代の移り変わりによって変動が生じてきた部分に関しても、様々な情報源を活用してアップデートを行い、その時々に応じた確実性のある情報を都度伝え教えることができます。
2023.11.1
指定管理者の応募に欠かせない申請書や事業計画書。締め切りに設定されている日にギリギリ間に合えばよいのでは……とお考えになる方も少なくありませんが、期日が差し迫っている時に思わぬトラブルが発生し、結局提出に間に合わなかった、といった事態が起こらないとも限りません。不備なくしっかりと拵えた書類を万全の状態で提出する、これが一番ベストな選択と言えるでしょう。
2023.10.26
自治体やその外郭団体が独占的に管理していた公共施設の管理業務を民間企業やNPO法人などに委託し、管理運営の効率化を図る制度である「指定管理者制度」。指定管理者情報センターは、指定管理者を目指している、あるいは現在その任を務めている法人様へのアドバイスやサポートを行っております。指定管理者に関するご相談がありましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
2023.10.19
指定管理者の公募を行うに当たって、応募される団体向けの現地説明会が開催されるケースは少なくありません。中には現地説明会の参加が応募の絶対条件になることもありますので、参加される際には相応の準備をしておくに越したことはないでしょう。指定管理者情報センターでは、現地説明会への参加における心構えやすべきことなどもアドバイスを行っております。
2023.10.11
公益財団法人や公益社団法人の移行認定申請に関するコンサルティングや各種提出書類の作成代行は、その複雑さや文書量の多さ、そして指定管理者制度への豊富な知識が求められるため、税理士・行政書士といった士業の方であっても困難を極めるケースが少なくありません。指定管理者に関する豊富な知識を有する指定管理者情報センターでは、公益法人制度改革に向けたコンサルティングにも対応しております。どうぞお気軽にご相談ください。
2023.10.4
指定管理者は、地域の住民のために開かれている施設の運営に携わる業務です。指定管理者に選定されるには、利用者である住民の方々はもちろんのこと、選定を行う自治体側に評価される必要があります。自治体が行う公募での高い評価を得るための対策に関するご相談は、指定管理者情報センターまでどうぞ。
2023.9.27
指定管理者の選定のために作成される事業計画書。事業計画書において大事なものとは一体何でしょうか。計画書のデザインや見栄え、訴求力のあるプレゼン、これらももちろん大切な要素ではありますが、何よりも大切にしていただきたいのは「どのような管理運営を行うことができるか」を的確にアピールすることにあります。指定管理者情報センターでは、重要なポイントにしっかりとウェイトを置いた事業計画書の執筆方法についてのレクチャー・アドバイスも行っております。どうぞお気軽にご相談ください。
2023.9.20
車両の輸送に陸送業者を使うメリットとは。それは、車の納車先まで業者が安全にノンストップで搬送してくれるので、効率よく輸送されること、また輸送中に事故、あるいは車上狙いなどの盗難被害などに遭いにくく安全であることなどが挙げられます。e-陸送では、最大20社までの見積もりを一括で取得できるので、お客様に最適な業者をかんたんに見つけることができます!
2023.9.13
指定管理者を選定するのは公募を行う地方自治体です。つまり、指定管理者に選ばれるためにはその考え方や提案が自治体側からどれだけ高い評価を得られるかにかかってきます。指定管理者情報センターは、指定管理者の選定・モニタリングに携わった経験から得た視点からより確かなコンサルティングを行っております。
2023.9.6
指定管理者制度は通常の管理委託が原則1年間の契約になることに対して、3~5年ほどの複数年の契約が締結されます。その契約期間が満了した後、再度公募を行い、新たな指定管理者を選定することもあれば、評価如何によっては引き続き前任の指定管理者が再び選定され、業務を継続することもあります。指定管理者情報センターは、これから指定管理者に応募されるというケースはもちろん、再選を目指す現職の管理者へのサポートも行っております。
2023.8.31
広く一般的に知れ渡っている子供向けの遊びやゲームなどに、地域独自のルールが付加されることを「ローカルルール」などと呼んだりします。こういったローカルルールは先に挙げたような遊びの場面だけでなく、大人の方が日々過ごす社会生活においても存在し、特に地方自治体の運営の中ではしばしこのローカルルールが重要な位置に登場することがあります。指定管理者として施設の管理運営を行うに当たって、その地方自治体が持っているローカルルールや習慣を知り、上手に活用することはテクニックとして持っておいて損はありません。
2023.8.23
「指定管理者への応募を検討している」という方でも、現在の状況は千差万別です。事業計画書の書き方からサポートが必要という方もいれば、作成は自身でも可能だが細部にアドバイスが欲しい、という方もいらっしゃいます。相談者の方それぞれの状況に応じたサポートができるのが指定管理者情報センターの強みです。
2023.8.9
指定管理者公募の場において高い頻度で開催される現地説明会。現地説明会は、指定管理者に応募してきた事業者の本気度を探り、測るための機会としての意味合いが非常に強い場所と言っても過言ではありません。指定管理者情報センターでは、現地説明会に臨むに当たってのアドバイスなども行っております。
2023.8.2
指定管理者の応募に欠かせない、自治体へ提出する事業計画書。事業計画書作成に当たって押さえておくべきポイントは様々です。ご覧のウェブサイトには事業計画書作成のポイントをまとめたページがございます。実際にご相談いただく前にそちらも併せてご覧ください。
2023.7.26
日本全国の各自治体で導入・運用されている指定管理者制度。指定管理者に任命されるために必要なノウハウを有しているのが、私ども指定管理者情報センターです。実際に指定管理者の選定・モニタリングに従事した経験があるからこそできる的確なサポートをお約束致します。どうぞお気軽にご相談ください。
2023.7.19
指定管理者制度は、応募される側の方だけでなく公募を出す側である各地方自治体の担当者の方にとっても考えていくべきポイント、知識を深めるべき箇所などが様々ございます。私ども指定管理者情報センターでは、そういった各自治体を対象としたメニューもご用意しております。現状の指定管理者制度について様々な問題意識を持っているけれど、どこに相談して良いかわからない……。そんな時はお気軽にお問い合わせください。
2023.7.12
ある事例に対してノウハウを有する専門家にコンサルティングを依頼するに当たって、依頼者の方がどの程度の知識を有しているかも大切なポイントのひとつになります。指定管理者情報センターは、ご相談いただくお客様のニーズに合わせた商品設計を可能としております。「事業計画書の書き方から教わりたい」「大枠は執筆できるので、細かなところを指摘・修正してほしい」など、現在の状況をお伝えください。
2023.7.5
私たち指定管理者情報センターが指定管理者応募に向けての質の高いコンサルティングを提供できる理由のひとつが、所有している情報量の豊富さにあります。自治体への情報公開請求はもちろんのこと、弊社独自で有するルートから入手した300種類以上の事業計画書、そして1,000種類を越える募集要項・仕様書などにより、全国の指定管理者選定の特徴や傾向を収集・分析することができます。その作業を通じて、それぞれの自治体の方針やライバルとなる他企業・団体が取るであろう戦略に応じたコンサルティングを提供することができるのです。
2023.6.28
現在、指定管理者制度を導入している施設は全国で7万以上あります。その中の実に4割の施設の指定管理者を民間企業やNPO法人などが務めています。これから指定管理者への応募を考えているけれど、そのための手順やノウハウが分からず悩んでいる……。そんな時は私ども指定管理者情報センターにご相談ください。
2023.6.21
施設を所有する自治体側の意向にも左右される面はありますが、指定管理者には管理する施設をより良い形で運営していくための先進的な対応が求められることがあります。そのためには、もちろんただむやみやたらと新しいこと、誰も実践していないことを推進するのではなく、現実的な落としどころを見極めながら一歩先を行った提案を行う必要があります。指定管理者情報センターでは、より良い形での先進的な対応の提案に関するご相談も承っております。
2023.6.14
新たに指定管理者に選出された際にほぼ間違いなく発生するのが、前任の指定管理者からの引継ぎです。引継ぎ対応は基本的には当事者同士で行うものですが、自治体側の担当を交えた席が少なくとも一度は設けられるので、その時には前任の担当者が任期の間は適切に業務を行ってくれるように自治体側と協力体制を敷いてアプローチをかけていくことが求められます。この他にも業務の引継ぎに関しては様々なポイントがあります。それらについてもアドバイスなどを行っておりますので、お気軽にご相談ください。
2023.6.7
指定管理者応募のために作成が求められる事業計画書。計画書の中に盛り込まれるテーマやポイントは様々です。たとえば避けては通れないテーマであるコストの削減に関する事柄などは、削減すべきコストとそうでないものを適切に見極め、論説する必要があります。事業計画書の執筆・作成手法に関するご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
2023.5.31
何かと分かりにくいことの多い指定管理者制度。皆様それぞれに聞いてみたいこと、知っておきたいことがあると思います。指定管理者情報センターでは、指定管理者制度に関する個別無料相談会を開催しております。zoomを利用したオンライン形式の相談会にも対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
2023.5.24
国や地方自治体が、公共施設や公共サービスの運営を民間の法人や団体に委託する制度、それが指定管理者制度です。指定管理者制度が導入された背景にはさまざまな理由がありますが、公共施設を運営するに当たってより効率的な運営を行うために民間側の持つノウハウや知識が役立てる要素が少なからずあるというのがその理由のひとつと言えるでしょう。私ども指定管理者情報センターでは、指定管理者の公募に対しての対策や各種サポートに関するご相談を承っております。
2023.5.17
指定管理者を民間から選出する施設は、選ばれた指定管理者、つまり民間団体と自治体側の協力体制によって運営されます。健全な施設運営のためには、それぞれが持てる力を持ちよって協力体制を整え、様々な課題に取り組んでいく必要があります。運営のためにどのような取り組みを行うかについてのサポート・コンサルティングに関するご相談は、指定管理者情報センターまでどうぞ。
2023.5.10
感謝のお声や苦言・苦情など、施設を利用される利用者の方々からいただくお声は、指定管理者公募の際の事業計画書に欠かせないポイントのひとつと言って良いでしょう。利用者の声を収集するために効果的なアンケート・ヒアリング調査を行うに当たっては、様々なコツやポイントが存在します。指定管理者情報センターでは、そういった細部に関するご相談やそれに対したアドバイスなども行っておりますので、お気軽にご相談ください。
2023.4.26
私ども指定管理者情報センターは、指定管理者への応募に関するサポート・コンサルティングを行っております。対応内容は応募に際してのアドバイスはもちろんのこと、公募を行っている施設への応募を勧めるか否かについてのジャッジなども行っております。指定管理者に関する物事でしたらどのようなことでも回答致しますので、お気軽にご相談ください。
2023.4.19
指定管理者業務は一般企業とは異なる考え方をベースにしていることもあるため、企業的な考え方では採用・評価してもらえないこともしばしばあります。指定管理者情報センターでは指定管理者の公募に対するサポートや施設運営をしていくうえでのアドバイスなどを行っております。これから指定管理者の公募に応募する場合や指定管理者として施設の維持にお困りの際には是非ご相談ください。
2023.4.12
施設の運営には営業的な面もあれば施設のメンテナンスなどの維持・管理に関する面も存在します。指定管理者情報センターでは、指定管理者の公募における事業計画書の執筆について幅広いサポートを行っております。施設の維持管理に関する記述についてのアドバイスももちろん対応しておりますので、お気軽にご相談ください。
2023.4.5
難関な試験や課題を突破するためには勉強が不可欠です。とはいえ、闇雲に勉強をするよりも今現在どのような学習が必要なのか、そのためにはどんな取り組みを行えばよいのか、それらが明確になっていた方が目標がより定めやすくなるというものです。指定管理者情報センターでは「これから指定管理者制度の勉強をしたい」「来年の公募に向けて準備を始めたい」といった人によって異なるニーズに対応できる専用のセミナーを開講しております。
2023.3.29
指定管理者を公募する自治体・公共施設は全国津々浦々様々な場所にございます。そのどれにおいても管理者として求めている条件が完全に一致することはなく、いわゆる高校・大学受験のような共通の必勝法のようなものは存在しません。指定管理者情報センターでは、通り一遍のワンパターンなコンサルティングではなく、それぞれが持つ個別の事情を考慮したオーダーメイド式の戦略を策定し、指定管理者採択へのサポートを行います。
2023.3.15
指定管理者として運営を務める施設の形態によっては、イベントの開催などが業務の内容に含まれることがあります。開催するイベントの提案に関する内容も事業計画書を作成する上では欠かせないポイントのひとつです。施設を利用する地域住民のことをしっかりと見据えて提案することが、指定管理者採択に当たっての審査に重要な役割を果たすことも少なくありません。
2023.3.8
指定管理者情報センターでは、指定管理者制度に関する個別無料相談会を開催しております。公募や施設の管理運営に関するご相談でしたらどのようなことにもお答えしております。会場を利用しての開催のほか、zoomを活用したオンライン上での相談会も行っておりますので、お気軽にご相談ください。
2023.3.1
指定管理者として運営に携わるに当たって、コストの削減と同等、もしくはそれ以上にしっかりと向き合わなければならないのが、利用される方や運営するスタッフ側の安心・安全の確保です。事故の未然防止措置と発生時の危機管理体制については特に詳細に、かつ間違いなく実現可能なものを記載することが求められます。指定管理者情報センターでは施設の安全・安心の確保に関する情報ももちろんサポート可能です。お気軽にご相談ください。
2023.2.22
何事においても、先人から学ぶ知識というものは大切です。指定管理者の仕事においてもそれは例外ではありません。指定管理者情報センターでは、全国の指定管理施設の先進事例や管理運営のヒントになる情報を提供しております。ぜひご参考になさってください。
2023.2.15
指定管理者を務めるに当たって、その施設を管理している地方自治体が独自に有する様々なルールや慣習の存在は避けて通れないものです。施設の管理運営において、それらを把握・理解することはとても重要です。指定管理者情報センターでは、施設の管理運営に欠かすことができない必須知識・テクニックに関するアドバイスを行っております。
2023.2.8
指定管理者制度は、契約期間が満了を迎えれば原則的に再度公募が行われます。これにより管理者が交代するケースもあれば、前管理者が再度選定され引き続き業務を務める場合もあります。私ども指定管理者情報センターでは、初めて応募されるという方はもちろんのこと、再選を目指す現職の管理者の皆様へのアドバイスも行っております。
2023.2.1
指定管理者として円滑な施設運営を行うためには、その施設を利用される方が何を求めてそこに来られるのか、どういった形で施設を利用しているのか、そういったポイントを細かく把握しておくことがキーポイントになります。それを行うことで、これまで利用されていなかった方々の潜在的なニーズの掘り出し、そして今利用されている状況の中に潜んでいる問題点の炙り出しをすることができます。指定管理者情報センターは、こういったポイントを知るためのコンサルティングを行っております。
2023.1.25
弊社の手掛ける指定管理者応募コンサルティングを自信を持ってお勧めできる理由のひとつが、提供できる情報がとにかく「活きた情報」であるという点です。実際に地方自治体にて指定管理者制度の担当を務めあげた経験を持っているからこそ知りえた知識や指定管理者に対しての考え方など、糧となる情報を提供することが可能です。指定管理者への応募を検討していて、それに伴うコンサルタントをお探しの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
2023.1.18
指定管理者への応募の際にその作成が必須となるもの、それが事業計画書です。事業計画書の中身は作成される方によって千差万別ですが、施設を管理・運営していくに当たっての基本方針についての記載は欠かすことのできないポイントと言って良いでしょう。利用者の安心・安全の確保やコスト削減を目標とする管理運営についての記載など、骨格となる方針をしっかりと打ち出せるようにすることが強く求められます。
2023.1.11
指定管理者公募においてほとんどの場合開催される現地説明会。参加が応募の絶対条件になることもある現地説明会ですが、例えば現在の指定管理者と応募される側の方が何らかの取引を行っている場合、その参加がきっかけで取引が停止になってしまう事案が発生することもあります。指定管理者情報センターでは、こういった気づきにくいポイントに関しての案内なども行っておりますので、指定管理者への応募をお考えの際は、ぜひご相談ください。
2022.12.21
事業計画書に盛り込まれることも少なくない施設利用者から寄せられる様々な意見や感想についての項目。「アンケートやヒアリング調査を実施する」というだけでは、具体性が見えにくいところがあります。アンケートを行う回数や収集サンプル数の目標値などを分かりやすい形で掲示するのが、質の高い事業計画書作成の一歩と言えるでしょう。
2022.12.14
私ども指定管理者情報センターが行う指定管理者応募コンサルティングの特徴のひとつが、その豊富な情報量です。各自治体への情報公開請求はもとより、独自のルートで入手した事業計画書・募集要項・仕様書などを元に、選定の特徴や傾向を収集・分析し、より生きた情報を提供することができます。指定管理者公募についてより確実なコンサルティングをお求めの際は、ぜひご相談ください。
2022.12.7
指定管理者制度へ応募するための事業計画書を作成するためのポイントのひとつに、「強み」と「弱み」の分析と把握についての考え方というものがあります。まず、ここでいう強み・弱みというのは、運営予定の施設のことではなく、これから運営を手掛けることになるかもしれない皆様自身のことです。皆様の持っている強みが施設の運営にどのような利をもたらすのか、それを適切にアピールすることは大きなポイントとなると言っても過言ではありません。
2022.11.30
自信を持って行った提案や取り組みが、相手にとっては全く意味をなさない、影響を与えらないというケースは少なからず存在します。指定管理者の公募・施設の管理運営においてもそれは多く起こりうる事象のひとつで、この原因となるのが自治体側と企業・外郭団体の考え方の相違です。建設的かつ公募を行う自治体側にとっても有用な提案をするためのサポートをご希望でしたら、私ども指定管理者情報センターにご相談ください。
2022.11.23
指定管理者制度に関する事柄は、専門的な内容になればなるほど簡単にそれらの情報を取り入れたりするのが難しくなります。弊社代表は、実際に制度の担当者としての実務経験を有しており、より活きた情報を共有できると考えております。オンライン形式の相談会なども随時行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
2022.11.16
私ども指定管理者情報センターでは、指定管理者を務める財団法人・社団法人に特化した公益認定申請のコンサルティング業務も行っております。指定管理者向けに特化したコンサルティングとなっており、財団・社団の現状を踏まえ、かつ将来のビジョンをしっかりと見据えた公益認定申請のアドバイスを行います。実際にご依頼いただく前段階でのコンサルティングの内容や費用に関するご質問なども随時承っておりますので、お気軽にご相談ください。
2022.11.9
指定管理者が行う施設の維持・管理には、様々なポイントがあります。施設の安心・安全を確保するために【維持管理委員会】を設置するといった手法がそのひとつと言えるでしょう。指定管理者情報センターでは、アドバイスの一環としてこういった施設の維持・管理に関する情報も提供しております。
2022.11.2
中小企業診断士の方々が行っている経営コンサルティングは、売上のアップや人員削減を命題としたコンサルティングが行われることが多いと思われますが、こういったテーマは指定管理施設においてはあまりメインに上がることがなく、効果的なコンサルティングを得ることができなかったりすることもめずらしくありません。指定管理者センターは、自治体からの評価を高めるためにはどのような管理運営を行うべきかといった点などにスポットを当てて、より特化したコンサルティングをご案内しております。
2022.10.26
公共施設の管理・運営を民間企業・NPO法人などに委託する指定管理制度。施設の運営には様々な知識・テクニックを求められる場面が少なくありません。指定管理者情報センターでは、そういった知識・テクニックに関するアドバイスを含めたコンサルタント業務を行っております。
2022.10.19
指定管理者を務める方がいれば、当然その方々に対して受け入れる側となる自治体が存在します。自治体側の方々にとっても、指定管理者と良好かつ建設的な関係を築ければ、メリットの方が多くなるというものです。指定管理者情報センターでは、自治体の担当者様向けのメニューのご用意もございます。
2022.8.3
指定管理者として施設を運営するためには、様々なテクニックが求められます。指定管理者情報センターでは、施設運営に関するヒントをまとめて紹介しております。実際にコンサルティングをご依頼いただく前に、そちらも併せてご参照ください。
2022.7.27
公共施設における「サービスの向上」といえば、かつては「休館日の削減」であったり、「営業時間の延長」であったりが主な手法として考えられていました。しかし、時間というものは有限であるため、これらを対象とする対策にはどうしても限界が生じます。指定管理者の選定時に必要な事業計画書に欠かすことのできない「サービスの向上」についての記載に関して、これからの時代にどういったものが求められるのか、またどういったものが現実的な落としどころとして施行できるのかといったアドバイスに関しても、私ども指定管理者情報センターにご相談ください。
2022.7.13
指定管理者制度とは、かつて自治体及びその外郭団体が独占していた一部の公共施設の管理を民間企業・NPO法人等に委任し、管理運営の効率化を図る制度の名称です。指定管理者は原則として公募制で、選定に際しては自治体側の議会内で審査が行われ、選ばれます。私ども指定管理者情報センターでは、一連の公募に関して、自治体元担当者による確かな情報をご案内しております。
2022.7.6
指定管理者にとって重要なのは、その施設を利用する地域住民の方とその施設が所在する自治体の両方から評価される運営を行うことです。特に今現在指定管理者を務めていて、次回の公募でも再任されるためには、それが大きなアドバンテージとなります。住民と自治体の両方から高い評価を得るための方策についてのアドバイス・サポートをお求めの際は、私ども指定管理者情報センターへご相談ください。
2022.6.29
指定管理者への応募の際に提出が求められる事業計画書。事業計画書には、管理運営の基本方針や組織体制、収支計画や施設・設備の維持管理のことなど、記載すべきポイントはあらかた決まっていることが多いです。事業計画書作成の準備や、書き方に関するご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
2022.6.22
指定管理者の選定作業において必ず行われることのひとつが、現在の指定管理者の評価です。その人が管理者を務める施設の利用者数や稼働率、施設の安全・安心確保への取り組みなど、様々なベクトルから評価がなされ、そこから公募のスタンスが決まります。現在進行形で指定管理者を務めている方にとっては、その評価査定において高い評価を得ることが次回の公募への最大の対策になると言えるでしょう。
2022.6.15
ここ数年、公園内の敷地の一部で、キャンプ場やバーベキュー広場などの集客施設を民間が設置・運営する「パークPFI」の公募が、都市部だけでなく地方でも増えています。公園の指定管理者のみなさんは、このような傾向にも注意を払い、導入された場合に向けた対応を検討する必要があると考えられます。
2022.6.8
指定管理者への応募の際には必ず作成を行う事業計画書。事業計画書の作成には様々なポイントがあり、そのポイントを的確に押さえることが肝心です。指定管理者情報センターのウェブサイトでは、こういった事業計画書作成に必要なポイントに関する紹介ページも設けております。事業計画書の作成をはじめ、指定管理者への応募に関連する情報を多数掲載しておりますので、ぜひご参考になさってください。
2022.6.1
指定管理者の公募に当たって、現地説明会が開催されるのは稀なことではありません。時には現地説明会の出席が応募の絶対条件になることもありますので、可能な限り参加されることが望ましいです。当ウェブサイトには現地説明会に関して説明したページもございますので、ぜひご参照下さい。
2022.5.25
ひとくちに指定管理者への応募を検討されている方と言っても、そのスタンスは人によって様々です。事業計画書の書き方から知りたいという方もいれば、事業計画書作成に関しての大体のノウハウは持っているのでプラスアルファのサポートが欲しいという方もいる、といった具合です。指定管理者情報センターのサポートメニューは、ご相談いただいた方のニーズに合わせた対応が可能です。
2022.5.18
指定管理者は、地方自治体との関係が切っても切り離せません。例えば、運営において自治体側から事業計画書に記載のない要求を求められることも少なくありません。事業計画書にないことを完全に対応する必要はありませんが、とは言えすべてをシャットアウトしてしまうのも心象的によろしくありません。そんな時は、代替案を提示することにより、関係性を大切にしながら運営を進めることができます。
2022.5.11
今現在、指定管理者を務められているという方の中には、管理・運営に関して大なり小なりのお悩み・お困りごとをお持ちの方も少なくないと思います。「施設の利用者数が伸び悩んでいる」「自治体の担当者から降りてくる指示や、担当者の考え方が理解できない」などなど、例を挙げるだけでもきりがありません。現行の指定管理者さんで、これらのお悩みに対するサポート・コンサルティングをご希望の際は、私ども指定管理者情報センターへご相談ください。
2022.4.20
各自治体の指定管理者制度への応募を検討しているけれど、どんな情報を参考にしたらいいか分からず困っている……。そんな方は、ぜひ私ども指定管理者情報センターが運営する当サイトをご覧ください。サイトを運営しているのは実際に指定管理者選定・モニタリングに携わった経験者ですので、どこよりも活きた情報をご紹介できます。サイトを見て生じた疑問や質問などにもご回答いたしますので、お問い合わせもお気軽にどうぞ。
2022.4.13
指定管理者の公募に当たって、ほとんどの場合現地説明会が開催されます。自治体によってルールはまちまちですが、可能な限りこの現地説明会には出席した方が良いでしょう。現地説明会に参加することで、説明会でしか配布されない資料が手に入ったり、指定管理者に応募を考えている他の企業・法人の情報を得ることができたりと、メリットになる面が多数あります。
2022.4.6
指定管理者に応募する際に、必ず作成を要するのが事業計画書です。事業計画書の様式を受け取り側の自治体が提示するのは、公募が開始される時です。締め切りまでのわずかな時間から書き始めるのではなく、公募が始まる前に様式を想定し、記載内容の検討を行うことが重要となります。
2022.3.30
指定管理者の選定は、原則として公募によって行われます。その後、契約期間を経て、期間が満了すれば再度公募が行われ、新たな人員が選定されます。長く指定管理者を続けるためには、その公募にしっかりと選ばれる必要があります。指定管理者に選ばれるためのノウハウに関するご相談は、指定管理者情報センターへお尋ねください。
2022.3.23
現在指定管理者を務められている方でも、改善すべきこと、是正しなければならないことなどを把握し、それらに対し何かしらの措置を講じないと、次回公募の際に苦戦してしまう可能性が高まります。次回公募に勝ち、次の任期も指定管理者を務めるためには、自治体やその地域に住まう住民に評価される運営を行う必要があります。弊社では、現行の指定管理者向けのサポート・コンサルティングも行っております。
2022.3.16
当サイトでは、指定管理者への応募を検討されている方のサポートを行っております。サポートメニューは、事業計画書の企画立案やそれに伴う文章作成の依頼、文章をご自身で作成できるという方には企画立案のサポートと作成した文章の添削、その他、応募される方それぞれのニーズに合わせたコンサルティングプランのご提案が可能です。「ここまではできるのでここをサポートしてほしい」というようなご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
2022.3.9
指定管理者に応募する際に必ず作成する必要があるのが、事業計画書です。事業計画書には、特に記載すべき内容というものがあります。ご覧のウェブサイトには、事業計画書作成時におけるポイントをまとめたページがございますので、そちらも是非ご覧ください。
2022.3.2
私ども指定管理者情報センターでは、公益法人制度改革コンサルティングのご案内も行っております。公益財団法人・公益社団法人の移行認定申請は、税理士や行政書士といった士業の方もコンサルティングを行っていますが、指定車管理者制度に対する知識を有していないために、適切な処理ができない可能性があります。指定管理者の方向けのコンサルティングができるのは、確かな知識を持った専門家の強みです。
2022.2.23
指定管理者情報センターでは、指定管理者制度に関する個別無料相談会を開催しております。会場を設けての開催はもちろんのこと、昨今の状況を鑑みてのオンライン形式での相談会もご案内しております。指定管理使者制度について聞いてみたいと、気になることなどありましたら、お気軽にお問い合わせください。
2022.2.16
指定管理者への応募を検討されている方の支援を行うコンサルティングサービスは様々なところで展開されていますが、ほとんどの場合は行政書士や中小企業診断士といったいわば外部の方が務められていることが多く、行政側の生きた情報を得にくいという可能性があります。弊社は、行政側である自治体で実際に指定管理者制度の担当を務めた経験者がコンサルティングを務めますので、より身になる生きた情報を提供することが可能です。
2022.2.9
公募で選ばれる指定管理者。現在進行形で指定管理者を務められている方や、これから指定管理者を目指される方にとって、生きた情報は必要不可欠です。ご覧のウェブサイトは、自治体の元担当者が運営する、指定管理者のためのウェブサイトです。指定管理者に関する有益な情報を多数掲載しております。
2022.2.3
自治体には、それぞれの決まり事や慣習といったローカルルールが必ずと言っていいほど存在します。これがネックとなって、指定管理者になっても十分な意思疎通が取れず、互いに不信感を抱いてしまうことも少なくありません。管理運営に必要な知識、知っておくと役立つテクニックなどをお知りになりたいなら、ぜひ当サイトをご活用ください。
2022.1.26
指定管理者の公募に当たっては、ほとんどの場合において現地説明会が開催されます。応募の絶対条件に現地説明会への参加が求められることもありますので、可能な限り現地説明会に参加した方が良いでしょう。当ウェブサイトでは、現地説明会に関するご案内も紹介しております。
2022.1.19
指定管理者制度とは、従来であれば自治体、もしくはその外郭団体が独占していた公共施設の管理を民間企業やNPO法人にも広げることにより、管理運営の効率化を図る制度です。制度が導入されて20年近くになりますが、制度が導入されている施設の内4割に民間側の指定管理者がついています。指定管理者情報センターは、今現在指定管理者を務められている方、これから指定管理者を目指される方にとって有益な情報を展開しております。
2022.1.12
指定管理者を必要としている施設・企業・団体は様々ありますが、それぞれの状況に応じて求められる戦略は異なります。私ども指定管理者情報センターでは、既存の情報・マニュアルに則ったコンサルティング法ではなく、個別の事情に応じたオーダーメードの戦略を策定し、提案できるようにするためのサポートを行います。
2021.12.22
一般的な企業であればプラスの取り組みとして捉えられる、人件費やコストの削減。指定管理業務においてはそうした取り組みがプラスに捉えられるとは限りません。その施設の職員も住民と考えるため人件費を削減することが住民の生活を脅かすものと考えられることもあるからです。指定管理業務には公的な考えを理解する必要があります。指定管理者情報センターではそうした自治体の発送や考え方を説明し、どのような考えが自治体から高い評価を得るものかを解説していきます。
2021.12.15
指定管理業務は、業務を行っていくうえで通常の企業間の役務提供とは異なる点が多く発生します。それは企業と自治体の業務に関する考え方の違いから起こるものです。指定管理者情報センターでは弊社代表の自治体での指定管理者担当の経験を活かし、指定管理業務に関するコンサルティングを行っています。
2021.12.8
指定管理者情報センターでは、現行、指定管理者として施設の管理を行っている方のお手伝いや、これから指定管理者に公募する方のお手伝いを行っております。指定管理者業務には、通常のBtoBのビジネスとは異なる点が多々あります。指定管理者に関することでお困りの際には是非ご相談ください。
2021.12.1
指定管理者公募を行う際には現行の管理方法よりも優れた方法やよりコストを抑えた方法を提案しても自治体にその提案が認められないこともあります。その背景には企業と自治体の間には考え方のギャップがあります。自治体には自治体としての考えがあるため、指定管理業務を行う際にはそうした考えを理解する必要があります。指定管理者情報センターでは元自治体の指定管理者の経験を活かし、コンサルティングを行っていきます。
2021.11.25
指定管理者業務のコンサルティングを行っている企業は多くありますが、その多くは実際の指定管理の業務内容を見たことがないというケースがほとんどです。管理者を指定する側は自治体の指定管理者の担当職員であり、そうした業務を経験した人が一企業でコンサルティング業務を行うことが珍しいからです。当社の代表は実際に自治体で指定管理者の担当職員の経験があり、自治体の意図と企業側の実情を把握してコンサルティングを行うことができます。
2021.11.17
公的な機関と事業を行う場合、気を付けなければならないことはたくさんあります。そうした事柄というのは行政としては当たり前のことかもしれませんが、一企業としては驚くべきこともあります。そうした情報と言うのはなかなか入手することができません。指定管理者情報センターでは指定管理者に関する情報に特化。これから指定管理者を目指す方や現行指定管理者として何か悩みを抱えている方はぜひご覧ください。
2021.11.10
指定管理者の業務は通常の企業間の取引さサービスの提供とは異なり別の思考で考えて対応しなければならないことがあります。指定管理者情報センターでは自治体の指定管理者担当の経験を活かし指定管理業務を行っていくうえで必要なノウハウを掲示しています。
2021.11.4
指定管理者について調べようと思ってもなかなか本当に知りたい情報が書かれているサイトに出会うのは難しいでしょう。当サイトは自治体の指定管理者選定・モニタリング経験者によって運営されています。指定管理者として施設を運営しているけれど困っていることがある、これから指定管理者を目指している方には非常に有益な情報となっています。
2021.10.27
指定管理者の業務をこれから新しく始めようと思っても、一般的な企業とのやり取りとは異なる点があるため、なかなか参入しにくいというのが現状かもしれません。指定管理者情報センターでは自治体の指定管理者を行っていた経験からお客様の応募・運営をサポートいたします。
2021.10.20
指定管理者はその地域に密着した業務を行っていきます。そのため指定管理者としての実績はその地域における信頼につながっていきます。しかし応募を考えていたとしてもその応募にあたってのノウハウがなければなかなか難しく、手が出せないというのも現状でしょう。指定管理者情報センターではそんな指定管理者についての情報を掲載しております。応募をあきらめる前に是非当サイトをご覧ください。
2021.10.13
新しく指定管理者として応募したい。だけれどこれまで指定管理者として施設の管理を行ったことがないためどうしていいのかわからないという方は指定管理者情報センターにお任せください。指定管理者部門の自治体担当者としての経験や多くの企業をコンサルティングしてきた実績であなたの応募のお手伝いをいたします。
2021.10.6
指定管理者として施設を管理することによって、その地域においての実績や信頼をつくることができます。しかし、今までそうした経験のない企業にとって新たに受託を勝ち取ることは非常に難しいことでしょう。指定管理者情報センターでは指定管理者の応募をサポート。自治体の担当者としての経験を活かしコンサルティングサービスを行います。
2021.9.29
指定管理者制度は導入する自治体にとっても受託する民間企業にとってもメリットのあるシステムです。受託する民間企業にとっては、自治体などの公的な団体から継続的に売り上げを確保することや実績を作ることによって企業としての信頼性を確保することができます。指定管理者制度に応募をお考えでしたら指定管理者情報センターにご相談ください。
2021.9.22
多くの指定管理者応募コンサルティングサービスは中小企業診断士や行政書士によって行われています。そのため行政側の情報や行政が何を求めているのかということについてはそこまで多くの知識を持っているわけではありません。当社代表は自治体で指定管理者制度の担当者としての経験があるため実際の選定過程や自治体の考えなどについても熟知しています。そうした知識や情報を活かすことで他社にはまねできないコンサルティングサービスをご提供することができます。
2021.9.15
指定管理者として行政の一端を担っていくためには、通常の企業としての活動を行っているときには意識しなくても問題にならなかったことも気を付けていく必要があります。特に現在では動画などの録画や会議内容の録音が簡単にできるようになっているため、そうしたミスをしないために最新の注意を払う必要があります。
2021.9.8
指定管理者の公募や管理運営を行っていくうえで最も重要なことは、企業と自治体の考え方のギャップを埋めることです。一見企業からすると非常に良い提案だと考えられることだとしても、自治体としてはマイナスだと判断されることもあります。指定管理者情報センターでは指定管理者選定やモニタリングに従事した経験から自治体から見た発想をご紹介いたします。
2021.9.1
指定管理者精度とは、公の施設の管理や運営を法人やその他の団体に包括的に代行させることです。従来の委託との違いは一部を業務を委託するのではなく、その施設や事業単位で代行するということです。制度の利用にあたっては公募が行われます。一般の企業間のコンペとは異なり、自治体として業務を行うため、通常の企業活動として是と考えられることでも自治体の代行者として行う場合には問題になる場合もあります。
2021.8.26
指定管理者情報センターでは現行指定管理者として施設管理を行っている企業様への施設運営の改善のコンサルティングサービスも行っております。全国の自治体の先進事例や元自治体担当者の経験からご依頼主の状況に合わせたサポートを行っております。施設管理で問題点がある、次回の公募に向けて何か対策をしたいなどのご要望がございましたら指定管理者情報センターにご依頼ください。
2021.8.18
指定管理者の公募を勝ち取るためには通常の企業間のコンペとは少し違った対策が必要になります。自治体はどのような目的からその事業の指定管理者の公募を行っているのか、応募するにあたって気を付けなければならないことは何かなど公募に向けて必要な情報を開示しそのサポートをしていきます。準備段階での作業を軽減し、より高い確率で公募を勝ち取るために指定管理者情報センターにご相談ください。
2021.8.4
次回の指定管理者の指定を勝ち取るに当たって、プレゼンテーションの準備・事業計画書の作成は非常に重要な事柄です。公募を行っている自治体にとって魅力的な内容とは何かということをきちんと考え、その内容に合わせた計画を建てていくことが大切なのです。
2021.7.28
指定管理者として施設の管理運営を行っていくためには自治体のルールや公的な機関の考え方というものを理解したうえで企画を立て、実行をしていく必要があります。そこでは通常の企業としての管理運営とは異なる目線が必要であり、自治体と上手に歩調を合わせていく必要があります。指定管理者情報センターでは自治体の指定管理者担当としての経験を活かし、これから指定管理者を目指す企業や現行指定管理者として施設の管理運営を行っている方へコンサルティングを行っています。 2021.7.21
指定管理者として施設を運営していくなかでも最も苦心するのは指定管理者として選定されること、そしてそれを継続していくことでしょう。その中でも最も注意しなければならないのは民間企業と自治体の考え方の違いです。一般企業では是とされることであっても自治体の職員からすると非とされることがあります。そうした公の考え方を知っておくことが何より大切なのです。 2021.7.14
指定管理者情報センターでは、これから指定管理者を目指す法人の方、現行の指定管理者で管理にお困りの方のサポートをしております。公的な施設運営は企業が行う営利活動とは異なり、思わぬことが思わぬ結果に繋がることもあります。当情報センターでは自治体元指定管理者担当が自治体側から見た指定管理者を分析しサポートをしていきます。 2021.7.7
現在指定管理者として施設の管理を行っている企業にとって、次回の公募に向けて重要なことは住民そして自治体に高い評価を受けることです。そのためにはそのためには自治体の担当者の考えを理解することが重要です。指定管理者情報センターでは住民はもちろん自治体からも高い評価を受けるためのコンサルティングを行っています。現行の施設管理にお悩みの方は是非ご相談ください。 2021.6.30
指定管理者として施設の管理運営を行っていくうえで難しいことのひとつとして利用者の範囲があります。公的な施設の場合、利用対象者は住民全体であり幅広い方に利用していただけるようにする前提で利用者数の改善や利用環境の改善を行わなければなりません。 2021.6.23
当社では指定管理者への応募、指定管理施設の管理運営サポート、公営貴法人制度改革コンサルティングを行っております。他の指定管理者コンサルタントとの一番の違いは当社の代表が自治体で指定管理選定の経験があるということです。これから指定管理者を目指す方、現行指定管理者で運営にお困りの方、是非ご相談ください。 2021.6.16
指定管理者制度は行政側にとっても企業側にとっても有益な制度です。しかし行政と企業の間には価値観の違いなどから本来機能すべき効果を十分に発揮できていないこともあります。指定管理者情報センターでは応募に関するお手伝いや施設運営のアドバイスなどのコンサルティング業務のお手伝いをしております。 2021.6.9
指定管理者への公募にあたっては、事業計画書の作成が必要になります。事業計画書の作成に当たってはきちんと自治体の求める運営方針に適した事業計画書を提出する必要があります。基本となるポイントは同じですがそれぞれの事業内容に合わせて必要な項目を考慮していく必要があります。 2021.6.2
指定管理者として業務を行うということは、公的な機関として利用者から見られることになります。そのため、表現なども細心の注意を払う必要があります。住民に不快感を与えないよう特に印刷物に関しては注意を払って作成する必要があります。 2021.5.26
指定管理者情報センターでは、指定管理者への応募のサポートや指定管理者としての管理運営のサポートなどを執り行っております。どのような考え方で提案や管理を行うかをご説明いたします。現在指定管理業務を行っていて困っていることがある場合やこれから指定管理者として応募を行なおうとしている方はぜひご相談ください。 2021.5.19
指定管理者として公共の施設を管理・運営することは、民間の企業としては非常に大きな案件となることもあります。しかし、その一方でそうした公共の業務に対してのノウハウが少なく二の足を踏んでいるという企業様も多いのではないでしょうか。指定管理者情報センターでは元自治体の職員から見た目線でコンサルティングを行っていきます。これから指定管理者を目指していきたいけれどどうしていいかわからない、という方はぜひご連絡ください。 2021.5.12
指定管理者制度というのは実は多くの施設に利用されています。例えばJリーグで利用されるスタジアムの多くは自治体の運営ではなく指定管理者によって運営されています。そうした際には施設および付属設備の維持管理や使用承認関連業務、指定管理者による企画立案などが指定管理業務として行われています。 2021.4.28
コロナウィルスによる影響がいまだ続く中、施設を管理していくうえでその衛生面での問題点や利用者数・稼働率などで頭を悩ましている指定管理者の方もいらっしゃるでしょう。指定管理者情報センターでは指定管理者への応募の対策から施設管理の運営サポートまで幅広くサポートいたします。 2021.4.21
指定管理者に応募したり、また管理運営を行ったりしていくうえで最も大きな障壁は企業と自治体職員の間の考え方のギャップです。一般企業としては合理的であると思える行動であっても自治体職員から見ると問題のある選択であることも少なくありません。指定管理者情報センターでは元自治体職員の代表の経験を活かし、指定管理者のサポートを行います。指定管理者に応募する際や指定管理者として管理運営を行っていく際にはぜひご相談ください。
2021.4.14
四月は年度の始まりであり、公的な機関でも多くのことが始められる時期です。指定管理者として新しく施設の運営を行っている人も多くいらっしゃるはずです。指定管理者情報センターでは指定管理者制度にまつわることのご相談を承っております。実際に指定管理業務をはじめてみてお困りのことがある場合にはご相談ください。 2021.4.8
指定管理者として業務を行ううえで常に意識をしなければならないのは、民間企業と自治体の考え方のギャップです。例えば施設運営を行っていくうえでコストの削減は重要な項目のひとつです。しかし、人員削減という形でコストの削減を進めていくと安全面の確保ができなくなる恐れや自治体の生んでいた雇用をカットしたと考えられるおそれもあります。 2021.3.31
指定管理者情報センターでは指定管理者にまつわる情報を発信しています。また、独自に入手した資料から各自治体の選定方法の特徴や傾向を分析しています。指定管理業務に従事した経験がある代表を中心にその自治体に応じた公募、運営へのコンサルティングを行っています。
2021.3.24
指定管理者の業務というのは通常の企業間や顧客との取引とは違い、自治体とそして地域住民を相手に取引を行うことになります。そのためそのシステムをきちんと理解しておかなければトラブルに発展することもあります。指定管理者情報センターではそんな自治体とのやり取りを円滑に行うためのアドバイスやコンサルティングを行っています。
2021.3.17
指定管理者情報センターでは当サイト内で指定管理者へのお役立ち情報を配信しているほか、現地説明会やプレゼン、また施設を運営していくなかで必要な知識などのコンサルティングを行っております。自治体へのプレゼンや自治体との付き合い方などは通常の企業と仕事を行っていくのとは少し違った感覚が必要になります。指定管理者情報センターは代表が元自治体の担当員であった知識を活かして、ご相談に乗っていきます。
2021.3.10
指定管理者情報センターではこれから指定管理者応募を行おうとしている法人様や現行指定管理者として施設管理を行っている法人様へのサポートを行っております。自治体での指定管理業務への従事経験から自治体側の立場から見たコンサルティングを行います。
2021.3.3
指定管理者はあくまで自治体に指定を受けて施設を管理しているという立場ではありますが、利用者からすると公的な側の立場であると判断されます。そのため発信する情報などに関しても公的な立場であると考えて発信する必要があるのです。通常の企業としての発言ならば問題がないことであっても指定管理者という立場ではやり玉に挙げられることもあります。公的な立場であることを意識し利用者が不快な気持ちにならないように考慮する必要があるのです。
2021.2.24
指定管理者に応募する際には、その自治体の仕様書の確認をするだけでなく国政全体のことも把握しておく必要があります。国全体として決められた方針はいずれ地方自治にも影響も及ぼします。そのため提案する内容にもそうした先を見たものをより取り入れていくことによってより評価を受けることができるのです。
2021.2.17
指定管理者制度とは、地方公共団体がそれまで行っていた公の施設を一般企業やNPO法人などに代行してもらうことです。2003年から施工された制度で現在では多くの施設の管理運営が指定管理者によって行われています。公的な性質を残すため、管理を指定した地方公共団体などとの打ち合わせなどを行い運営をしていくことになります。そのため、通常の施設管理・運営とは異なりさまざまな慣習などがあります。指定管理者情報センターでは指定管理者制度についての情報を発信しています。指定管理者に公募しようとしている方、指定管理者として施設の運営をしているものの運営にお困りの方は是非ご相談ください。
2021.2.10
指定管理者として施設を運営していく中で大切なのは公益性です。いつも施設を利用している方の利便性だけでなく、まだ施設を利用していない方に対してもより利用しやすくなるように施設の改善をしていかなければなりません。民間の運営している施設のように単純に最も利益が出ることを最小公倍数とするのではなく、対象となっている住民の利潤が最も大きくなること考えていかなければならないのです。
2021.2.3
指定管理者に指名されたものの、今まで民間企業との間で行っていた業務とは異なり、自治体の様々な慣習などに頭を悩ましている方もいらっしゃるでしょう。自治体はどう考えているのかそして自治体とのやり取りをどのように行っていくのかは、業務を円滑に進め次の指定管理者に指名されるためにもしっかりと考えていかなければならない事柄です。指定管理者情報センターでは自治体職員の発想や自治体特有のルールを説明しています。ぜひ一読してください。
2021.1.27
指定管理者として、施設を運営していく中で、公的施設としてどのように感染防止対策を行っていくべきなのかということで頭を悩ましている方もいらっしゃるでしょう。これから施設の運営を行っていく中で感染防止対策というものは欠かせない事柄です。各取り組みを行っていく中で、どの法令や条例を根拠にどのような施策を行うのかということについて施設内で確実にまとめていく必要があるのです。指定管理者情報センターでは自治体から見た発想をアドバイスするとともに、どのような提案を行うべきかをご紹介していきます。
2021.1.20
政府が「小さな政府化」を進めていくなか、自治体も同様にその業務内容を少しずつ外部に委託しています。全国の指定管理者制度が導入されている施設のうち、おおよそ半分弱が民間企業によって管理されています。一見自治体によって管理運営されているように見えても、調べてみると指定管理者によって管理運営されていることが多いのです。しかし、民間企業にとって、そうした公共の施設に参入するのは非常に敷居が高いと感じるかもしれません。指定管理者情報センターでは、応募から施設の運営までの相談を受け付けています。
2021.1.13
指定管理者の公募に関しては、重要政策の影響を非常に大きく受けます。そのため世論や政権などによって指定管理者に求めるものも大きく変わってくるのです。現在では公衆衛生やデジタル化の面からキャッシュレス決済などを取り入れた事業者が多くいました。自治体が新たに行おうとしている施策に対してどれだけ対応できるかということもひとつの基準となっているのです。指定管理者情報センターは指定管理者についての最新の情報を発信すると同時に、応募サポートや運営管理サポートも行っております。指定管理者に応募をお考えの際には是非ご連絡ください。
2020.12.23
指定管理者をして施設を運営していく中で、ボランティアの採用や地域連携を行っていくこともあります。ボランティアの採用は施設の利用者とは異なった扱いになります。利用者の場合には平等に利用してもらうという原則が働きますが、ボランティアの採用などの場合には指定管理者側でその人選に関して判断を下すことができます。実際に施設の運営をしていく中で本当にきちんと業務を行ってもらえるボランティアの方のみ選別することが可能です。
2020.12.17
本年も師走を迎え、残すところ数週間となりました。指定管理者として施設運営をしていく中でも2020年はコロナやオリンピックの延期などさまざまな予期せぬ出来事があったと思います。ひとつの大きな変化として衛生環境に対してより敏感になったことがあります。来期以降の指定管理者の公募にあたってそうした項目が今まで以上に注視されることになるでしょう。指定管理者情報センターではこれからの公募や現行の管理者が施設運営をしていく中で役立つ情報を提供しています。
2020.12.09
現在指定管理者として施設の運営をされている方の中には次回の公募に向けてさまざまな対策をされている方もいらっしゃると思います。しかし、現在の運営の中で、利用者数が伸び悩んでいるという状況や自治体のモニタリングで良い評価が得られていないという方もいらっしゃるでしょう。指定管理者情報センターでは現行の指定管理者の方がより良い評価を得るためのコンサルティングサービスも行っています。指定管理者として運営にお悩みの方は是非ご相談ください。
2020.12.02
コロナ禍の中少しずつ生活様式も変わってきているように感じられます。自宅からできるだけでないで生活を行うことや店舗や施設でのアルコール消毒や検温などにも多くの方が慣れてきたように思えます。その一方で施設を運営していくうえで、衛生環境に対してより高い意識を持って取り組まなければならないようにもなってきました。今後、施設でのイベントの開催には常にそうした衛生に関する対策も取り組まなければなりません。
2020.11.25
指定管理者制度はその自治体の状況に応じて利用されるものであるため、応募内容もその施設ごとによってさまざまです。期間や内容などについてもある程度の慣例がありますが、応募要項によってさまざまなです。応募して指定されるためには、その自治体が何を求めて指定管理者制度に踏み切ったのかを読み取る必要があります。指定管理者情報センターでは自治体での指定管理者担当経験もある代表が、経験者ならではの視点から相談に乗ることができます。
2020.11.19
指定管理者情報センターでは指定管理者応募のコンサルティングを行っています。当社代表は自治体で指定管理者制度の担当者としての経験があります。制度そのものへの理解はもちろん、選考の過程などにも熟知しており、他の指定管理者コンサルティングにはまねできないコンサルティングを行うことができます。
2020.11.12
施設の管理を行っていくうえで重要なこととして安全の確保があります。自治体が所有する公的な施設の場合、一般の施設以上にそうした安全性の確保が重要となります。指定管理者に応募する際には、その安全の確保に関して十二分に配慮をした企画書を提出するようにしましょう。
2020.11.04
指定管理者制度は自治体が所有管理している施設をより効率よく運営するため民間の企業のノウハウを利用して運営していくというシステムです。しかし、公募を行っている母体は自治体ですので、企業として有効な方策だと考えて応募してもその意見が採用されないこともあります。指定管理者情報センターでは、代表が指定管理者選定を行った経験から自治体側から見た指定管理者応募への有効な情報を発信しています。
2020.10.28
自治体は指定管理者の評価をするためにモニタリング調査を行っています。現行指定管理者として施設の管理を行っている場合、次回の公募の際の事業計画書にそのモニタリング結果を利用するのもひとつの方法です。公募対策として非常に高い評価が得やすくコストパフォーマンスが高いからです。年度末にかけてモニタリングを行う施設は多くあります。そうした対策を真剣に行うことによって次回の公募で有利に立つことができます。
2020.10.21
小さな政府化が進み、多くの公共の施設が指定管理者の公募を行っています。しかし、その歴史が浅いためかそうした公募に対するコンサルティングを行うことができる業者は非常に少ないのが現状です。当社では自治体で指定管理者業務に従事した経験をもとに、自治体目線から見た指定管理者応募へのポイントを包括的にコンサルティングしていきます。
2020.10.13
オリンピックの開催年や翌年には、体育関連施設の指定管理者の応募に大手企業が増加する傾向があります。その背景としては自社に所属するオリンピック選手によるスポーツ教室などを開催するという事業計画を打ち出しているからです。しかし、必ずしもそうした大手企業が勝つとは限りません。指定管理者を公募している自治体は、その公募にあたって目的があります。その目的をくみ取ることによって中小企業でも指定管理者に選定されることができるのです。
2020.10.08
指定管理者の方にとって契約の更新時期と同じである公募の時期が近づいてくると、他の競合先がいるのかどうか不安になることもあるでしょう。該当施設に情報公開資料請求などがあったときには要注意が必要です。良い管理運営を行っていれば、心配をする必要はありませんが、ある程度競合先の情報を集めておくことも引き続き指定管理者を継続して指名してもらうためには重要なことです。
2020.09.30
指定管理者に指定されて施設の管理を行うことは企業側にとってもプラスになることがあります。施設管理のノウハウの構築や地域における知名度の向上、公的機関とのパイプの構築など、通常の企業運営ではなかなかできにくいことを行うことができます。しかし、応募するにあたって知っておかなければならないことも多くあります。指定管理者情報センターでは自治体側からの発想を説明し、これから応募する企業や現在管理を行っている企業へ情報を紹介します。
2020.09.23
指定管理者の応募をするにあたって知らなければならない知識は非常に多くあります。一般企業の受注に対するコンペティションとは異なり、明らかに一般企業から見れば優れているであろう応募者が破れることもあります。管理者を指定する自治体には一般企業とは異なる事情があります。指定管理者情報センターでは、指定管理者の応募・運営をしていくにあたって必要な情報を提供していきます。
2020.09.15
指定管理者情報センターは、指定管理者の方やこれから指定管理者に応募しようとしている方にここでしか得られない情報を提供しています。指定管理者は自治体や住民を対象にサービスを提供しなければなりません。そのため通常の企業が行うサービス提供とは異なる点がたくさんあります。報告書の作成やセルフモニタリングの方法など、さまざまな疑問にお応えします。
2020.09.08
施設の管理を行っていくうえで、頭を悩ますこととして設備の修繕があります。指定管理者として故障した設備に対してはきちんと状況や修繕方法、現行の対応状況や陽などをまとめて自治体に報告を行うべきです。しっかりとした対応を行えば自治体の職員に対しての評価も上がります。
2020.09.02
指定管理者の業務は、指定された施設をきちんと管理することだけでなく、住民の潜在ニーズを拾い上げていく必要性があります。住民がその施設に対して信頼をし、利用しやすい施設であるもしくは役に立つ施設であると判断することは、指定管理者を続けていくうえで非常に有利に働くことは間違いないでしょう。
2020.08.26
利用者の利便性をよくする方法のひとつとして、他の指定管理者と連携するという方法があります。新規事業を実施する場合にお互いのもつノウハウを提供し合うことによってよりスムーズに事業を行うことができるからです。また、連携を広げることによって、自治体側が指定管理者を代えにくいという利点もあります。
2020.08.19
指定管理者として施設の管理をしているときには、業務そのもの以外にも努力しなければならないこともあります。それはきちんと運営していることを伝える努力です。おそらくほとんどの指定管理者の方が施設をより使いやすく、そして無駄なコストを抑えてということに尽力しているはずです。しかし前者の部分についてはきちんと利用者の方にわかるように行わなければなりません。
2020.08.05
指定管理者として業務を遂行することになると、自治体のさまざまなルールなどに合わせて業務を行っていく必要があります。自治体ときちんと意思の疎通を行っていくためには、きちんとそうした ルールや制度、慣習を把握したうえで、きちんと内容を説明していく必要があります。
2020.07.31
多くの場合、事業計画書は、前回公募の様式とほとんど変わりません。そのため、公募が開始される前にあらかじめ前回の様式で記載内容を決めておいたり、必要書類を集めておいたりする必要があります。
2020.07.15
指定管理者制度の導入の目的のひとつとして経費の削減というものがあります。自治体が直接管理運営をする場合には、その施設に自治体の職員を配置しなければなりません。それに対して指定管理者制度の場合には指定管理者が人件費なども含めて管理を行うことになります。
2020.07.08
新たに指定管理者に公募する際には民間企業のノウハウを取り入れたとしてもそれが受け入れられないということもあります。最も大きな原因としては、自治体との考え方のギャップです。企業が主として利益やコスト、そしてサービスの向上を目的としてサービスを展開しているのに対して、自治体は公平性というものを主眼において考えているからです。
2020.07.01
公共の施設に対する業務委託はある業務のみに対する委託となります。そのため主導は地方公共団体にあり、一部の業務に対しての委託となります。それに対して指定管理者制度の場合には管理として包括的にその施設の管理を行うことになります。
2020.06.25
自治体は指定管理者の評価を前年度と比較して行っています。そのため、事業計画書にあった数字のクリアや前年度数値同月数値のクリアなどは指定管理者として評価されるために必要不可欠な要素となります。指定管理者として施設を管理運営していくためにはそうした数字を常に意識していく必要があります。
2020.06.17
自治体は指定管理者の評価を前年度と比較して行っています。そのため、事業計画書にあった数字のクリアや前年度数値同月数値のクリアなどは指定管理者として評価されるために必要不可欠な要素となります。指定管理者として施設を管理運営していくためにはそうした数字を常に意識していく必要があります。
2020.06.09
指定管理者として施設の管理を行っていくには、自治体の担当者と協力して行くことが大切です。担当者への連絡や報告はきちんと資料を作成したうえで、書面で提出するのが好ましいです。その施設の管理・運営を委託するために自治体は指定者管理制度を利用しています。自治体に円滑な対応をしてもらうためにも、担当者を動かすだけの資料作りが必要になるのです。
2020.06.02
自治体が指定管理者制度を利用するには何かしらの理由があります。コストの削減や施設の改善のほか、民間のノウハウの導入など、その施設の課題を解決するために民間の活力を利用しようとしているのです。指定管理者制度の公募に申し込むさいには、その自治体が求めているのはなんなのかということをきちんと把握してから対策を講じなければなりません。 2020.05.26
初めて指定管理者に応募する際には、その施設の特性の確認や募集に対する対策を行う前に、そもそも指定管理者制度とはどういったものなのかという基礎知識を知る必要もあります。通常の民間企業に対するプレゼンとは異なる対策がそこには必要になります。