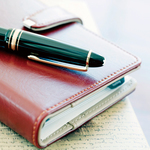このコーナーでは、指定管理者公募に欠かせない現地説明会やプレゼンについて、知っておくべき知識をご説明します。また、現地説明会やプレゼンは、番外での駆け引きも日常的に行われています。これについても、公開できる範囲?で紹介します。
【このコーナーの内容】
・現地説明会
・公募時の質問と回答(その1)
・公募時の質問と回答(その2)
・デザインとプレゼン
・プレゼン留意事項(その1)
・プレゼン留意事項(その2)
・プレゼン留意事項(その3)
・プレゼン留意事項(その4)
・22年度のプレゼンの傾向(その1)
・22年度のプレゼンの傾向(その2)
・22年度のプレゼンの傾向(その3)
・22年度のプレゼンの傾向(その4)
・プレゼン会場での駆け引き
・プレゼンの有利・不利
・事業計画書の内容とあまり関係ない質問
・経費削減と指定管理料削減
・令和2年度のプレゼン
・現地説明会での新型コロナ対策
指定管理者の公募に当たっては、ほとんどの場合、現地説明会が開催されます。現地説明会への出席が指定管理者への応募の絶対条件になる場合と、そうでない場合と両方あるのですが、現地説明会への出席義務がない場合でも、できる限り現地説明会には出席したほうがよいと思います。ここでは、現地説明会について知っていいただきたいことを紹介します。
■現地説明会は自治体が本気度を探る機会
自治体は、現地説明会で、指定管理者に本気で応募する事業者がどれくらいいるかを探っています。言い換えると、現地説明会に出席しない事業者については、どうしてもあまり本気でないという先入観で見られてしまいます。本気で応募する気があるなら、出席者は担当者でよいので、ぜひ現地説明会には出席してください。
■別途資料が配布される可能性があります。
最近はホームページから募集要項や応募様式がダウンロードできるようになりましたが、現地説明会当日にホームページからではダウンロードできない資料(図面や過去の利用実績など)が配布されることも珍しくありません。
■ライバルを知る機会
現地説明会はライバルを知る機会です。ぜひ、名刺交換してどのような企業が関心を持っているか情報収集してください。現在の指定管理者の場合は、自治体の現地説明会開催に積極的に協力してください。特に、受付を手伝うことができれば、参加者名簿を確認できます。
■必ず応募する事業者ばかりでありません。
現地説明会に出席したからと言って、必ず応募しなければならないわけではありませせん。指定管理者制度はまだまだ始まったばかりで、とりあえず勉強してみようという感覚で、現地説明会に参加する事業者もたくさんいまし、場合によっては、応募を減らすために、現在の指定管理者が下請企業の社員を大量動員している可能性もあります。したがって、出席者がたくさんいるから激戦になるとは限りません。
■少しだけ気にしなければならないことがあります。
勉強感覚で出席する場合は、現在の指定管理者をよく調査してから申し込んでください。たまにあるのが、現在の指定管理者とみなさんが何らかの取引を行っている場合、現地説明会に出席しただけで、取引停止になることがあります。現在の指定管理者は、現地説明会にどのような事業者が来るかそれくらいピリピリして注目しているのです。
もし、勉強で現地説明会に出席する場合で、現指定管理者と何らかの取引がある場合は、事前に現地説明会に出席する趣旨をよく説明した上で、出席してください。
→[現地説明会 プレゼン対策]に戻る
指定管理者の公募に際しては、質問期間が設けられます。わからないことはどんどん質問することが基本なのですが、とは言え、指定管理者制度独特のルールがあるために、知っておくべきことがあります。
質 問
指定管理料の積算で光熱水費は17〜19年度平均の95%ということで、3,006千円となっていますが、最近の原油の値上がり分を考慮すると、1年あたり5,816千円は必要です。このような歴史的な原油の値上がりは指定管理料に反映してもらえないのでしょうか。
回 答
募集要項のリスク負担の表にあるように、物価上昇リスクは指定管理者が負うこととなっています。
質 問
○○館は平成8年以降、中の展示物の入れ替えが全くなく、展示内容が陳腐化しており、細かい故障も頻繁に発生しています。現段階で県の予算で展示物の更新(買換え)を行う計画はないのでしょうか。
回 答
現段階で、県予算で展示物の更新を行う計画はありません。
質 問
クラブ、ボール等のレンタルが市民に好評だとお伺いしています。これらの所有者は○○市との解釈でよいのでしょうか。
回 答
クラブ、ホールなどのレンタル用品は現在の指定管理者が購入し自主事業としてレンタルしているものです。市では指定管理料にクラブ等の購入は見込んでおりませんが、市民サービスの継続という観点からも指定管理者が自主事業としてレンタル事業を継続していただくことが望ましいと考えております。
少し古いですが、平成20年度に公募があった施設の質問回答から目についたものをピックアップしました。なぜ、この3つをピックアップしたかわかりますか。この質問回答は、実は現在の指定管理者からの質問です(ただし、最後の質問は現指定管理者の関連会社からの質問)。現在の指定管理者がなぜこのようなわかりきった質問をするのでしょうか。
指定管理者の公募においては、「質問はホームページ等によりすべての人々に回答する。」というルールがあります。一部の指定管理者はこれをうまく活用する、すなわち、当該施設の指定管理者になれば多くのコストが必要だったり、難しい管理運営を迫られるということを過大にアピールして、競合相手を減らそうと考えているのです(実際、上記3例は現在の指定管理者以外応募がありませんでした。)
冷静に考えると、最初の質問は、3,006千円や5,816千円に言及しなくても質問することは可能ですし(5,816千円も本当かどうかあやしいものです。)、真ん中の質問の「細かい故障が頻発しています。」は質問の趣旨と全く関係がありません。また、最後の質問も「クラブ、ボール等のレンタルが市民に好評だとお伺いしています。」の一文もなくてもなんら問題ありません。これをあえて意識的に文書に入れて、競合相手を減らそうとしているのです。
決して紳士的な方法ではないと思いますが、勝負なのですから、決められたルールの範囲内で駆け引きを行うことは、むしろ、見習わなければならないことだと思います。
あまりに露骨なやり方でなければ、自治体職員も知らないふりをしてくれますので、少しは考えてみてください。ただし、本筋はあくまで、他社に負けない内容の事業計画書を作成することです。競合相手を減らす質問に必要以上に時間をかけることは本末転倒ということは忘れないでください。
→[現地説明会 プレゼン対策]に戻る
今度は、平成20年度に実施された公募の中から、今回はまずい質問の例をピックアップしてみました。
質 問
仕様書に受電設備の項目がありませんが、管理対象外と考えてもよいでしょうか。
回 答
施設内のすべての設備が管理対象となるため、受電設備も含まれます。
質 問
仕様書に特殊建築物定期点検の記載がありませんが、指定管理業務対象外と考えてよ
ろしいでしょうか。
回 答
指定管理業務に含まれています。3年に1回実施する必要があります。
質 問
総合案内業務は2階で実施することとなっていますが、利用者の利便性を考えれば1階で行うことが望ましいと考えられます。受付ブースを1階に設置して、1階で行うことは可能ですか。また、1階に受付ブースを設置し、指定管理期間が終了した場合は原状回復が必要ですか。
回 答
指定管理者の費用負担で受付ブースを設置することは不可能ではありませんが、設置する際には、○○課との協議が必要となります。また、受付ブースが○○センターの運営に支障がなければ、原状回復を求めない場合もあります。
何がまずいか、みなさんはピンときたと思います。最初の2つの質問はともに維持管理の問題です。土木部(県土整備部)や農林水産部は技術系職員がいてあまりこのようなことはないのですが、文化、福祉、商工労働などの部局は技術面から施設管理をチェックする職員がいないことが多いため、しばしば、例のように、本来仕様書に掲載すべき法定点検や維持管理業務の掲載漏れが起こります。指定管理者制度においては、点検業務や維持管理業務の一部を自治体が担当することほとんどなく、法律で定められている点検やメンテナンスが仕様書に記載されていなければ、まず、記載漏れと考えてよいでしょう。
このような仕様書の掲載漏れだと考えられる案件を見つけたら、質問で間違いを指摘するのではなく、事業計画書で「我々はたとえ仕様書に記載されなくても法令に定められている業務は当然に実施します。」というように記載しましょう。高い維持管理ノウハウがあることをアピールする絶好のチャンスを逃す手はありません。
また、最後の質問ですが、自らの手の内を暴露してしまっています。利用者の利便性が向上する工事を指定管理者の費用負担で行うことを自治体が拒否することは、技術上の無理がなければほとんどありませんし、ましてや利用者の利便性を向上させているものを敢えて指定管理期間終了後に原状回復させて不便にするなど考えられません。
したがって、3番目の質問のような件については、質問するのではなく、いきなり事業計画書に記載して問題ありません。施設の耐久性や騒音の問題等で工事が認められない可能性もゼロではありませんが、仮に工事が認められなくても、指定管理者の選定にマイナス点になることはありませんし、むしろ、(技術的に不可能だが)積極的な提案したという事実を好意的に受け取ってくれる審査委員もいるくらいだと思います。
なお、余談ですが、受付などの位置を移動することを提案する場合は、受付までの動線を表示する点字ブロックの移動が必ず必要になりますので、この工事費を積算することも忘れないでください。
→[現地説明会 プレゼン対策]に戻る
指定管理者の事業計画書作成のご相談を受ける際に、よく、「事業計画書のデザインを整えてほしい」とか、「プレゼンテーション用の資料をきれいに作成してほしい。」とかのご依頼をいただきます。これは、もちろん大切なことなのですが、少し冷静に優先順位を考えたほうがよい場合が結構あります。
普通に考えれば、事業計画書で一番大切なのは、「どのような管理運営を行うか」、すなわち内容です。事業計画書に十分な内容を盛り込んで、その後に「デザイン」や「プレゼン」があるということを、まず理解すべきです。
私は、よく、デザインやプレゼンを、野球のリリーフエースに例えます。阪神の藤川投手や日本ハムの武田投手は、チームになくてはならない戦力ですが、活躍できるのは、接戦の場面だけです。最初から5点も6点も負けていては、出番がありません。デザインやプレゼンもこれと全く同じで、これらが勝敗の分かれ目になるのは、接戦になった場合だけなのです。
仕事で、指定管理の事業計画書の検討委員会に参加させていただくことが、よくあるのですが、内容そっちのけで、事業計画書のデザインや文章表現を議論しているという場面をよく見かけます。
このような、本末転倒の議論で時間をつぶし、結局、内容についての議論がほとんどないまま事業計画書を作成している企業・団体は決して少なくありません。このような、無駄をなくすることが、公募に勝利するための第一段階だと思います。
→[現地説明会 プレゼン対策]に戻る
指定管理者として選定されるために必ず通らなければならないのが審査委員の前で行うプレゼンテーション(プレゼン)です。通常、プレゼンは事業計画書の提出期限から間もない時期(おおむね2週間から3週間あと)に実施されます。やっとの思いで事業計画書を作成した後にすぐに行われるので、ろくに準備もしないでプレゼンに臨む方もたくさんいらっしゃるのですが、特に接戦の場合は、大切な勝負どころになるので、ぜひ万全の準備をして臨むことをお薦めします。
■プレゼンのルールを確認してください。
プレゼンにはルールがあります。まず、かならずこのルールは確認してください。
1.プレゼン日時・場所
役所で開催されるとは限りません。ホテル等で開催される場合もあります。
2.プレゼンの持ち時間(説明○○分、質疑○○分)
3.出席可能な人数
4.追加資料を配布することが可能かどうか
追加資料は、事前に提出する必要があるか、当日配布することが可能か。
追加資料を当日配布する場合は何部必要か。
5.プロジェクタやOHPが使用可能かどうか。
使用可能な場合、パソコンやスクリーン等の機材は誰が用意するのか。
プロジェクタやOHPの機材調整の準備は何時から可能なのか。
これらは、プレゼンの開催通知書に記載されていることが多いと思いますが、記載されていない場合は必ず自治体担当者に確認してください。
なお、服装ですが、普段、作業着で仕事をされている方は、スーツを着るとそれだけで緊張してしまうことがあります。審査会は作業着でもぜんぜんOKなので、無理にフォーマルすぎる格好をする必要はありません。また、現在は、ほとんどの自治体で夏はクールビズを実施しています。クールビズの時期ならノーネクタイでも全く問題ありません。
■原則として追加資料は不要
追加資料を配布できるかどうかを確認すべきと説明しましたが、率直に言うと、原則として、追加資料は必要ありません。提出した事業計画書は、事前に審査委員に配布されており、委員は最低でも一読はしています。
よく、審査会当日、事業計画書のダイジェスト版などを配布する申請者がいるのですが、委員から見ると「せっかく事業計画書を読んできたのに別の資料をまた読まなければならないか。」という気持ちになることが多いようです。ですから、できる限り、提出した事業計画書をもとに説明しましょう。言い換えると、プレゼンの説明時間(おおむね15分から20分)で効率よく説明できるような事業計画書を作成することが大切なのです。
■準備できるなら写真や模型を準備
視覚に訴えることができる資料、すなわち写真や模型(国会で質問者がよく使用しているようなパネルでもOKです。)は持ち込みが可能ならば準備しましょう。だいたい3名程度はプレゼンに参加できることが多いので、説明者以外の2名は、プレゼンの進行具合に合わせて、写真や模型を机の上に掲げてください。
たとえば、イベントで「親子工作教室」を実施するのであれば、「こんなものを親子共同で作成しようと考えています。」といって模型を見せれば、審査委員の印象に残ります。そのほかにも、「過去に○○のイベントを■■で実施したときの状況です。本当にたくさんの方々にお越しいただきました。」と言って大きく引き伸ばした人ごみの写真を見せるのも効果的です。
■写真や模型が持ち込めるかどうかの確認方法
写真や模型をプレゼンテーション会場に持ち込めるかどうかを確認する場合には、注意が必要です。指定管理者選定では、1社からあった質問は全社に回答するというルールがあります。このため、自治体担当者への質問は、下手に行うと、自らの手の内を明らかにするという非常にまずい結果になります。
例えば、「写真や模型を持ち込んで説明してもよいでしょうか。」と質問すると、自治体は、競合相手にも「写真や模型を持ち込んで説明していただいて結構です。」と回答しますので、「写真」や「模型」をプレゼンで使おうとしていることがばれてしまいます。「写真」や「模型」も事業計画書の内容を補足する「追加資料」には変わりがないのですから、ここは「追加資料を持ち込んで説明してよろしいでしょうか。」という漠然とした言葉を使用して質問すべきなのです 。
→[現地説明会 プレゼン対策]に戻る
プレゼン対策として、大手企業がプロのアナウンサーに説明させることがあります。
アナウンサーが説明すると、非常にわかりやすくなることは確かですが、だからといって、
アナウンサーを使うことが良いとは限りません。
アナウンサーは指定管理者制度の知識はなく、用意された原稿を読むだけです。したがって、質疑応答時は一切発言しませんので、審査するほうから見ると、雇われたアナウンサーが説明していることはすぐにわかってしまいます。プレゼンのような重要なことを外部人材に任す企業は、指定管理者に選定したくないと考える審査委員のほうが圧倒的に多いと思います。
プレゼンはぜひ自社社員で行うことをお薦めします。別に責任者が行わなくてもかまいません。責任者が最初に少しあいさつして「詳細は、担当者の○○からご説明させていただきます。」と言えば、あとは担当者が説明しても何の問題もありません。雇われたアナウンサーを「担当者です」と虚偽の説明をすることが、多少、下手な説明よりも、はるかに罪が重いことを理解してください。
→[現地説明会 プレゼン対策]に戻る
プレゼンは弁論大会ではありません。したがって、説明の上手・下手が審査に直接影響するわけではなく、多少説明が下手でも、審査委員に自らが作成した事業計画書の趣旨をある程度理解してもらえれば十分だと考えてください。
■ゆっくりしゃべってください。
緊張すると早口になりがちですが、必ずゆっくりしゃべってください。説明者本人が気をつけることはもちろんですが、説明者以外の出席者も、ゆっくり説明できているかどうかをチェックし、もし、早くりになりかけている場合は、背中をたたくなどの合図をあらかじめ定めておいて、説明者が早口にならないよう協力してください。
■全部、説明する必要はありません。
膨大な事業計画書を短い時間で全部は説明できません。ポイントを絞って説明してください。ポイントを絞った結果、全く説明できない部分が出てきますが、これは問題ありません。利便性の向上や利用者を増やす取り組み、地域住民との連携などを中心に説明してください。
■まず、ページを指定してから説明を行なってください。
ポイントを絞って説明するわけですから、必ず、「○○ページをご覧ください」といった上で、審査委員が当該ページを開いたのを確認して、説明を始めてください。
以上のことを実行すればよいのですが、ページを指定しつつ、ゆっくりとしゃべって説明すると、たいていは時間が不足します。必ず何回か練習して、制限時間内に終了できるようにしてください。時間が不足する場合は、しゃべり方を早めるのではなく、説明内容を減らして、時間を短縮してください。
プレゼンに自信のない方はあらかじめ全文原稿を用意し、それを読む形でもかまいません。プレゼンは事業計画書の趣旨を審査委員に説明する場であって、面接試験ではないので、原稿を読みながら説明したからといってマイナス点にはなりません。
なお、私が知っている限り、新宿区や横須賀市、佐賀県などはプレゼンを一般公開しています。指定管理者選定の透明度を高めるため、プレゼンを公開する自治体は今後も少しずつ増えてくると考えられます。近くでプレゼンが公開されていれば、一度、見学に行くことをお薦めします。
→[現地説明会 プレゼン対策]に戻る
事業計画書の説明が終わると、次は審査委員からの質問の時間になります。質問に対する回答にも留意事項が何点かあります。
■簡潔に回答してください。
質問は審査委員が事業計画書の内容を理解するための時間です。したがって、聞かれた内容以外のことを答えて時間を浪費することは審査委員の印象を悪くします。
■質問をある程度は想定してください。
できれば、審査委員の立場に立って、どのような質問をするか想定してください。
基本的には、公認会計士なら収支関係、利用者代表なら施設の利用(特に多くの利用者が不便だと考えていること)というようにそれぞれの委員の得意分野から出ますので、審査委員の肩書を見ながら想定するとよいと思います。
また、みなさんが案外回答できないのが大きな質問(今回の指定管理に応募した動機、施設の将来ビジョンなど)です。指定管理者に応募した動機が「儲けるため」というのではちょっと寂しすぎます。「○○の管理運営を通じて●●の分野で地域に貢献したい。」と回答できるようにしておいてください。
■想定外の質問が出てもあわてずに
どんなに準備しても、想定外の質問を100%防ぐことはできません。すぐに答えが出ない場合は「少し時間をください」といってタイムをかけることが可能です。特に数字関係で答えに確証がない場合は、タイムをかけて、出席者全員で確認してください。
また、場合によっては、出席者のひとりが会場の外へ出て、携帯電話で社員に確認することもできますので、特に事業計画書を分担して作成している場合などは、出席できない作成者は、社内でいつでも連絡が取れるよう待機しておくと出席される方も安心できると思います。
なお、持っている知識で、全く回答でいないことに無理に回答する必要はありません。「申し訳ありませんが、○○については知識がありません。」と素直に答える方が、傷が浅いことが多いと思います。
→[現地説明会 プレゼン対策]に戻る
プレゼンの方法は、もちろん、自治体によって異なるのですが、全体的な傾向として、今年だけでなく、ここ数年、プレゼンの説明時間が短くなる傾向にあり、平成17年ごろは、概ね、説明、質疑とも 15分〜20分というのが多かったのですが、最近は、「説明10分、質疑15分」というのが主流となっています。また、説明は全くなしで、「質疑」のみという自治体も増えており、プレゼンを「説明」と「質疑」に分けると、「説明」の時間がより短くなる傾向にあります。
「説明」の時間が短くなるわけですから、当然、ポイントを絞る必要があり、説明できない部分があってもやむを得ません。説明する部分は、一般的に言うと、「サービスの向上」、「利用促進」、「住民との協働」、「地域貢献」などで、「管理運営体制」、「維持管理」などは割愛する部分です。ただし、静岡県のように、施設で重大事故が発生している自治体では、「安全確保」には絶対に触れる必要がありますし、例えば、環境部局の施設では、「環境配慮」にも触れるべきと言うように、施設や審査基準によって、説明すべき部分と割愛する部分は変わってきます。
また、プレゼンにパワーポイントを使用する場合がありますが、説明時間が10分以下の場合、私は、基本的には、使用しないようにアドバイスしています。これは、持ち時間10分で、冒頭の「あいさつ」から、「パソコンの操作」、「事業計画書の説明」をすべて手際よく実施することは、よほどプレゼンになれている方でなければ難しいからで、パワーポイントの資料を作成するくらいなら、10分間のスピーチの全文原稿をつくり、それを読む方がはるかにリスクが少ないやり方だと思います。(プレゼンは弁論大会ではないので、原稿を棒読みしても、それが減点材料になるわけではありません。)
→[現地説明会 プレゼン対策に戻る]
プレゼンの説明時間が短くなる傾向にあるのは、以前に比べて、民間の審査委員の割合が増えていることと密接な関係があります。つまり、業務多忙な多人数の民間審査員のスケジュールを調整して審査会を開催することが容易ではなく、「多数の応募があるけれども、1日だけしか審査会が開催できない」とか「民間審査委員の拘束時間をできる限り短くしなければならない」というような事情が発生しがちだからです。
実は、審査委員の採点の方法も、以前とは変わりつつあります。以前は、応募者のプレゼンを聞いて、その後、質問をしてから、各審査項目の点数を付けることが多かったのですが、特に、プレゼンの説明時間が10分以下の場合は、あらかじめ各審査委員が各審査項目の採点を済ませており、説明や質疑の印象で、採点結果の一部を修正するということが多くなっています。
これは、審査委員の質問事項に影響を与えています。以前は、「なぜ指定管理者に応募したのか」とか、「○○の運営を通して、一番何がしたいのか」などの大きな理念を確認する質問が多かったのですが、最近は、いったんは採点が終わっているので、採点する際に審査委員がわかりにくかったこと、すなわち、以前に比べれば、細かい質問がたくさん出るようになりました。
質問があるということは、各審査委員自らが行った採点が適切かどうか確認しているわけですから、的確な回答ができればあらかじめ終了している採点が上方修正される可能性が高いということですし、逆に、的外れな回答を行えば採点が下方修正される場合もあるわけで、「質疑」の重要性は、以前よりもはるかに高まっています。
一方、「説明」部分は、事前に採点が行われ、「説明」を聞いて採点するわけではないので、以前よりは、重要性が下がっているというとになり、これを踏まえると、今までよりは、質疑対策に重点を置いた方がよいという結論になります。
→[現地説明会 プレゼン対策]に戻る
「質疑」対策についても、よくご質問をいただきます。簡単に言うと、「何を聞かれるのか」ということなのですが、前回ご説明したように、大きな質問が減少し、細かい質問が増える傾向にありますので、質問の予測が以前より難しくなっているというのが私の実感です。
ただ、それでも、「これだけは回答できるように準備しておくべき」という質問はあります。最近は、質問の内容が現指定管理者と参入側でかなり異なる傾向にあるので、今回は、現指定管理者の場合をご紹介します。
現指定管理者の場合
今回の公募が指定管理者の更新に当たる場合は、前回の事業計画書に記載した事項がどの程度達成できているか聞かれることが非常に多くなっているので、これをきちんと整理しておく必要があります。
「適正な清掃を行う。」とか、「高品質な維持管理を行う。」のような抽象的な記載は、あまり気にしなくていいですが、「利用者数目標」や「具体的なイベント名」などについては、もし、達成していなかったり、実施していない場合は、その理由がきちんと回答できなければなりません。例えば、21年度の利用者数が減少している場合、「新型インフルエンザ」や「リーマンショック」等の影響を理由にすることが考えられるのですが、仮に22年度前半の利用者数も減少しているとすれば、利用者数の減少の理由を「新型インフルエンザ」や「リーマンショック」にするのは無理があります。
また、よく、利用者減少の理由として「週末の天気が悪かった」という説明をされる団体の方がいらっしゃるのですが、これはあまり説得力がありません。本当に天候が原因なら、「21年度は土曜日・日曜日104日のうち●●日で雨が降りました。これは20年度の●●日に比べ、●日も増えており、これが利用者数が伸び悩んだ主な原因です。」というような言い方をすべきです。
もうひとつ、「前回の事業計画書と何が違うのか」というに対する準備も必要です。この質問は、「今回の事業計画書で何をしたいのか。」とか、「今回の事業計画書のセールスポイントは。」とかのような形で聞かれることもあります。事業計画書には、おそらく、新たな取組みを記載していると思うので、基本的には、それを説明するとよいのですが、回答に対して、「では、なぜ今までやらなかったのか。」という再質問への対応も考えておく必要があります。一般的に言うと、アンケートなどの利用者ニーズの調査を理由にするのが一番無難で、「去年、今年に実施した利用者アンケートで多くの要望があったので、何とか実現するということで検討を重ね、今回の事業計画書で提案させていただきました。」と回答すれば、それ以上掘り下げられることはほとんどないはずです。
もちろん、細かい質問はたくさん考えられますが、現指定管理者なので、ある程度の細か質問にも対応できるはずです。そういう意味では、現指定管理者は、大きな質問だけ押さえておけばプレゼンは何とかなるということは言えます。
→[現地説明会プレゼン対策]に戻る
今回は、参入側の「質疑」対策です。率直に言って、今まで指定管理業務の経験がない方が審査委員の「質疑」に対し、常に的確に回答するということは非常に難しいので、名答弁をしようなどとは考えずに、自分の意図するところをできる限り審査委員に伝えることができればOKと考えてください。
参入側に対する審査委員の質問の意図は、「事業計画書の表現や趣旨がわかりにくい箇所の確認」か「よいことは書いてあるけれども本当にできるのか。」のいずれかの場合がほとんどです。表現は前者の場合は、事業計画書の記載内容を補足すればよいだけです。
後者ですが、例えば、「ボランティアはどのように集めるのか」のように方法論を質問したり、「餅つき大会を行うには保健所の許可が必要なのでは」というように、法的規制をあげて検討状況を質問するというように、さまざまな形に変わることがありますが、突き詰めて考えるといずれも「本当にできるのか」ということを聞いています。
これに対し、「ボランティアは集められます。」とか、「保健所の許可は取れます。」という回答では、説得力がありません。もちろん、いろいろな回答方法があるのですが、比較的どんな場面でも応用が利く回答方法は、「当社は(施設名)周辺でさまざまな企業活動を展開しており、周辺住民のみなさんとは深い信頼関係があります。このケットワークを活用させていただくことにより、ボランティアを確保することは十分可能だと考えています。」というように、「さまざまな関係者と信頼関係があってこのネットワークを活用する」という回答方法と、「当社は、(会社の事業名)で保健所の許可をいただくことがあり、今回の事案についても、当社の経験に基づけば、許可がいただける案件だと考えています。」というように、「会社のこれまでの経験やノウハウから判断すれば十分可能です。」という回答方法です。
また、会社の経験・ノウハウから説明することが明らかに無理な場合、例えば、造園会社が公園の指定管理に応募していて、公園内にあるテニスコートの運営について質問された場合などには、「当社には、テニスを趣味としている社員が複数おり、この社員のネットワークを活用して、テニス教室の講師を確保します。」のように、会社ではなく、社員個人のネットワークを前面に出して回答するという方法もあります。
なお、「●●(イベント名)のリーフレット印刷代はどこに含まれているのか」のように、経費関係の細かい質問については、いちいち「●●に入っています。」のような回答をすると、矛盾が出やすい(回答の合計額が記載している金額より大きくなる等)ので、「必要と考えられる経費はすべて見積もったつもりです。万一、想定外の経費が発生しても当社の責任で費用負担し、県民(市民)のみなさんにはご迷惑をおかけしません。」と回答する方がよいと思います。
現地説明会は、公募される施設で行われますが、事業計画書を提出した後のプレゼンテーションは県庁や市役所など、自治体の庁舎で行われることが多いと思います。これには理由があって、現在の指定管理者を有利にしないためです。
つまり、現在の指定管理者は、プレゼン当日に、多く利用者(来館者)が見込めるイベントを開催したり、場合によっては、「サクラ」の利用者(入館者)を多数動員して、施設の「にぎわい」を意図的に創出できます。利用者代表以外の指定管理者審査委員は、あまり施設には来ていないことが多いので、「こんなに活性化している施設の指定管理者を交代させることはできない。」と思わることが可能になります。このようなことが行われないようにするため、あえて現場とは違う場所でプレゼンを開催しているのです。
ところが、21年度は、公募する施設でプレゼンテーションが開催された事例が結構ありました。これは、おそらく、指定管理者制度が導入されてから数年が経過し、自治体の担当者が交代した際に、そこまで引き継がれていないというのが原因だと思います。(現在の指定管理者を守ろうとして、意図的に行っているケースも、もちろん考えられます。)
実は、21年度、私が参入側のお手伝いさせていただいた案件の中にも、現地でプレゼンが行われるというケースがありました。その施設は、平日はほとんど入館者がいない施設なのですが、予想どおり、ホームページで調べてみると、いつも、週末にしか実施していないイベントが、なぜかプレゼンのある週だけ、木、金、土の3日間(プレゼンは金曜日)に開催されることになっています。これは、明らかに作為があり、プレゼン当日は、現在の指定管理者が動員した「サクラ」で「にぎわい」が創出されることが確実です。そして、それを見た審査委員は現在の指定管理者の管理運営に好感触をもつことでしょう。
そこで、私は、対抗手段を用意しました。こちらも、親子の「サクラ」を動員し、審査が行われる会議室の廊下の前で、現在の指定管理者のプレゼンの時間を見計らい、まず、子どもに「今日は、人がいっぱいいるね。」と大声で言わせ、母親に「そうね、いつもはがらがらなのにね。」と大声で答えさせました。これが功を奏したかどうかはわからないのですが、結果的には、私がお手伝いした企業が指定管理者に選定されました。
あまりほめられた方法ではないのですが、公募施設でプレゼンが行われる場合、参入側がトライする価値は十分あります。また、逆に言うと、現在の指定管理者は、会議室の前の廊下を、「審査中」という理由で、一般者通行禁止にすれば、このような作戦に対抗できます。指定管理選定の本質とは全然関係ない話ですが、このような駆け引きも勝負のうちだと私は思います。
→[現地説明会 プレゼン対策]に戻る
プレゼンの有利・不利
背負っているプレッシャーに大差がある指定管理のプレゼンを、同じ基準で評価するのは、私は、酷だと思っています。少なくとも、説明の上手・下手で、評価に差をつけるのは厳しすぎるでしょう。「加点・減点の対象は、説明の内容(中身)であって、説明者の「話し方」の技量ではない」 という運用を行うのが公平な審査ではないか思います。
ただ、現実問題として、上記のような運用を行っている自治体はあまりありませんし、そもそも、このようなプレゼンの有利・不利を意識していない自治体担当者も多いでしょう。ですから、現指定管理者の方は、プレゼンには上記のような有利・不利があることを、機会を見つけて、自治体担当者に伝えるべきです。特に、今年度に公募がある指定管理者の方は、公募が始まってしまうと、言いにくい状況になりますので、今年度の早い時期に話をしてみてはどうでしょうか。(2017.4.3)
→[現地説明会・プレゼン対策]に戻る
事業計画書内容とあまり関係のない質問
毎年同じことを書くのですが、6から10月まで本当に多忙で、ホームページの更新まで手が回りませんでした(申し訳ありません)。今年は、初めて、石川県、沖縄県で仕事をいただき、これで、秋田県、山形県、栃木県、茨城県、福井県、鹿児島県を除く41都道府県に受注実績が広がりました。いつか、「全都道府県で業務実績があります。」と言えるようになりたいと思っています。これらの県の方々からのオファーをお待ちしています。
まだ、プレゼンが終わっていない自治体もあるようなので、プレゼンについて、記載させていただきます。指定管理者公募のプレゼンでは、審査委員からの質疑があります。先月(10月)に、ある企業から問い合わせをいただきました。審査委員からの質疑にうまく答えられなかったので、今後のために「どのように返答するべきだったのか」を教えてほしいという内容でした。私は、以下のような回答がよいのではとお答えしました。(下線部が質問)
収支予算書には、利益が入っていないが、企業なのに利益はないのか。
収支予算書は「指定管理料の見積書」と理解しています。日本の商習慣では、見積書に「利益」という項目はありませんので、収支予算書には利益は入れませんでした。ただ、事業計画書に記載した事項をすべて実施することを前提に、経費を削減し、あるいは利用料金収入を増やして、利益を出すよう努めたいと考えています。
メンテナンス企業同士が事業共同体を組むのはなぜか。
公共事業では、多くの場合、JVという形で、建設業同士が共同事業体を組んでいます。これは、同じ建設業でも、得意分野が異なるからです。私どもも同様で、設備管理を得意とする○○社と清掃を得意とする○○社が組むことで、よりよいサービスを提供できると考えました。
民間企業の方には、回答が難しい質問かもしれませんが、「的確な回答を行う自信がない」などと悩む必要はありません。このような事業計画書の内容とあまり関係ない質問は、ほとんどの場合、審査委員の単なる個人的興味に過ぎないからです。
したがって、回答の内容が少しぐらい 「嘘っぽくても」 評価が下がるケースことはほとんどありません。例えば、上記の1番目の質問で 「社会貢献の一環と考えているので、利益は考えていません」、2番目の質問で 「両社で業務を行うことで、利益の共有やリスクの軽減を図ることができると考えました」 のように答えても大丈夫です。評価を下げるのは、結論を言わなかったり、投げやり (「単に名義を借りただけ」などと開き直る) な場合だけだと考えてください。(2017.11.8)
→[現地説明会プレゼン対策]に戻る
毎年、同じことを書くのですが、今年度も多くの仕事をいただき、特に、6月以降は多忙で、多くの仕事依頼をお断りせざるをえず、ましてや、サイトの更新にまでは、手が回りませんでした。やっと落ち着いてきたので、サイトの更新を行います。時間のある時に読んでいただければ幸いです。
今年度のプレゼンで、「指定管理者制度導入の趣旨を踏まえ、もう少し指定管理料を削減できないのか。」 という趣旨の質問が結構出たようです。人件費高騰などにより、ほとんどの施設は指定管理料削減が困難になっているはずですが、一方で、「指定管理者制度導入の目的には 「経費削減」 という項目があるわけですから、プレゼンのような公式の場で 「これ以上の経費削減はできません。」 という回答をしにくいのも事実でしょう。
私は、以下のように回答するのがよいと思っています。「日本政府も毎年、予算編成時などに『経費削減』 を掲げていますが、経費削減が行われる中で、税金や社会保険料などの国民負担はむしろ上昇しています。指定管理業務も同様で、私どもも経費削減を限界まで行っていますが、一方で、人件費や燃料費の高騰などの要因があり、これ以上の指定管理料の削減には至らないことをご理解いただければと思います。」
つまり、「経費削減」 と 「指定管理料削減」 を分けて考え、指定管理者制度導入の目的である経費削減の努力は行っているけれども、人件費高騰などの要因があるため、経費削減がこれ以上の指定管理料削減にはつながらない」 という理屈で回答することが大切です。単に、「経費削減はできません」 では、指定管理者制度の導入目的を否定していると解釈されるリスクがあり、よい回答ではないと思います。
なお、回答例の「日本政府」を「○○県、○○市などの自治体名」に代えるのは、直接的すぎるのでやめた方が無難でしょう。(2018.10.13)
毎年同じことを記載するのですが、夏期は多忙で更新ができませんでした。特に今年度は、緊急事態宣言が解除された6月から、業務の依頼が急に増えた関係で、例年より業務が落ち着くのが遅れ、11月に入って、やっとサイトの更新作業を再開できるようになりました。また、
1か月に1度くらいは、新たなコンテンツを掲載しますので、時間があるときにご一読いただければ幸いです。
今年は、指定管理公募でも、新型コロナが高い関心を集めました。当社がお手伝いさせていただいた案件で、10月末現在、21案件の指定管理応募のプレゼンが終了しているのですが、このうち、17案件で新型コロナ関係の質問があり、特に、9案件では、新型コロナ関係の質問が一番多かったようです。
質問の趣旨は、大きくは3パターンに分かれます。1点目は、感染防止対策で、さらに、職員の感染防止対策と利用者感染防止対策に細分化できます(両方について質問が出た例もありました)。
2点目は、感染防止対策とも一部重複するのですが、「コロナ禍の中で、利用者数や稼働率をどのように確保するのか」 という趣旨の質問で、また、3点目は、「コロナ禍の中で法人の本業の経営は悪化していないか」 という趣旨の質問です。
「職員に感染者が出た場合の対応」、「体温が37.5度以上ある方の利用を拒む法的根拠」
など、上記3パターンとは少し異なる趣旨の質問が出ることもあり、自治体職員の審査委員はもとより、外部の審査委員も、新型コロナに対する強い関心があることがうかがわれます。
まだ、プレゼンが終わっていない応募法人の方もいらっしゃると思いますが、ぜひ、新型コロナ関連の質問に対する回答を準備しておくべきだと思います。また、私の予測に過ぎませんが、令和3年度の公募でも、新型コロナ対策は、審査委員の一定の関心を集める可能性が高いように思います。来年度の公募の準備に入っている指定管理者の方は、事業計画書の記載内容において、現在実施している以上に新型コロナ対策を検討すべきだと思います。(2020.11. 1)
→[現地説明会・プレゼン対策]に戻る
今年、当社がお手伝いさせていただいた中に、同じ自治体内に3つの同種施設があり、そのうちの1施設の指定管理者である法人から 「3施設すべてで指定管理者に選定されたい」 との依頼がありました。
あくまで一般論ですが、自治体内に複数の同種施設があり、別々に公募されている場合、すべての施設の指定管理者に選定されるのは、難しいことが多いと考えるべきです。自治体がすべての施設の指定管理者が同じ法人でもよいと考えているのなら、一括してひとつの単位で公募する方が、「規模拡大で指定管理料削減が期待できる」、「事務処理の手間が少なくてすむ」 などのメリットがあるからです。
ただ、依頼をいただいた法人は、少なくとも、他の2施設よりは、優れた管理運営を行っており、3施設すべては難しくても、2施設なら十分可能性があると考えられたので、お手伝いさせていただきました。
そして、新型コロナ第2波の真っ只中である8月下旬に、公募の現地説明会が開催される
こととなりました。現地説明会は、公募を行う自治体が主催者であり、指定管理者は、通常、場所提供および立ち会い以外の業務はありません。
ただ、私は、現地説明会での積極的な新型コロナ感染防止対策、具体的には、「受付・
演壇へのアクリル板の設置」、「受付での消毒液・非接触型体温計の準備」、「狭くて、密閉
・密接が避けられない機械室等の映像の準備」等を自治体に提案・協力することを申し出る
(= これらを指定管理者が実施することを提案する) よう、指定管理者の方にアドバイスしま
した。(当日にはこれら提案が自治体に受け入れられ、指定管理者が準備を行いました)
私が、このような提案をアドバイスしたのは、自治体の評価を高め、公募を有利にするためで、結果的には、私がお手伝いした法人が3施設すべてで指定管理者に選定されました。
もちろん、優れた管理運営の実績や事業計画書作成が選定の大きな要因ですが、審査基準「安全管理」(感染症対策も含まれます) の点数が他の応募者よりもかなり高かったので、
現地説明会でのコロナ感染症防止対策の提案も、結構、評価されたのではないかと思っています。
自治体は、現在、新型コロナ対策関係で多忙になっている部署が多く、数年に1度しかな
い指定管理者の公募業務が加わってしまうと、さらに余裕がなくなり、現地説明会のような
ノウハウがあまりない(数年に一度しか実施しない)業務では、細部にまで神経が行き届か
なくなることが少なくありません。
このような際に、(嫌みにならない範囲)で提案や協力を行うと評価が高まり、公募でも有利に働きます。来年は、新型コロナとは無縁の年になってほしいと切に願っていますが、万一、夏になっても続いており、現地説明会開催時に自治体から特に指示等がなければ、感染防止対策の提案・協力を申し出てみるのも公募対策としてあり得るのではないかと思っています(2020.12.18)
→[現地説明会・プレゼン対策]に戻る