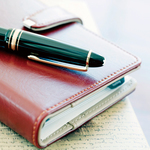このコーナーでは、指定管理者に応募する際に必ず作成する必要がある事業計画書に記載すべき内容のポイントをご紹介します。自治体や施設にもよるので、100%とは言えませんが、記載漏れのがないかどうかの判断の目安として、事業計画書で以下の項目の記載があるかどうかは確認すべきです。
自治体が示す様式によっては、記載できる箇所がないという項目があると思いますが、そのような場合でも、できる限り触れるべきです。例えば、下記項目2〜4は項目1の「管理運営の基本方針」に含めて記載できるるはずです。
また、下記項目では、障害者配慮を「公平・平等な管理運営」の中に含めていますが、多くの障害者利用が想定される施設では独立した項目にすべきであるように、施設の種別によって、重点項目は異なります。
1.管理運営の基本方針
2.施設の設置目的を果たす管理運営
3.指定管理者制度導入の目的を達成する管理運営
4.自社の「強み」・「弱み」
5.安全・安心の確保
6.快適な施設環境の提供
7.公平・平等な管理運営
8.高品質な維持管理・適切な修繕
9.利用者の声の収集・苦情対応
10.サービスの向上
11.自主事業
12.イベント等の開催
13.コスト削減
14.職員のスキル・研修
15.地域連携
16.個人情報保護
17.環境への配慮
18.収支計画書(その1) 収支計画書(その2)
【そのほかの内容】
・事業計画書作成の準備
・自治体の指定管理者選定作業手順
・事業計画書の分量
・利用料金の設定
・事業計画書に記載する内容の重複
・審査員は事業計画書を読んでいる?
・情報公開制度の活用(その1) ・情報公開制度の活用(その2)
・利用者が多すぎる施設(その1) ・利用者が多すぎる施設(その2)
・ワードとパワーポイント ・公契約条例
・指定管理公募時に吹く風 ・参入側の利用者アンケート
・議員への依頼 ・指定管理者公募における自治体からの応募要請
・25年度公募の施設の収支計画書
・サービス水準の低下を認める応募要件の緩和
・前回の募集要項・仕様書 ・事業計画書に使用する写真
・事業計画書に記載する男女共同参画 ・2期目に向けての努力
・少人数での緊急対応 ・「枚」 と 「ページ」
・防災に対する提案の検討 ・5年前のリベンジ
・体育施設での大手企業との競合
・収支計画書上の利益 ・オリンピックイヤーの公募日程
・「します」 と 「しています」 ・with コロナ下での公募
・公募に勝つための第1歩 ・事業計画書の作成スケジュール
・令和3年度の検討事項 ・事業計画書に記載する経営理念
・令和5年度公募における指定管理料 ・申請書の受理
・審査内容の確認 ・地域に密着したネットワーク
・事業計画書の作成体制 ・応募者名「黒塗り」の事業計画書
事業計画書の構成は、自治体が「様式」という形で示します。通常、自治体が様式を示すのは、公募開始時、つまり、締め切りまでもうあまり時間がないという段階です。したがって、公募開始前に「様式」を想定し、記載する内容についての検討を始めることが大切です。
「様式」を想定することはそんなに難しくはありません。事業計画書で記載しなければならないことは、大体決まっているからです。
■事業計画書に記載しなければならない内容
- 1管理運営の基本方針
- 2管理運営組織体制
- 3施設・設備の維持管理
- 4安全・安心の確保、危機管理体制
- 5利用者ニーズの把握、苦情処理
- 6利用者サービスの向上
- 7施設の利用促進
- 8自主事業
- 9コスト削減
- 10その他取り組み(個人情報保護・情報公開、地域貢献、環境配慮、障害者雇用等)
収支計画、申請者の実績、財務内容)
自治体、あるいは施設によって、重点が置かれている分野は異なりますが、これくらいを検討しておけば、十分でしょう。まれに、「応募の意欲」や「施設の将来ビジョン」などを問われることがありますが、それくらいは、公募が始まってからでも考えられると思います。
→[事業計画書作成のポイント]に戻る
管理運営の基本方針には、みなさんが、施設の運営を通して何を行いたいかということを記載する部分です。とはいえ、これでは、漠然としすぎているので、具体的には、表現はいろいろあるにしても、以下の内容からいくつかを選ぶというのが一般的です。
- 1施設の設置目的を果たす管理運営
- 2安全・安心の確保
- 3快適な施設環境の提供
- 4公平・平等な管理運営
- 5高品質な維持管理の実現
- 6利用者の声を反映した管理運営
- 7利用者視点に立ったサービスの向上
- 8コスト削減を可能にする管理運営
- 9住民との協働による管理運営
- 10地域に貢献する管理運営
環境に配慮した管理運営
この中から、おおむね5〜7つくらいの基本方針を掲げることが普通だと思います。一番目の施設の設置目的は、ひとつの場合もあれば、例えば、「交流人口の拡大と地域経済の活性化」のように複数あげられる場合もあるでしょう。また、「安全・安心な管理運営」と「快適な施設環境の提供」をいっしょにして「安全・安心・快適な管理運営」というような方針を掲げる場合もあります。
どれを選ぶかは、みなさんが作成する事業計画書の中身と自治体(担当部局)が重視している項目を総合的に判断して決定する必要があります。
施設の設置目的は、自治体が定める施設設置(管理)条例の第1条に記載されています。ただ、条例の記載内容は極めて抽象的な場合も多いので、自治体が策定している「総合計画」や「地域振興計画」なども確認し、自治体における当該施設の位置づけをしっかりと理解する必要があります。
また、施設のターゲットもできる限り正確に把握してください。例えば、同じ公園でも地域密着型の場合と観光施設的側面を持っている場合があります。地域密着型の場合は、自治体内向けの広報で十分ですが、観光施設的側面があるとすれば、県外(市外)に向けた広報活動も必要です。同様に文化施設でも、「地域住民の文化活動の発表の場を提供する。」ことと「県外(市外)の優れた文化・芸術を鑑賞する機会を住民に提供する。」のどちらがより大切なのか(=どちらが施設の設置目的なのか)を判断することが重要になります。
事業計画書を作成する場合に、中小企業診断士や税理士の方がよく最初に「自社の『強み』と『弱み』を分析しましょう。」というアドバイスを行うようですが、私は、まず、施設の設置目的を正確に把握し、それを職員全体で共有ことが一番だと思います。
普通の商売では、まず自社の経営資源があって、それを活かした商業活動を行いますが、指定管理者制度では、まず施設があって、施設の設置目的を最大限達成する管理運営を行わなければならないからです。
施設の設置目的が重要なことは言うまでもありませんが、もうひとつ、指定管理者制度導入の目的も忘れてはいけません。
指定管理者制度導入の目的は、「安全・安心の確保を前提としたサービスの向上と経費の削減」です。つまり、みなさんが作成する事業計画書には、「施設の設置目的の達成」のほかに、最低限の話として「安全・安心の確保」、「サービスの向上」、「経費の削減」についての記載が必要になります。
なかでも、「サービスの向上」は一番の重要部分なのですが、現在の指定管理者、特に外郭団体の事業計画書に「サービスの向上」の提案がほとんどないことが意外にあります。「サービスの向上」ですから、現在のサービス水準をそのまま提案することは「向上」ではありません。サービスを継続的に向上させることは非常に難しいことですが、それでも、これまで培った経験やノウハウを生かして、新たな「サービスの向上」を提案することが現在の指定管理者に求められているのです。
→[事業計画書作成のポイント]に戻る
まず、「施設の設置目的」と言いましたが、自社の「強み」と「弱み」を分析することが必要でないわけではありません。ただ、注意していただきたい点が2点あります。
ひとつは、施設の「強み・弱み」と自社の「強み・弱み」を混同しないことです。「客席数2,000席の県内最大のコンサートホールです。」と事業計画書に記載しても、それは施設の「強み」、言い換えると自治体の手柄であり、何のポイントにもなりません。「当社が管理運営を行った過去3年間で、県内最大のコンサートホールを年平均15回満員しています。」という記載は、自社のイベント開催(誘致)能力を説明しているのでポイントになります。「強み・弱み分析」を行う場合は、この違いを必ず理解してください。
もうひとつは、「弱み」の分析は、指定管理者選定に関しては、あまり意味がないということです。もちろん、至らないことを改善することは大切です。けれども、競争である以上、事業計画書に至らない点を進んで記載する必要はありませんし、「今まで至らなかった点を改善する。」という提案は、マイナスをゼロにするだけで、アピールポイントにはならないと考えてください。
ただし、利用者や住民の意見を積極的に収集して「至らない点を継続的に改善する仕組みを構築する」という提案は重要です。これは、「利用者の意見の把握」などの項目でしっかりとアピールしてください。
→[事業計画書作成のポイント]に戻る
「安全・安心の確保」は当たり前と考えている方もたくさんいらっしゃるでしょうが、指定管理者の審査においては、みなさんが考えているより大きな点差がこの分野でついています。
埼玉県内のプールで発生した小学生の死亡事故はまだ記憶にあると思いますが、あの事故で市役所の担当者2名が有罪判決を受け、失職したことは全国の自治体職員にとって衝撃的なことでした。
つまり、コスト削減に過度に重点を置いて指定管理者を選定することは、自らの失職につながる可能性があるということで、あの事故以来、指定管理者の選定に当たって、「安全・安心の確保」の重要性は飛躍的な高まっているのです。ある意味、しつこいくらい「安全・安心」に重点を置いた管理運営を行うことをアピールすることが必要だと思います。
ポイントはたくさんあるのですが、まず、大きく分けて、未然防止措置と万一の事故発生時の危機管理体制について記載する必要があります。
このうち、未然防止は、施設内の巡回、施設・設備の日常点検、利用者に注意を促す掲示板の設置などについて、実施回数や実施方法を数字や手法を具体的に記載する必要があります。また、危機管理については、緊急時の体制(危機管理本部の設置など)、担当者の配置(救護班、連絡調整班、マスコミ対応班など)、情報の一元化(すべての情報を誰に集約するか)などを具体的に記載するとともに、日常の訓練や研修等にも触れる必要があります。
「安全・安心」や「危機管理」はおそらく、誰が考えても講じる措置はあまり変わらないはずです。それでも、実態として大きな点差がついているのは、「これくらいは当たり前」と考えて、記載を省略しているケースがほとんどです。「安全・安心の確保」に関しては、多少、分量が大きくてもよいので、細かすぎるくらいに説明した方がよいと考えてください。
なお、「万一の際の事故発生時の対応」には、必ず、再発防止策の検討・実行も忘れずに記載してください。
→[事業計画書作成のポイント]に戻る
この項目では、「接遇」についての記載が求められることもありますが、ほとんどの場合は清掃についてです。
清掃は外部委託する場合が多いと思いますが、「外部委託します。」と記載するだけでは何のポイントにもなりません。最低限の話として、委託業者に「事前打ち合わせ」、「中間報告」、「完了届」等の提出を義務づけるとともに、担当者が適宜(できれば具体的な回数を明示した方がよい。)チェックを行うなどの適正な業者管理について触れる必要があります。
また、「外部委託」や「業者管理」はある意味当たり前の話で、「職員による朝の一斉清掃」や「ボランティアによる清掃活動」などの分野で工夫した取り組みを提案できれば、評価をアップすることに結びつきます。
なお、最近、ちょっとしたアイディアを思いつきました。お金をかけずにできるので、もしよろしければ試してみてください。
→[事業計画書作成のポイント]に戻る
公の施設は、公平・平等な管理運営が求められています。とはいえ、ほとんどの事業計画書では「受付の平等」や「利用許可の平等」など手続きの平等を記載しているにすぎません。
公の施設はあらゆる住民が利用できなければなりません。あらゆる住民には当然のことですが、高齢者、障害者、小さな子ども、外国人などが含まれます。これらの方々にも気軽に施設を利用いただけるよう、利用申請書、案内表示板、パンフレットなどを工夫するユニバーサルデザイン視点にもぜひ触れてください。
また、企業の場合は、「自社の系列企業・取引先を優遇しないこと」、「ライバル企業に不利な取り扱いをしないこと」も忘れずに記載してください。
→[事業計画書作成のポイント]に戻る
メンテナンスが本業の企業などで、よく、細かな維持管理手法を延々と説明している事業計画書を見ますが、もともと、維持管理はあまり点差がつかない分野であり、正直、細かな維持管理手法を説明することが、ポイントにはつながりません。むしろ、維持管理の大まかな考え方を簡潔に示すほうが重要です。
施設により、説明する内容は異なると思いますが、大きなポイントは次のとおりです。
■維持管理委員会の設置
維持管理や修繕は「安全・安心の確保」と直結しますが、一方で資金や工期が限られていますので、優先順位を設けて実施する必要もあります。このような、重要な判断を、特定の担当者の経験に頼るのではなく、組織としてきっちりと行うという体制を示すことがまず大切です。名前には特に決まったものはありませんが、通常は「維持管理委員会」、「修繕委員会」などの名前になっているようです。
■予防保全
予防保全とは、部品の交換等を壊れてからではなく、不具合発生前に実施することです。不具合発生前に実施するわけですから、当然、不具合の前兆を的確に把握する綿密な点検作業とセットで記載する必要があります。
■職員の資格・経験
年1回程度実施する保守点検は専門業者が行うことが多いと思いますが、日常の点検は職員が行なわなければなりません。この日常の点検について、専門資格や経験を持った職員が実施することは大きなアピール材料になります。
→[事業計画書作成のポイント]に戻る
利用者の声を収集する方法としては、アンケートやヒアリング調査などが考えられます。多くの事業計画書が「アンケートやヒアリング調査を実施します。」としか記載していませんが、これでは、具体性が全くありません。アンケートやヒアリング調査は最低限の話として、回数や収集サンプル数の目標を示す必要があります。
特に、アンケート調査は、施設内にアンケート回収箱を用意するだけでは、なかなか回答してもらえません。「アンケート回答者に粗品を進呈する、抽選で○○が当たる。」などのインセンティブを用意し、できる限りサンプル数を増やす努力を提案してください。
また、収集したアンケートは分析を行い、改善計画を作成・実行し、再びアンケート等でチェックして、さらなる改善計画を策定するというように、利用者の声の収集が継続的に管理運営の改善につながる仕組みを構築しなければなりません。一般的には、これをPDCAサイクル(Plan → Do → Check → Action)により説明することが多いようです。
また、苦情処理については、忘れがちなのが「未然防止策」です。特に、利用者に対する説明不足で発生する苦情については、「お客様説明マニュアル」、「事前打ち合わせマニュアル」などでかなり減らせるはずです。
苦情が発生した場合の対応は、一次対応(内容の正確な把握)と二次対応(再発防止)に分けて記載してください。本によっては一次対応を「利用者への謝罪」と説明している場合もありますが、指定管理者公募の場合は、「内容の正確な把握」と記載するべきです。公の施設には、民間施設よりもはるかに多くのクレイマーなどが訪れるので、毅然とした対応を行なわなければならない場合も多々あるからです。
→[事業計画書作成のポイント]に戻る
指定管理者制度が導入された当初は、「サービスの向上」と言えば、「休館日の削減」と「営業時間の延長」がメインの提案でした。ただ、これ以上休日を削減したり、営業時間を延長したりすることが物理的に困難という施設が多いので、近年は、時間延長以外の「サービスの向上」の提案が求められています。
「サービスの向上」は、大きく分けると「快適性」、「利便性」、「自主事業」に分けることができます。「快適性」には、接遇・マナーの向上、清潔な清掃などが、「利便性」には、わかりやすい施設内の案内表示や・パンフレット、利用手続きの簡素化、レンタル用品の充実、案内ガイドの配置などが、「自主事業」には、飲食の提供やイベントの充実などが考えられます。また、広報活動の充実や文化ホールでの許認可手続きの代行なども、指定管理では、「サービスの向上」に含めてよいと思います。
「サービスの向上」は、指定管理者選定の中で最も重要な勝負どころです。これらのカテゴリーから、対応可能なことをみなさんで議論して、ひとつでも多くアイディアを出し、事業計画書に盛り込むことが勝利への最大の近道です。
→[事業計画書作成のポイント]に戻る
指定管理者制度に欠かせない自主事業ですが、実は、自主事業の範囲がきっちりと決まっているわけではなく、自治体によって取り扱いが異なることも珍しくありません。例えば、公園でジョギング教室を実施することを、ある自治体では自主事業としていますが、別の自治体では、施設の利用促進の一環、つまり、指定管理者の本来業務として取り扱っています。
このあたりの難しい解釈は、別の機会にゆだねるとして、物販でもイベント開催でも自主事業を提案するにあたっては、ぜひ押さえておいてほしいことがあります。
それは、自主事業で利益を出すことを想定すべきでないということです。特に、民間企業は、自主事業でできる限り利益を出して、指定管理料を下げることを提案することがありますが、現状では、ほとんどの場合、評価されません。
公の施設には、設置目的がありますが、「利益を追求すること」が設置目的になっている施設はまずありません。民間企業のみなさんにはなかなか理解できないかもしれませんが、公の施設あくまで住民サービスのために設置しているのであり、自主事業も実費徴収を原則に設計された制度だからです。(ただし、自動販売機の設置等は例外です。)
したがって、自主事業を行う目的は、住民サービス、特に、施設の利便性向上(飲食等の物販など)や施設に親しみを持ってもらう(イベント開催など)ことを目的に実施するということを強調した事業計画書にすべきです。
なお、非常に財政状況が特に悪い一部の自治体では、自主事業で利益を上げることを奨励していることがまれにあります。これは、募集要項を見ればわかりますので、このような場合は例外と考えてください。
→[事業計画書作成のポイント]に戻る
「どのようなイベントを提案すれば審査会で高い評価が得られるか。」というご質問をいただきます。特に最近は、一部の大手企業が、有名アスリート・アーティストなどを招へいすることを提案して指定管理者に選定されていますので、これにどのように対抗したらよいかという趣旨のご質問が増えています。
実は、有名アスリート・アーティストを呼ぶという提案は、審査会でみなさんが考えているほど高い評価を得られるわけではありません。年に1回や2回、有名アスリートやアーチストが来たからといって、その地域のスポーツや文化の水準が高まるわけではありません。単発イベントがいくらすばらしい企画であったとしても、それで稼げるポイントはごくわずかなのです。
とはいえ、少しはポイントを稼がれるわけですから、対抗手段は考える必要があります。私は、体系的にイベントを提案することが一番良いと思っています。役所は理屈好きなので、「なぜ、このイベントを実施するのか」という理論武装をしっかりと体系的に提案すると評価が高まります。
体系的な提案の切り口は、「あらゆる住民に気軽に利用いただく」ということです。一般向けのイベントのほか、女性向け、高齢者向け、障害者向け、親子向け、外国人向けなど、特定の層に偏らない企画を行う旨を記載すれば、イベントのトータル的な企画力があるという評価を受けやすくなります。
→[事業計画書作成のポイント]に戻る
指定管理料の積算根拠についてもご質問をよくいただきます。一言で言えば、「いくらにすればよいのか。」という趣旨なのですが、自治体の方針や競合相手との兼ね合いがありますので「○○円」と具体的に言うことはできません。ただ、安ければよいというものではありません。
「コスト削減」は指定管理者制度の大きな目的です。ただし、自治体から見ると「よいコスト削減」と「悪いコスト削減」があることを知ってください。
まず、「悪いコスト削減」は何かというと、大きく分けて2つあります。ひとつは、「地元住民に負担を押しつけるコスト削減」です。たとえば、職員の給料を低く抑えるということを事業計画書に書く場合がありますが、職員は自治体の住民であり、この住民の給料をカットするということは、住民の生活水準を下げることを自治体が自ら容認するということです。
同様に、外部委託業者の委託料をカットするという方法も、その外部委託業者が地元企業である場合は、むしろマイナス評価だと考えてください。地元住民に負担を押しつけるようなコスト削減は、議会に説明する際に非難されるので、少しくらいならともかく、大幅な削減は自治体担当者としても避けてほしいというのが本音なのです。
もうひとつは、「安全・安心に関するコスト」を削減するものです。「そんなことするわけがない。」とほとんどの方が考えるでしょうが、自治体担当者から見て、「安全・安心に関するコスト」を削減していないと判断してもらえることが大切です。よく、一律に経費を5%とか10%とか削減している事業計画書をみるのですが、一律削減なので、修繕費も削減されています。
自治体担当者から見ると、「修繕費」は「安全・安心の確保」を確保するコストの代名詞と言ってもよいくらいで、これについては、確実にチェックをしています。一般に、施設は経年劣化していくので、前年度よりも「修繕費」の額が削減されているということは、前年度の修繕費の使い方に無駄があったということを証明しない限りは、明らかなマイナス評価となります。また、人員の削減も同様で、これは、削減する人員への負担押しつけともとれますし、人員を削減することにより、「安全・安心」に逆行するともとれるので、明らかに過剰な人員体制である場合を除けばマイナス評価になります。
逆に「よいコスト削減」なのですが、例えば、県外業者の外部委託費を削減するとか、印刷部数を減らして印刷費を削減するとかいうことは、「悪いコスト削減」ではないですが、そんなに工夫があるわけでないので、これで評価が上がるということはありません。
私の感覚で言えば、例えば、近くの建物(公の施設でなくてもよい)と夜間巡回警備契約を共同で実施して、夜間巡回警備料の単価を下げるとか、共同イベントを実施して、イベント開催経費を削減するとか「共同」や「連携」をキーワードにコスト削減を行うことが評価を上げやすいのではないかと思います。
もちろん、「共同」や「連携」で実施することによるコスト削減などは微々たるものです。ただ、自治体担当者が喜ぶのは、工夫されたコスト削減方法の提案で、つまり、議会から「住民に負担を押し付けるコスト削減ではないのか。」と質問されたときに「たとえば、共同で○○を行うことや●●を行うことにより、コスト削減を図ったものであり、職員や外部委託先に負担を押し付けたものではないと聞いています。」というように回答できることが、ある意味一番大切なことなのです。
→[事業計画書作成のポイント]に戻る
施設は人が運営します。ですから、施設に従事する職員のスキルは非常に重要な要素であることは言うまでもありません。ところが不思議なことに、職員のスキルの説明が充実しているという事業計画書はあまり見かけません。
指定管理者制度では、専門性の高い職員が管理運営に携わることが大前提になっているので、様式上、職員のスキルを記載する欄が重要に見えない(=維持管理関係の特殊な資格だけ記載すればよいように見える)ことが原因のひとつだと思います。
たとえが少しずれているかもしれませんが、プロ野球チームの魅力を説明する場合に、チームの強化方針の説明も重要ですが、やはりメインはエースや4番バッターをはじめとする選手の紹介でしょう。指定管理は様式があるので、これを無視して説明するというわけにはいきませんが、施設で業務に従事する職員のスキル(魅力)はもっともっと強調すべきと思います。
通常、資格や経験年数は記載していると思いますが、これだけでなく、例えば、「平成●●年の○○大会の企画運営に携わり、期間中の入場者が3,000人を超えるなど、大会を成功に導いた。」などの文章を入れると、高いスキル・ノウハウを持っていることを感じやすくなります。
なお、下線部の「企画運営に携わり」の部分は拡大解釈してかまいません。全く関わっていない場合は虚偽ですが、仮に駐車場の整理係だったとしても、運営に携わったことには間違いないのですから堂々と記載してなんら問題ありません。
→[事業計画書作成のポイント]に戻る
地域の住民・企業・団体・NPOなどと連携した管理運営を行うことは、いまや指定管理者として常識になっており、ほとんどの企業・団体が事業計画書に何らかの記載をしています。ということは、すべての応募者が何らかの提案を行うわけですから、よほど工夫して記載しないと競合先に差をつけることができないばかりか、逆に差をつけられかねません。
地域連携で高い評価が得られないパターンは大きく分けて2つあります。ひとつは、ボランティアを単なる「お手伝いさん」としか見ていない清掃ボランティアなどです。ボランティアを募集することは悪いことではありませんが、単に「清掃ボランティアを募集します。」では、あまりに工夫がなく、それでなくても、最近はさまざまな場所でボランティア活動の機会があるわけですから、「ほとんどボランティアは集まらない。」と審査委員に判断されます。
つい最近、ニュースで見たのですが、大阪城公園では、真田幸村の甲冑を身にまとったボランティアが清掃行っており、話題になっているようです。これなどは、利用者に評価され、評価されることが、ボランティアのやりがいを高め、さらにボランティアが集まるという好循環が期待できるので、単なる清掃ボランティア募集とは異なり、とても高い評価が得られる工夫ではないかと思います。
もうひとつ、高い評価が得られないのは、「住民からのアイディア募集」という提案です。住民が企画段階から運営に参加する理想的な事業と考えられているのか、公園や文化施設のロビー活用などで、このような提案をよく見受けますが、「企画の丸投げ」と評価される可能性があり、リスクが高い提案です。あくまで、大まかな企画は指定管理者が行うが、その中の一部について、住民からアイディアを募集するというスタンスで提案すべきものだと理解してください。
→[事業計画書作成のポイント]に戻る
個人情報保護も指定管理者に課せられた重要な責務です。ただ、これは、記載する内容がほぼ決まっており、記載漏れがなければ十分という分野です。記載すべきことをきちんと書いて、競合先に点差をつけられなければOKという発想で臨んでください。
記載すべき内容は、ほぼ次の4点です。
一点目は、「プライバシーポリシー(個人情報保護方針)の制定」です。現在の指定管理者のみなさんは、プライバシーポリシーは制定済みだと思いますが、忘れずに制定済みであることを記載してください。制定がまだだという方は、インターネットで検索すると様々な企業のプライバシーポリシーがヒットしますので、これを参考に制定してください。
二点目は、個人情報保護責任者の設置です。通常は、施設長を個人情報保護責任者にしていることが多いようですが、別に施設長でなくてもかまいません。ただ、公の施設の管理者として必ず設置しなければならないと考えてください。
三点目は、個人情報保護のために講じる措置です。これは、施設によって多少は異なるでしょうが、通常は、「個人情報取得の目的の明示と目的外使用の原則禁止」、「個人情報の厳格な管理(パソコンの暗証番号設定、鍵の付いた場所での個人情報の保管、目的が終了した個人情報の迅速廃棄など)」、「個人情報の持ち出し禁止」、「外部委託先への個人情報保護義務づけ」などを記載することで足ります。
四点目は、個人情報保護措置の検証です。個人情報保護が適正に行われるよう、職員研修を実施したり、定期的に個人情報保護責任者によるチェックを行うことなどです。
大規模施設の場合、個人情報相談窓口の設置や個人情報訂正申請の受け付けなどを記載することもありますが、基本的には、先の4点を記載すれば、十分合格点です。
なお、個人情報で高評価を得るために「プライバシーマーク」の取得に取り組まれている企業・団体の方がいらっしゃいますが、指定管理者選定に関しては、プライバシーマークの取得が大きなアドバンテージになることは、ほとんどないと考えてください。プライバシーマークは取得にも維持にも相当な費用・手間・時間がかかりますので、費用対効果を考えれば、指定管理者に関しては、あまりお勧めできません。
→[事業計画書作成のポイント]に戻る
地球環境問題への急速な関心の高まりを受け、指定管理者も地域の環境はもちろんですが、地球環境に配慮した管理運営を行うことが求められるようになりました。ただ、施設にもよりますが、ほとんどの場合、指定管理者ができることは、電気・水の使用量削減、グリーンカーテン、両面コピー、アイドリングストップ、廃棄物の減量・分別収集・リサイクルなど限られたことしかないと思います。
「ISO14001」や「エコアクション21」を取得しているのであれば、しっかりアピールしてください。ただ、これらは、取得に経費・手間・時間がかかります。リサイクルプラザのような環境部局が所管する施設を除けば、環境配慮で大きな点差がつくことは少ないので、環境配慮で高得点をとるために、今から「ISO14001」や「エコアクション21」取得にチャレンジするよりは、その努力を他の分野(サービス向上、安全確保など)につぎ込む方が合理的だと思います。
新たな取り組みとして、最近、私はLED電球の導入を検討するようアドバイスしています。LED電球の価格はまだまだ高く、いくら電気代が安くなっても指定管理期間でLED電球の代金を回収することはできません。「初期投資額を指定管理期間では回収できないけれども、それでも環境配慮の観点からLED電球を導入します。」という提案は、現在のところは多くの審査員に高い評価をいただいています。
なお、言うまでもないことですが、上記の提案は、施設内のすべての電球をLEDに交換するという内容ではありません。施設内の電球のうちひとつでもLED電球に変える予算が確保できるのであれば、堂々と提案してかまいません。
→[事業計画書作成のポイント]に戻る
みなさんは、公募で指定管理者を選定する手順をご存知ですか。公式的には、指定管理者を募集し、提出された事業計画書を審査して最も優れた提案を行った企業・団体が選定されます。これは嘘ではないのですが、すでに指定管理者制度が導入されている施設では、公募が始まる前から選定作業が始まっています。
自治体では、指定管理者公募が始まる3カ月くらい前から、募集や選定作業の検討を始めます。その際にまず最初に行われるのが、現在の指定管理者の評価です。利用者数、稼働率、モニタリング結果、安全・安心確保への取り組み、自治体施策への協力度合いなど、様々な観点から現在の指定管理者を総合的に評価し、あくまで一例ですが、以下のような公募に対する自治体のスタンスを決めます。
■他の企業・団体からよほど良い提案がない限り指定管理者を変えない。
■他の企業・団体から良い提案が出てくれば指定管理者を変える。
■できれば指定管理者を変える。
このような基本スタンスを定めた上で、指定管理料上限、指定管理期間、審査基準、その他要件(本社が県内になければ応募できないなど)の公募要件(募集要項)を固めていきます。当然のことですが、現在の指定管理者を基本的に変えないとスタンスであれば、現在の指定管理者が有利な公募要件になりますし、変えたいというスタンスであれば、現在の指定管理者の優位性が生かされない(管理運営実績の配点が低いなど)ような要件になります。
つまり、現在の指定管理者から見ると、公募が始まった段階で勝負は半分くらい決まっているのです。したがって、指定管理期間にどれだけ自治体の評価を高められるかが、現在の指定管理者にとって最大の次期公募対策なのです。
→[事業計画書作成のポイント]に戻る
「事業計画書はだいたい何ページくらいになるのが普通なのですか。」というご質問をよくいただきます。もちろん、自治体によっても施設によっても異なるのですが、ごく平均的に言えば、単体施設で40〜50ページ前後、「公園プラス体育施設」のように複合施設になっている場合で、60〜70ページ前後といったところではないかと思います。
このように回答すると「そんなにたくさん書くことがあるのか」という反応が返ってくることが多いのですが、みなさんが日ごろ努力していることを審査会で正当に評価してもらうためには基本的にはこれくらいの分量が必要です。
指定管理者を選定する審査委員は、それぞれ専門分野は持っていますが、自治体職員も含め、施設の管理運営ノウハウについては素人同然です。このため、みなさんが、「これくらいは当たり前」と考えていることが、実は全然理解されていなかったということが案外あります。
例えば、大規模な施設であればあるほど、安全管理やメンテナンスを行うための休館日が必要なことはみなさんには常識でしょう。ところが、休館日は少ないほどよいと考えている審査員はいまだにたくさんいて、「月曜日を休館日にします。」と記載するだけでは、全く評価されないどころか「怠けている」と減点される可能性まであります。したがって、「なぜ週1回休館日が必要なのか。」、「休館日にどのような安全管理やメンテナンスを実施しているのか」などをこと細かく説明し、休館日を設定しないことが安全管理上大きなリスクを生むことを説明することが必要なのです。
このようにみなさんが当たり前と考えていることを説明するだけでも、実はかなりの記載スペースが必要で、このため、事業計画書のページ数はどうしても多くなってしまうのです。
ちなみに、横浜市内の8つ公園(基本的に体育施設が併設されています)の事業計画書を情報公開請求し、閲覧したことがあるのですが、平均76ページでした。横浜市の場合は、競争が激しいので、平均的な分量よりは少し多いかなあという印象です。それぞれの自治体の事業計画書の平均的な分量は、このように情報公開請求で事業計画書を閲覧すれば、調べることができます。
審査委員は莫大な分量の事業計画書を応募者数分だけ読まなければなりません。本業を持ち、とても忙しい審査委員が本当にすべての事業計画書を読んでいるかどうか不安な方もたくさんいらっしゃると思います。
結論から言うと、よほどひどくて審査の対象とならない事業計画書を除けば、審査基準に関係するすべての項目を読んでいると考えてほぼ間違いありません。それは、審査にあたって、審査基準が必ずあり、審査基準(「利用促進」、「安全確保」、「維持管理」など)ごとに点数つけ、その点数の合計で優劣が決まるからです。つまり、各審査委員はそれぞれの項目ごとに評価を下さなければならないため、事業計画書の各項目に必ず目を通さざるを得ないという現実があるからです。
ただ、審査委員は忙しく、自治体からの報酬もわずかであるため、隅から隅までていねいに読む審査委員は少ないでしょう。その意味で、さっと目を通した時に何が書いてあるか頭に残りやすいように事業計画書の記載方法を工夫することは大切です。
様式にもよるのですが、私は、事業計画書の各項目ごとに、どのような内容が記載しているかのまとめを入れるようアドバイスしています。まとめを入れておくと、審査委員の頭にも残りやすいですし、プレゼン時にまとめ部分を中心に説明することで、審査委員が事前に読んで記憶に残ったことがよみがえるという効果も期待できます。
参入するにあたって、どうしても知っておきたいのは、現在の指定管理者がどのような事業計画書を提出しているかです。これは、札幌市のように、だれでも自由に閲覧できる自治体もありますが、多くの自治体では、情報公開請求を行わない限りは入手できません。実は、この情報公開請求にもやり方があります。
理由は長くなるので省略しますが、自治体職員は皆さんが思っているよりはるかに情報公開請求者に非常に悪いイメージを持っていることがほとんどで、法人名や幹部社員名で情報公開請求するのはやめた方が無難です。自治体側に名前が知られていない社員や社員の家族の名前で公開請求してください。この場合、自治体によって、住民のみが請求できる場合と、だれでも請求できる場合がありますので、住民のみ請求できる場合は、必ず、当該自治体内に住所がある社員(またはその家族)が請求してください。
請求すると、たいてい、①請求する文書範囲、②請求目的・意図を確認されます。このうち請求する文書の範囲は、「○○(施設名)の指定管理者公募にあたって、○○(指定管理者名)が提出した一切の書類」と答えてください。事業計画書と言わずに「提出した一切の書類」と表現するのは、自治体によっては、事業計画書と収支計画書が分かれている場合があり、「事業計画書」と限定すると「収支計画書」は公開されないからです。
請求目的・意図については、必ず「行政研究」とだけ答えてください。詳細な目的・意図を聞くのは、「では、○○と○○部分があれば結構ですね。」というように、公開する資料の分量を少なくする目的の場合がほとんどです。詳細な目的を話さなければならない義務はありません。何を聞かれても「行政研究です。」と言い切れば、このような、誘導に引っかかることはなくなります。
→[事業計画書作成のポイントに戻る]
指定管理業務に参入する場合、情報公開請求は非常に重要なアイテムですが、現在指定管理者の方にとっても役に立つ場合が結構あります。
ひとつは、競合先がどんな情報を持っているかを知ることができます。情報公開は請求しても全部の情報を公開するわけではありません。法人の内部情報や個人情報に該当する部分は黒く塗られて部分公開されます。
この黒く塗られる部分は自治体によって相当な開きがあり、事業計画書を情報公開請求しても、真っ黒に塗られてほとんど内容がわからない場合から、ほぼすべて公開する自治体まで千差万別です。ただ、同じ施設の事業計画書をAさんとBさんが情報公開した場合にAさんとBさんで公開される情報の範囲が異なるということはありません。したがって、現在の指定管理者の方が、前回公募時の自らの事業計画書を情報公開請求すれば、競合先がどこまで情報を入手しているかを知ることできます。
また、全国展開しているような大手企業の事業計画書は、内容はどこの施設も似たり寄ったりです。このため、全国展開している大手企業の参入の可能性がある場合は、他地域での事業計画書を入手すれば、相手の戦い方が予測でき、対応策を考えることが可能です。
なお、情報公開請求ができる対象者を住民に限定している自治体があり、この場合は、当該地区に住居がある親戚や知人等に情報公開請求者になってもらうなどの方策をとる必要があります。また、ほとんどの自治体で、情報公開請求には、公開期限の延長規定があり、これを適用されると事業計画書の入手まで6週間かかりますので、時間に余裕をもって請求することが大切です。
多くの方に施設を利用していただくことは、非常に望ましいことですが、公の施設の場合は、多すぎでも問題が生じます。
例えば、東京ディズニーランドが公の施設だったらどうでしょうか。もちろん、毎年、信じられないくらい多くの入場者があるのは、ディズニーランドならではの演出やサービスがあるからで、この意味では100点満点の管理運営が行われていることは間違いありません。
ただ、利用者が多すぎるゆえに、アトラクションはもちろん、レストラン、売店まで、相当長い行列が常態化しています。民間施設なら「長い待ち時間があっても行きたい魅力ある施設」ということになるのですが、不思議なことに公の施設になると、「利用者を長時間待たせる不親切な施設」という評価がされることが多々あります。そして、これは、「利用者を平気で長時間待たせる指定管理者」という悪評につながりかねません。
冷静に考えると、施設のキャパシティが小さすぎることは、自治体の需要予測の誤りであり、指定管理者の責任ではありません。にもかかわらず、努力して利用者を集めることが、指定管理者の評価を下げるとすれば、これは、まったくやりきれません。
実は、このようなことがみなさんの考える以上に発生しています。毎日のように利用者が施設キャパシティを上回っている施設は少ないかもしれませんが、土日に限ると、「予約が取りにくい」、「イベントの参加申込抽選で多数の落選者が出ている」という施設はかなりあるはずです。このような場合に、「利用者が多いことはよいこと」と判断して何の対策をとっていない場合は要注意です。
公の施設は、できる限り多くの住民に広く利用していただくことが原則です。利用者が多いことに満足せず、もう一段階上の対応を行えることが、自治体に評価される指定管理者です。
公の施設では、利用者が多すぎることにも対応が必要とご説明しましたが、では、実際どのような対応が考えられるのでしょうか。
利用者が多く予約が取りにくい施設の代表はスポーツ施設でしょう。スポーツ施設は週末に利用者希望者が集中しやすいことに加え、競技サークルのような特定団体の利用が半ば既得権化していることが多いからです。この既得権を無視すれば、ほとんどの場合、問題は解決しますが、現実的には難しいことだと思います。
私がお手伝いさせていただいたスポーツ施設にもこのような問題があったので、2つのことをアドバイスさせていただきました。
ひとつは、利用が少ない2階の会議室を一部改装し、ここで、アリーナで実施していた体操教室や太極拳教室などを実施することにより、アリーナのキャパシティを増やすことです。
ふたつ目はスポーツ教室の参加機会を増やすため、ジョギング教室やウォーキング教室など施設を使用しなくてもよいスポーツ教室を開催することです。
事業計画書にこれらを盛り込んだところ、指定管理者選定委員会では、私が考えていた以上に高い評価を受け、同時に公募された他の体育施設も含めたすべての応募者の中で、最高点を獲得し、指定管理者に選定されました。
もちろん、会議室の改装やジョギング教室の実施で、住民の希望すべてを満たすことはできません。けれども、住民の「利用したい」というニーズに少しでも応える工夫を提案したことが、審査員の心に響き、高い評価につながったのではと思います。
→[事業計画書作成のポイント]に戻る
みなさんは事業計画書の様式がどのように作成されるかご存知ですか。もちろん、前回の様式をそのまま利用したり、役所内の他部局の様式を流用したりすることもあるのですが、多くの場合は、まず、審査基準を定め、審査基準に沿って、つまり、採点がしやすいように様式を作成します。
この「採点しやすいように」というのは言い換えると、審査基準と様式が一致することなのですが、これには応募者側から見てリスクがあることを知っておく必要があります。
例えば、審査項目に「安全・安心の確保」、「適正な維持管理」という2項目があり、様式にもこの2項目を別々に記載する欄があるとします。審査する側が事業計画書を最初から最後まですべて一読して、その後に各項目ごとに採点してくれればよいのですが、審査基準と様式が一致していることから、当該項目だけを読んでまず採点し、次の項目のみを読んで、その項目を採点するということがよく起こります。
つまり、まず、「安全・安心の確保」の項目だけを読んで、この項目を採点し、後で出てくる「適正な維持管理」は様式でこの項目が出てきた時に別途採点されてしまうのです。
一般に「安全・安心の確保」と「適正な維持管理」には密接な関係があり、例えば、維持管理で実施している「施設・設備の点検」は多くの場合「安全・安心」のために実施しています。「安全・安心の確保」の記載欄に「点検」について記載していない(「適正な維持管理」の項目のみに記載している)とすれば、後に「点検」の記載が出てくるとしても、「安全・安心の確保」の項目の採点では、点検について全く考慮されずに採点されるということが発生するのです。
これを防ぐ方法は、「安全・安心の確保」の項目にも内容が重複することを承知の上で、「施設・設備の点検」を記載することしかありません。よく、内容が重複すると文章が「くどく」なるので、これを避ける方がいらっしゃいますが、事業計画書は文学作品ではないので、私は重複しても記載すべき、むしろ重要な内容は重複する方が審査する側の印象に残るとさえ思っています。「くどく」なるのがどうしても無理という方は、「施設・設備の点検については○○ページもご参照ください」というような注釈をつけて、他のページにも「安全・安心の確保」に関連する提案が出てくることを明示するという方法もあります。
事業計画書の作成に当たって、指定管理期間中の収支(=収支予算書)について記載する必要があります。実は、収支予算書にもいろいろなポイントがあって、例えば、A社とB社、指定管理料提案額が1億円で全く同じだとしても、収支計画書の記載方法によって、評価が大きく変わることは決して珍しくありません。これから2回にわたって、収支計画書作成のポイントをご説明します。
■原則として、詳細な内訳は必要ありません。
おそらく、みなさんは、事業計画書作成作業の中で、収支予算の積み上げにはかなりの労力を費やしているはずです。けれども、審査する側から見ると、収支予算書の細かい内訳はほとんど興味がありません。なぜなら、審査委員は大学教授、利用者代表、自治体職員など、施設運営経費の見積書を作成した経験がない人がほとんどで、収支予算書の細かい部分をチェックする知識・能力がないからです。
審査委員の中の公認会計士や税理士がチェックする場合もありますが、ほとんどの場合は、直近の現指定管理者の経費内訳と比べてみて、大きく数字が変わっている経費項目をピックアップし、その原因を分析したり、プレゼンで確認するだけで、数字の妥当性の検証(審査委員自らが見積書を徴収するなど)は100%に近いくらい行われていません。
よく、定められた様式の備考欄等で記載しきれないため、別紙をつけて、こと細かく内訳を記載している収支予算書を見ますが、添付した別紙(細かい内訳)はめったに読まれていない、つまり、はっきり言うと「無駄な努力」です。原則として、収支予算書に別紙など不要で、自治体が定めた様式をていねいに埋める以外の努力はあまり意味がないと考えてください。
■修繕費には注意を払ってください。
収支計画書の中で一番見られているのは、もちろん指定管理料の合計額ですが、二番目は修繕費の額です。他の項目でも紹介しましたが、審査する側から見ると、修繕費は安全確保や維持管理の根幹という認識で、これが大幅に減少していることは決してプラスにはなりません。
とはいえ、全体のコスト削減を行わなければならない中で、修繕費だけを聖域にすることは難しいでしょうから、少なくとも、「指定管理料は5%下げましたが、安全・安心の確保の観点から修繕費は2%の削減にとどめています。」というように、全体の削減率よりは削減幅を小さくするよう配慮すべきです。
■事業計画書の本文との整合性を確認してください。
例えば、利用料金制が導入されている施設で、毎年、利用者数が2%ずつ増加することを記載している場合、利用料金収入額も毎年2%ずつアップしなければ、整合性がないという評価をされます。
新たな割引制度を導入して利用者数を増やすので、利用者数増加割合と利用料金収入増加割合が一致しないという場合もありますが、この場合は、備考欄に一致しない理由を記載しなければなりません。備考欄に詳細な内訳を記載している方がたくさんいらっしゃいますが、収支予算書の備考欄は、細かい内訳ではなく、なぜこの額になったかという考え方を記載する欄だと考えてください。
■自治体が重視している項目が推測できる場合があります。
自治体が定めた収支計画書様式の中で、他の項目と比べて詳しい記載が必要な個所がある場合は、まず間違いなく、自治体が重視している項目です。例えば、他の項目は「清掃費」、「警備費」、「保守点検業務委託料」など、ごく大まかな項目なのに、人件費だけ所長、次長、職員A、職員Bなど個別の記載を求めているという場合は、低額な給料で職員を雇ってほしくないという自治体の意思表示です。つまり、収支予算書はもちろんですが、事業計画書本体にも、職員の人件費や労働環境に最大限配慮するという具体的提案が必要です。このように、収支予算書の様式で、自治体が重要視している項目が想定できることがあります。
→[事業計画書作成のポイント]に戻る
事業計画書本体と収支予算書には大きな違いがあります。それは、事業計画書は選挙で言えば公約であり、記載したことはよほどのことがない限り実施しなければなりません。 一方、収支予算書は、あくまで収入と支出の見積もりに過ぎず、例えば、イベント関連予算として50万円を計上したとしても、必ず50万円使わなければならないということはなく、実際の費用が40万円(あるいは60万円)であっても、事業計画書に記載したイベントを実施していれば、何の問題もありません。
つまり、収支予算書で変更できないのは指定管理料総額だけで、内訳は、比較的自由に変更できるのです。(もちろん、事業計画書に記載している内容を全て実施することが大前提です。)
ということは、指定管理料提案額が決まったら、内訳は後日変更できるのですから、審査で有利になる項目(修繕費など)を実際の積算額より高めに記載し、通常はあまり審査の対象とならない事務費などの額を下げるなどの調整を行う方が、審査上は得になります。
ただ、期間中に予想以上に不具合が発生し、修繕が必要になった場合に、自治体から、「修繕費予算がまだ残っているのだから執行しなさい。」と指導されるリスクがありますので、あまりに大きすぎる調整は行わない方が無難です。
→[事業計画書のポイント]に戻る
民間企業の方は企画書や提案書を作成する場合、パワーポイントを使うことが多いと思います。ところが自治体ではワード(一太郎)を使うことがほとんどです。この理由は民間の方と自治体職員の発想の違いにあります。
民間企業(おそらく外郭団体も同じだと思います。)で企画書等を作成する場合、「こんなことができる。」「こんなメリットがある。」などの「実施する内容」や「結果」が最も重要です。このため、これらを簡単に強調できるパワーポイントが使用されることが多いのでしょう。
一方、自治体では、何か新しい企画・立案を行う場合「なぜ行うのか」という「理由(理屈)」が「内容」、「結果」と同じくらい重要です。「理由(理屈)」を細かく説明することは、パワーポイントよりもむしろワードの方が適しているため、ワードが使われているのです。
これは、指定管理者の選定の場合も同じです。自主事業やイベントに「何の脈絡もなくこれとこれとこれを実施します。」と記載している事業計画書をよく見ますが、ひとつひとつの自主事業やイベントの内容がどんなにすばらしくても、「なぜ行うか」という「理由(理屈)がないと自治体職員から高い評価を得ることは困難です。例えば、「高齢者の利用が少ないので、高齢者をターゲットとした○○を実施します。」というように、自主事業やイベントには理由(理屈)をセットで記載するということを忘れないでください。
神奈川県川崎市で「公契約条項」を盛り込んだ条例が可決されました。政令指定都市では全国で初めてで、政令指定都市以外でも、千葉県野田市などごく一部しか事例がないそうです。「公契約条項」とは、自治体が発注する工事等において、発注業者と労働者や下請業者の契約に条件をつけるもので、自治体発注業務でのいわゆる「官製ワーキングプア」をなくすことを目的としています。
厳しい財政状況を背景に、自治体はあらゆる分野でコスト削減を進めていますが、一方で、住民である労働者や下請業者に「しわよせ」がいくことに頭を痛めています。指定管理者の選定でも、住民や地元業者に一方的に負担を押しつけるコスト削減が評価されないのはこのためです。
川崎市の条例によると、受注業者は、下請業者を含む業務に従事する労働者(一人親方も含む)の名前、職種、労働時間、作業報酬などを記載した台帳を市に提出する義務や市の立入調査、是正命令に応じる義務があり、改善されない場合は、契約解除などのペナルティを課せられます。作業報酬の下限額は市の審議会で決定されますが、法律である最低賃金を守ることは当然なので、それ以上の水準になることは確実でしょう。
話は変わりますが、この条例の「下請け業者を含む業務に従事する労働者の名前、職種、労働時間、作業報酬などを記載した台帳を市に提出する」という規定は、指定管理者公募の際の事業計画書に記載する内容としても十分使える、自治体にとって魅力的な提案だと思います。下請業者(指定管理者制度では外部委託先)も含め、労働者の労働条件に配慮を行い、その配慮を示す台帳を自主的に自治体に提出するという姿勢は、高い評価を受ける可能性が高いように思いますので、川崎市以外の施設に応募される方も検討してみてはどうでしょうか。(川崎市は条例で義務化されているので高い評価を受けることはありません。)
なお、自治体の関心があるのは、自らのエリア内(市内、県内など)の労働者や下請業者です。市外(県外)の業者に外部委託する場合は、いちいち労働者の名前や報酬などを自治体に提出するような手間のかかる作業を行っても全く評価されないので、提案する場合は、市内(県内)に限定しておくほうがよいでしょう。
最近、政権政党に強烈な逆風が吹いていますが、指定管理の世界でも風が吹くことがあります。例えば、ある東日本の自治体では、平成21年度は、17施設の公募があったのですが、すべての施設で現指定管理者が勝ち、参入側はノーチャンスでした。
おそらくこれが原因(=応募しても現指定管理者に勝てるはずがないというあきらめムードの蔓延)で、翌年(22年度)の5施設の公募では、合計でわずか7企業・団体、すなわち現指定管理者5企業・団体と新規参入希望企業2企業しか応募がありませんでした。(3施設は競合がなく、現指定管理者のみの応募)
結果は、なんと、複数の応募があった2施設の両方で現指定管理者が敗れ、参入を希望する2企業はいずれも新たな指定管理者に選定されました。ここから先は私の想像ですが、応募者があまりに少ないのはまずいと考えた自治体が、参入側にチャンスを与えたという部分があるのではないかと思います。これが当たっているのであれば、敗れた指定管理者は、逆風に巻き込まれたと言えるでしょう。
実は、このような風が吹いたと考えられる事例は、案外たくさんあって、特に、民間企業の指定管理者が事故を起こした場合、当該自治体や周辺自治体では、外郭団体の勝率が明らかに高くなる、つまり、外郭団体に追い風が吹くということが全国各地で起こっています。
残念ながら、みなさんは風を制御することはできません。どんな逆風が吹いても指定管理者選定されるよう、事業計画書に記載した内容プラスアルファの管理運営を行うことが指定管理者であるみなさんにできる唯一の風対策のように思います。
また、上記の例では、21年度の参入側全敗という結果にもめげす、あきらめずにトライした2企業が勝利を手にしました。参入する側に追い風が吹くこともあるわけですから、参入しようと考えている方は1回や2回の落選であきらめずに挑戦し続けることが大切なのではないかと思います。
最近、指定管理業務に参入したいということで、さまざまな企業・団体の方からご質問をいただきます。その中で比較的多いのが、「応募する施設の利用者の生の声を聞いた上で、改善提案をしたいのですが・・。」というものです。
その意欲は非常に評価するのですが、実際には難しい面があります。公の施設内で現在の指定管理者が利用者アンケートを行うことは「指定管理業務の一環」であり、法的に何の問題もありません。けれども、指定管理者ではない者が施設内で利用者アンケートを行うことは、施設の目的外利用に当たり、自治体の許可がないと行うことはできません。
通常、自治体は、全く関係ない第三者が施設内でアンケートを行うことをみとめることはまずないので、実質的には、参入しようとする側が施設内でアンケートを行うことは不可能です。(無許可で行なったことが発覚すると、自治体の当該企業(団体)の評価が下がり、指定管理者に選定されることが絶望的になります。
よく、街中で実施しているインタビュー形式のように、施設から出てきた利用者をつかまえてアンケートすることは不可能ではありませんが、これも、道路上で行うなら、道路管理者の許可が必要な行為です。事業計画書に「ヒアリング調査をしました」と記載して、審査時に道路管理者の許可を取っていないことが発覚すると、違法行為を自治体が認めることはできないので、落選確実になります。(道路管理者の許可も施設の目的外使用同様、簡単にはとれません)
結局、当該施設をよく利用している住民、団体、チームなどを見つけ、それらの方々の話を聞くというくらいしか方法はありません。ただ、この方法は、話を聞く相手が自らの身内、友人、知人などに偏る可能性が高いので、聞く相手をどのように公平に選んだかを記載しないと高い評価は得られません。率直に申し上げると、参入しようとする側が利用者アンケートを行うことはかなり難しいというのが私の意見です。
このことは、現在の指定管理者にとって、利用者アンケートがいかに大きな武器かということの裏返しです。単に「アンケートBOXを設けて、投函を待っているだけ」というのは非常にもったいない話で、ぜひ「積極的に利用者のご意見を収集し、これを管理運営の改善につなげています。」と次の事業計画書で記載できるようなアンケートと改善実績をたくさんつくってください。これは、現指定管理者にしかできない大きなアドバンテージなのです。
利用料金制が導入されている施設では、条例で利用料金額の上限が設定されており、通常は公募時にこの上限以下で指定管理者が実際の利用料金額を提案する必要があります(あくまで、提案であり、最終的には自治体の承認が必要です。)。 この利用料金設定をどのようにすべきかよくご質問をいただきます。もちろん、自治体の考え方や施設の事情によりケースバイケースなのですが、基本的な考え方を紹介します。
指定管理者制度が導入されたばかりの平成17、18年度ごろは、指定管理者制度導入のメリットを利用者が実感できるよう利用料金を引き下げることを歓迎する自治体が多数で、ずっとデフレ経済が続いていましたから、利用料金引き上げを歓迎する自治体はあまりありませんでした。
けれども、自治体の財政状況が年々悪化しており、「利用料金を下げるくらいなら、指定管理料を削減してほしい」と考える自治体が明らかに増えているほか、むしろ、利用料金を引き上げることを歓迎する自治体も出てきています。このため、指定管理者公募において、「利用料金引き上げ」、「利用料金据え置き」、「利用料金引き下げ」のどれが高い評価を受けるかを判断することが非常に難しくなっています。
まず、直近(過去1年くらい)に条例が改正され、利用料金上限額が引き上げられている場合は、自治体が利用料金引き上げを求めていると考えるべきです。住民に負担増を求める条例改正を行うには議会の根回しに相当な手間と時間が必要で、「とりあえず」というような安易な動機で利用料金引き上げの条例改正が行われることは考えられないからです。
ただし、例えば、条例で利用料金額上限が10%引き上げられたからといって、同率の引き上げを行うことがよいとは限りません。増税大歓迎の財務省がたばこ税の引き上げに抵抗しているのを考えればわかると思いますが、利用料金額を引き上げにより利用者が減少して、結果的に利用料金収入が減少するのでは意味がないからです。また、ほとんどの場合、議会の根回しで「条例改正の趣旨は、サービス向上にかかる経費の一部を利用者にご負担いただくことを可能にするものであり、仮に利用料金が引き上げられても、それはサービス向上の範囲内であり、利用者数が大幅に減少することはないと考えています。」と説明しているので、この趣旨に合致する範囲で利用料金の引き上げを提案することが高い評価につながると考えるべきです。
直近に条例改正がない場合は、審査基準が一応の目安となります。審査項目の「経費の削減」のウエイトが高い(全配点の概ね35%以上)場合は、経費を重要視しているわけですから、料金値上げにより多少利用者が減少しても、利用者数減少分を補えるだけの利用料金収入増加が見込まれるなら、利用料金を引き上げる方が高い評価を得られやすいと考えて方がよいでしょう。
一方、「経費の削減」のウエイトが30%未満の場合は、自治体がより多くの利用者を求めている可能性が強く、利用料金据え置きの方が高い評価を得られることが多いはずです。
なお、最近は、財政状況の厳しい自治体が多いので、利用料金の引き下げは、引き下げることにより利用者数が増え、結果的に利用料金収入が増加すると考えられる場合以外は提案しない方が無難だと私は思います。
昨年と全く同じことを書くのですが、ありがたいことに今年も非常に多くの方から仕事のご依頼をいただきました。けれども会社の規模が小さく、多くの方からのご依頼をお断りせざるをえず、ましてやホームページの更新にまでは手が回らない状況でしたが、やっと業務が落ち着いてきましたので、ホームページの更新を再開します。
今年は、はじめから結果が決まっている形だけの公募が大きな県から小さな市まで結構ありました。北陸地方のある市役所のように、ホームページのトップ(新着情報)に公募情報を掲載せず、都市計画課のページにだけ目立たないように掲載しているような露骨な事例も見受けられました。
これは、私だけの感想ではなく、多くの企業の方も感じているようで、今年は「議員に頼んでみたい」という話を本当によく聞きました。私の経験から言うと、指定管理に関しては、議員に依頼したからといって公募で有利になることはほとんどなく、むしろ、役所の反感を買って、マイナスになる可能性が圧倒的に高いのが現実です。
指定管理者の公募時期には、すでに役所の来年3月の退職予定者が決まっています。そして、退職予定者の天下り予定先が指定管理業務を行っている場合はその法人が指定管理者から外れると退職者の行き先がなくなってしまいます。
はじめから結果が決まっている公募は、このような人事関係の事情があることがほとんどで、議員が多少圧力をかけたくらいで、ひっくり返すことは非常に難しいことなのです。(もちろん、指定管理者の指定は議会の議決事項なので、議員の半分以上がプレッシャーをかけると、ひっくり返すことができますが、1人や2人の議員では普通は無理です。)
ほとんどの場合、議員側もこのような事情を心得ていて、有権者から依頼されると、「わかりました」と答えて、機械的に担当部長(課長)には話をしますが、有権者向けのアリバイづくりというレベルに過ぎません。結果として、議員からが良い返事をもらったけれども、自治体の判断は変わらなかったということになります。
率直に言って、はじめから結果が決まっている公募については、議員に依頼してもムダで、応募しないということが一番の対策です。どのように見分けるのかは、難しい場合のですが、基本は、現在の指定管理者に役所のOBがいるかどうかです。OBがいる場合は、OBの任期(普通は2年か3年)を調べ、任期が年度末で切れる場合は要注意です。年度末で切れるということは、後任人事が決まっている可能性があるからです。
少し不思議な言い方ですが、任期が年度末で切れない場合は、公募で勝てる可能性も出てきます。本人(OB)が自ら事業計画書を書いて負けたのは本人の責任ですが、次にそのポストに内定している人は自分で事業計画書を書けないので、他人のせいで内定者のポストがなくなるのは酷というのが役所の論理だからです。
→[事業計画書作成のポイント]に戻る
仕事柄、指定管理者選定に関する情報がよく入ってきます。その中で最近、結構あるのが「自治体から指定管理者に応募するように要請されたのに審査で選定されなかった。」という話です。おそらく、「自治体から要請されたから指定管理者に選定される」と考えていたのでしょうが、実際は違うことの方が圧倒的に多いと考えるべきです。
自治体にとって、指定管理者を公募して1法人だけしか応募がないというのはできる限り避けたいと考えています。それは、議会から応募条件の妥当性を問われる、すなわち、意図的に現在の指定管理者に有利な公募条件にしたのではないかと追求される可能性が高いからです。(現在の指定管理者が外郭団体の場合は特に追求を覚悟しなければなりません。)
このため、現在の指定管理者を交代させるつもりなど全くないにもかかわらず、「○○○○○の公募があるから応募してみては」などと声をかけることがあります。ひどい場合は、例えば「今の指定管理者はやる気がない」などと現在の指定管理者の悪口を言って薦める場合があるのですから、本当に迷惑な話です。
とはいえ、本当に指定管理者を交代させようとして、応募を薦める場合もゼロではないので、なんとか自治体の本音を探らなくてはなりません。正直、なかなか難しいのですが、ひとつの目安としては、特別な情報を提供してくれるかどうかです。
例えば、公募開始前に応募を薦められた場合、「事業計画書を作成するスタッフを確保しなければならないので、いつ公募がはじまって、いつが締め切りか教えていただけないでしょうか。」というように、公表されていない情報の提供を求めるのです。もちろん、このような情報提供は 厳密には守秘義務違反ですが、公募が始まれば明らかになる事実なので、本当に指定管理者に選定したいと考えているのであれば、できないことではありません。逆の言い方をすると、このようなこと(=公募が始まれば明らかになる事実)さえ事前に情報提供してくれないのであれば、とりあえず応募数を増やしたいと考えているだけだと判断すべきです。
ちなみに、公募が始まった後で自治体が応募を要請してきた場合は、前向な姿勢だけ見せて、応募しないのが賢明です。これは、公募したけれども問い合わせの電話や該当するホームページのアクセスが少なく、自治体が応募者数を増やしたいと焦っている場合と考えてほぼ間違いありません。本気で指定管理者に選定する気持ちがあれば、絶対にもっと早い段階で要請するからです。(2012.5.12)
まだ、24年3月なのですが、25年度の公募について、たくさんのご質問をいただきます。その中で、今年、特に多いと感じるのが収支予算に関するものです。指定管理者制度が導入されてからずっと、日本はデフレ経済でした。ですから、収支計画書で、物価上昇は考えなくてもよかったのですが、電気料金の値上がりや政府のインフレターゲット政策などで、25年度の公募ではそうもいかなくなっており、たくさんご質問をいただいているのだと思います。
電気料金やガソリンなどは10%単位で価格が上昇しており、これから先も上昇が避けられない中で、ほとんどの場合、物価上昇のリスクは指定管理者が負担しなければならないことになっていますから、結構、切実な問題です。
当然の話ですが、指定管理者制度導入の目的である「コスト削減」の努力は行う必要があります。その上で、指定管理者は行政の代行者なのですから、日本の行政のトップの発言である「インフレターゲットの目標2%」というのも、尊重しなければならないと私は思います。
とすれば、支出については、現在の指定管理料をまずいくらか削減したうえで、削減した数字を毎年2%ずつ増やしていきます。一律2%ではなく、租税公課のように2%増やす必要がない経費項目もあるでしょうし、一般に人件費の上昇は、物価上昇よりも遅れるとされていますので、何年かは、人件費は据え置きという考え方もあるとは思います。
また、収入ですが、インフレターゲット政策は物価を上げることが目的ではなく、デフレを脱却して、経済を活発化することが目的です。このため、経済が活発化するのですから、利用者数も当然増えるという理屈になります(このように考えないと、自治体や指定管理の審査委員から自分に都合のよい部分のみを収支計画に反映していると判断されてしまいます。)。これも毎年2%増えるというのが妥当でしょう。
以上から、あくまで理屈の話ですが、政府の施策で2%利用者が増え、さらに指定管理者の努力でいくらかは増えなければなりません。したがって、利用料金制が導入されている施設では、少なくとも、毎年2%プラスアルファの利用料金収入増加を見込む必要があるということになります。
これらを基本に、あとは募集要項で発表される指定管理料の上限をもとに、最初の指定管理者の努力によるコスト削減をどの程度にするかを考えるとよいと思います。(2013.3.7)
サービス水準の低下を認める応募条件の緩和
平成25年度の公募において、現指定管理者が応募しないという事例が、私の知る限り全国で6件ありました。このうち1件は、ある県営住宅ですが、実はある民間企業から、当社に相談がありました。内容は、県から「現在の指定管理者が応募しない可能性が強いので応募を検討してほしい」との要請があったようで、「指定管理の実績がほしい。指定管理料は低く採算性は厳しいが、それでも応募したい。ついては、事業計画書作成の支援をしてほしい。」というものでした。
この県は面積が広く、県内を数ブロックに分けて、指定管理者を公募しています。相談があった企業が応募を考えているブロックは山間部で、前回公募では、ブロックのほぼ中心に位置するA市に県営住宅の管理事務所を置くことが、指定管理者の要件のひとつとなっていました(現在の指定管理者はA市内にある自社の営業所の一部を管理事務所として供用しています。)。
ところが、今回の公募では、「県営住宅の管理事務所をA市内中心部から自動車で1時間(概ね50キロ)以内の場所に設置すること」なっており、A市の周辺部であるB市、C町、D町などに県営住宅の管理事務所を設置することも可能になっています。(したがって、一番多くの入居者が多存在するA市中心部の団地からは、管理事務所が遠くなる(=サービスが低下する)可能性があります。これは、おそらく、県が、現在の指定管理者が応募しないことを想定しており、人口が8万人に満たないA市に管理事務所を設置することを要件にしたのでは、応募法人がゼロの可能性もあると考えて、要件を緩和したのだと考えられます。
ただ、これは非常に危険な要件緩和です。現在A市内にある管理事務所が周辺部に移転すれば、多くの団地があるA市中心部の入居者から確実に反発があるからです。公園や文化ホール等は「不満があれば利用しない」という選択が可能ですが、住宅はそういうわけにいきません。したがって、入居者の不満が収まる可能性は少なく、自治体はクレームに弱いですから、最終的には、A市内に管理事務所を設置するよう強制(自治体から言えば要請)されるリスクが極めて高いでしょう。
この会社はA市内に事業所がないので、A市内に市営住宅の管理事務所を設置するとなると、新たに事務所を借りなければなりません。事務所の賃料相場がだいたい月5〜6万円程度だそうなので、私は、「年間60万円支払ってA市内に管理事務所を置く覚悟があるならお手伝いさせていただきます」と回答しました。相談していただいた企業は、ただでさえ採算性が厳しいのに、さらに年間60万円も負担することは困難であると判断し、最終的には応募を見送りました。
財政状況が厳しいことなどを理由に、自治体が募集要項や仕様書で、サービス水準の低下を認める事例が増えていますが、額面どおりには受け取らない方がよいと思います。住民(入居者、利用者など)からクレームがあった場合、自治体が盾になってくれる場合はまれで、多くの場合は、住民側に立って指定管理者にプレッシャーをかけてくるからです。指定管理者も地元住民とは様々な付き合いがありますから、会社への風評などを考えると、最終的には、以前のサービス水準に戻すという経営判断をせざるを得ません。特に、今回の事例のように、現指定管理者が応募しないということは、もともと、指定管理料などの条件が厳しい上に、さらに、想定外の負担をするリスクを背負うということで、慎重を期して考える案件でしょう。
あくまで一般論ですが、何の不祥事もないのに現在の指定管理者が応募しないということはよほど厳しい条件があると考えるべきです。このような場合に、自治体が応募の条件を一部緩和することがありますが、これが住民へのサービス低下につながる場合は、後に、住民からの要望という理由で、自治体も加わって、改善要望(=指定管理者の負担でもとのサービス水準に戻してほしいという事実上の行政指導)が行なわれ、最終的には対応せざるを得ないというリスクがあることはぜひ知っておいてください。(2013.12.15)
→[事業計画書作成のポイント]に戻る
前回の募集要項・仕様書
自治体は基本的に保守的ですから、募集要項や仕様書は、前回を踏襲するのが基本です。言い方を変えると、変更する場合は相当な理由が必要で、これを上司に説明し、了解してもらうにはかなりの手間が必要です。つまり、募集要項や仕様書を変更するということは、大きな手間をかけても変えなければならない重大な理由があるということで、今度の審査での大きなポイントになる可能性が高いと言えるのです。
特に、審査基準で配点が高くなっている項目や、様式で前回よりも詳しい記載を求められている(または前回はなかった様式が追加されている)項目がある場合は、自治体が今回の審査で大きなウエイトを置いている項目と考えて、ほぼ間違いありません。
もちろん、審査項目や様式全般に渡って、新たな提案を行なうのがベストですが、一方で、経費的な限界もありますから、メリハリが必要です。とすれば、自治体が重視している項目に重点を置いて、新たな工夫や改善を数多く提案することが、勝つ確率を高めることは間違いなく、これを判断するために、前回の募集要項、仕様書との比較を行なっているのです。
なお、前回の募集要項・仕様書は、通常は、情報公開請求を行なわなくても、自治体の担当課に行けば、コピーしてもらえるはずです。ただし、公募が始まってしまうと、特定の応募者にだけ資料を渡すことはできないので、簡単にはもらえなくなってしまいます。ですから、早めに入手するようにしてください。(2014.5.18)
→[事業計画書作成のポイント]に戻る
事業計画書に使用する写真
今年度もたくさんのご依頼をいただきました。ただ、会社の規模が小さく、お手伝いできる業務に限界があるため、せっかくご依頼いただいたにも関わらず、お断りせざるを得ない案件が発生しており、ましてや、サイトの更新までは手が回りませんでした。やっと、業務が落ち着いてきたので、サイトの更新を再開します。気軽に読んでいただければ幸いです。
現在の指定管理者の事業計画書作成をお手伝いする場合に、私は、できるかぎり、写真を掲載するようアドバイスしています。指定管理の審査委員は、施設のヘビーユーザーではないことがほとんどなので、「百聞は一見に如かず」という「ことわざ」のとおり、特に、成功した(=多くの参加者があった)イベントの実績を記載する場合などは、文章で説明するよりも、ビジュアルで見せた方が効果的だからです。
けれども、現実に「写真はありますか」とお尋ねすると、適当な写真がない場合が少なくありません。特に多いのが、イベント自体の写真はあっても、イベントと多くの参加者が一緒に1枚の写真に入っているものがないことで、参加者がほとんど写っていないと「多く方にご参加いただきました。」という文章に説得力が出てきません。
おそらく、最近は、個人情報や肖像権の問題が厳しくなっているので、職員が利用者を被写体にするのを避けるという傾向があるのではないかと思います。ただ、写真が指定管理者の実績や高いイベント開催ノウハウをアピールする重要なツールであることは、これからも変らないと思います。多くの参加者が写っていればよいのですから、後ろ姿でも全く問題ありません。公募を有利に戦うためにも、公募年度の事業計画書作成を見据えて、参加者が多いイベントはもちろん、職員研修、防災訓練、アンケート収集、訪問営業活動などの写真を、計画に集めていくことが大切だと思います。
特に、来年度に公募がある指定管理者の方は、今から事業計画書に載せることができる写真があるかどうかを確認して、もし、適切なものがない場合は、公募までに集めるように措置を講じてください。
なお、イベントで写真撮影を行なう場合、会場入口に「本日、イベントの記録を残すために写真撮影を行ないます。お客様が写り込む場合がありますが、ご了承ください。」と表示している施設もあります。知り合いの弁護士の見解では、法的には十分な措置ではないとのことですが、それでも、何もしないよりはよいのではないかと私は思います。(2014.11.13)
→[事業計画書作成のポイント]に戻る
事業計画書に記載する男女共同参画
早いもので、平成26年度も残り少なくなりました。27年度は、本格的に指定管理者の公募が始まって10年目ですから、5年周期での公募年度に当たっている施設が数多くあると思います。 時間はすぐに経過します。早めに事業計画書作成に取りかかることが大切だと思います。
事業計画書を作成する場合に、記載する材料が乏しく、困ることが多いのが男女共同参画です。現場や本社に女性の管理職がいたり、現場で多くの女性が活躍していれば何とかなりますが、そうでない場合は、「男女の区別なく、適材適所の登用を行っている。」と記載しても説得力が全くありません。
「事業計画書の様式に男女共同参画の記載項目がないので心配ない」と考えている方も多いと思いますが、決して安心はできません。現政権は女性の社会進出に力を入れており、つい最近も、「2020年の配偶者が出産した直後の男性の休暇取得率(有給休暇等も含む)の目標を80%、男性の育児休業取得率の目標を13%」とすることが閣議決定されました。現在の男性の育児休業取得率が2%程度ですから、非常に高い目標です。
このような高い目標ができた以上、自治体も大きな影響を受けます。前回、様式に記載項目がなかったとしても、27年度の公募では、「男女共同参画」、「ワークライフバランス」などの項目が新設される可能性は結構あると思いますし、仮に、記載項目がなくても、管理運営体制の項目で、「このような政府の目標を踏まえた体制整備に努めており、今後も努力を継続する。」と記載すると、評価を高めることができるでしょう。
現指定管理者の方は、「努める(=これから努力する)」と記載すると、「なぜ、今まではできなかったのか」という疑問を呈する審査員が多いので、少しでよいですから、男女共同参画等が様式に加わることを想定して、今から実績づくりに着手した方がよいと思います。
指定管理の現場だけでなく、法人全体の職員で考えてよいので、公募までに、出産直後の休暇取得や男性の育児休業取得者(3〜4日程度の短期間でもかまいません)が1人でも出るのが、実績としてPRするには一番でしょう。事業計画書に「出産直後の男性の休暇取得実績や男性の育児休暇取得実績がある等、これまでも努力して参りましたが、政府が閣議決定した目標を踏まえ、今後もさらに男女とも働きやすい職場づくりに努めます。」と記載できれば、少なくとも、この分野で、他法人に点差をつけられることはほぼないと思います。
出産直後や育児休暇の対象となる3歳未満の子どもがいる職員が在籍しない場合は、公募までに関連するセミナーや講演会に職員を出席させることだけでもぜひ検討してみてください。そうすれば、「職員を男女共同参画に関連するセミナー・講演会に出席させる等により、関心を高め、女性が働きやすい職場づくりに努めています。」と記載することができます。(2014.3.29)
2期目に向けての努力
今年度のある自治体の指定管理者公募で、民間企業が財団に敗れたケースがありました。前回公募では、民間企業が財団に勝利しており、今回は、逆の結果となりました。たまたま、出張中に地元紙の記事を読んだのですが、「かつての財団時代の運営より劣っていたとは思えない」と、敗れた結果に納得していない民間企業のコメントが掲載されていました。
新聞記事を読んだだけで、私自身が全体像を知らないという前提で読んでいただきたいのですが、このコメントだけを読むと「ポイントがずれている」というのが、私の感想です。
敗れた民間企業が、かつての財団時代よりも優れた管理運営を行っていたことは、おそらく事実でしょう。ただ、自治体から見ると、指定管理者を交代させた以上、これは当然のことです。つまり、以前の指定管理者よりも優れた管理運営を行っていることは当たり前で、今後、さらに管理運営を進化させるために、どのような取り組みを行うかが、審査の大きなポイントです。
敗れた民間企業のコメントからは、過去よりも優れた管理運営を行っていることに安住し、今後の新たな取り組みに関する部分のアピールが弱かったのではないのかということが推測できます。
加えて、敗れた財団側は、おそらく、敗因を分析し、次回での捲土重来を期して、この数年間努力していたのでしょう。自治体と財団は距離が近いので、財団が努力している姿は、必ず自治体に伝わります。そうすると、「もう一度財団にチャンスを与えても・・・・・・」と自治体が考えることも決して珍しくありません。指定管理を奪った側、特に、民間企業が財団に勝った場合は、敗れた側が次回を目指して努力していることを決して忘れてはなりません。管理運営で実績を上げることはもちろんですが、次回公募で、敗れた側が努力して優れた提案を行うことを前提に、それを上回る事業計画書を作成することが求められているのです。(2015.11.27)
→[事業計画書作成のポイント]に戻る
少人数での緊急対応
小さな施設では、初期消火と避難誘導を1名の担当者が兼務してもかまわないと思いますが、特に、出勤者が1名しかいない時間帯がある施設の場合、「1名の職員が緊急対応に関するすべての業務を行います。」と記載しても、「本当に対応できるのか」と判断されてしまい、高い評価を得ることは、難しいと思います。
このような場合、私は、協力者をつくることをお薦めしています。具体的には、万一の場合、施設の常連利用者や、施設に隣接する商店の方などに避難誘導や初期消火に協力してもらうよう、あらかじめ依頼しておくのです。「利用者に依頼するのは責任転嫁では・・・・」との反論をいただくことも少なくないのですが、例えば、飛行機でも、非常口近くに座る搭乗者は、避難誘導を手伝うこととなっており、自治体から見て、緊急時に利用者の協力を得ること前提とすることが評価を下げることは、まずないと思います。 加えて、協力者にも、防災訓練や緊急対応研修に参加していただくことができれば、むしろ、評価を上げることもできるでしょう。(2016.2.13)
「枚」と「ページ」
事業計画書の作成する場合に、「事業計画書は50ページ以内で作成すること」とか、「1項目当たり2枚以内とすること」のように、自治体が分量を制限する場合があります。勘違いされている方も少なくないので、この 「枚」 と 「ページ」 の違いを再確認してください。
「枚」という単位が使われている場合、「両面印刷不可」 という条件がない限り、両面に記載ができますので、「1枚」 イコール 「2ページ」 という意味です。「事業計画書全部で50枚以内」 というように、全体にのみ制限がかかっている場合はこれだけ理解すれば十分ですが、「1項目1枚以内」 のように項目ごとに制限がある場合は、もうひとつ注意することがあります。
例えば、「1項目1枚以内」 という制限ある場合に、最初の項目の分量が1ページだったとします。そして、次の項目の分量が2ページで、1項目に続けて記載したとすると、この項目は、1枚目ページ目の裏面と、2ページ目の表面に渡りますから、2枚となってしまい、「1項目1枚以内」 という条件を満たさなくなってしまいます。
同様に、「1項目1ページ以内」 との制限がある場合で、最初の項目が半ページくらいで、次の項目を1ページ目の中段から2ページ目の上段に記載した場合も、2ページに渡ってしまうので、これも条件を満たしません。
これらのケースは再提出を求められることの方が多いとは思いますが、減点されても文句は言えないので、気をつけるようにしてください。
項目ごとに分量制限があり、特定の項目の記載量が分量制限一杯に満たない場合は、必ず余っている分量の部分を余白にし、次の項目は、新たな 「紙」 または 「ページ」 から記載しはじめるようにしてください。(2016.6.2)
→[事業計画書作成のポイント]に戻る
防災に関する提案の検討
毎年、同じことを書くのですが、今年も、全国各地から多くの業務のご依頼をいただきました。特に、7月〜9月は、多くの方々から、オファーをいただいたにもかかわらず、ご依頼をお断りせざるを得ず、申し訳ない想いで一杯です。このため、ホームページの更新も全くできていませんでしたが、業務が一段落したので再開させていただきます。時間があるときにでも読んででいただければ幸いです。
今年度に入ってすぐ、熊本地震が発生しました(10月には、鳥取県でも大きな地震が発生しました)。当社の熊本県内のクライアントも、人的被害はなかったものの、まだ、十分に業務が再開できない施設もあり、大きな被害が出たことを実感しています。
思い起こせば、5年前にも東日本大震災がありました。この年(平成23年度)や翌年度(平成24年度)の指定管理者公募では、「安全・安心の確保」、特に、「災害発生時の対応」のウエイトが高くなり、危機管理体制の整備はもちろんですが、「利用者や周辺住民も参加した防災訓練の実施」、「防災備品(食糧、飲料水、毛布、使い捨てカイロ等)の準備」、「防災に関するイベント等(防災セミナー、避難宿泊体験等)の実施」などの提案が高く評価される傾向がありました。
おそらく、来年度(平成29年度)も、同様の傾向があるのではないかと考えられます。公募がある施設の方は、防災に関する新たな提案ができないかを、今から考えてみてください。
私が、お手伝いした施設、特に、広い駐車場がある施設では、熊本地震を踏まえ、車中避難に関する提案(車中避難を想定した防災訓練など)をアドバイスしました。まだ、全部の結果が出ているわけではなりませんが、すでに結果発表があった施設では、結構評価が高かったので、このような提案も検討してみてはどうでしょうか。(2016.11.2)
5年前のリベンジ
5年前の公募で、他の企業に敗れて、指定管理者から外された企業から、当該施設に再チャレンジしたいとの依頼をいただきました。話をお伺いすると、5年前、わずかの点差で敗れましたが、その後、他の自治体の同種施設の指定管理者に選定され、利用者数を伸ばしているほか、利用者満足度も非常に高いとのことです。一方、敗れた施設では、利用者数が低迷しており、勝てるチャンスはあるとのではないかとのことでした。
そのとおりと考え、当社でお手伝いさせていただいたのですが、事業計画書の作成とは別に、応募する企業の知り合いのメンテナンス企業とコンソーシアムを組んで応募するようにアドバイスしました。
なぜ、このようなアドバイスを行ったかというと、自治体にもメンツがあるからです。5年前、当該自治体は、指定管理者を交代させる判断を行いました。結果として、当該施設の利用者数は低迷し、指定管理者から外した企業は、他施設で良好な結果を出しています。このような状況の中で、指定管理者を元に戻すのは、「5年前の判断が誤りだった」 と認めてしまうことになりかねず、自治体幹部にかなりの抵抗があるからです。
コンソーシアムにすれば、形式上は指定管理者を元に戻すということにはなりません。また、「5年前の結果を踏まえ、コンソーシアムという形で体制を強化したことを評価した」 などの理屈をつければ、5年前の判断とも両立が可能です。
結果は、私が応援した企業が指定管理者に返り咲くことができました。もちろん、事業計画書や他施設の管理運営状況が評価されたことが勝利の最大の要因ですが、このような小さな工夫も大切だと私は考えています。(2016.12.5)
体育施設での大手企業との競合
あけましておめでとうございます。今年も毎月1回くらいは、コンテンツの更新を行う予定です。時間のある際に読んでいただければと思います。
北京オリンピック、ロンドンオリンピックの開催年やその翌年には、地方の体育施設の指定管理者に全国的な大手企業の応募が増えるという傾向がありました。リオオリンピックがあった昨年も、地方の財団や中小企業が指定管理者となっている体育施設の事業計画書作成を3件お手伝いさせていただきましたが、すべて、全国的な大手企業が相手となりました(幸いにも、3件とも勝つことができました。)。
オリンピックイヤーやその翌年に体育施設で大手企業の応募が増える理由ですが、所属しているスポーツ選手の中から(おそらく)メダリストが出るので、事業計画書に「オリンピックメダリストの○○選手によるスポーツ教室を開催します。」と記載することで、勝つ可能性を高めることができるからだと思います。
したがって、地方の財団や中小企業は、上記のような大手企業に対抗する戦略を考える必要があるのですが、私は、地域連携やボランティアに関する提案を充実するようアドバイスしています。 なぜかというと、地域連携やボランティアは大手企業の弱点だからです。
例えば、自動車メーカーの大手であるT自動車が指定管理者となったとします。そうすると、ライバル企業であるN、H、Mなどのメーカー、系列企業、販売店、下請け企業は、指定管理者とは連携できませんし、これらで働く方やその家族もボランティアには参加しにくい状況となります。つまり、企業規模が大きくなるほど、取引先や事業分野が拡大し、ライバル関係となる企業や住民が増えてしまうので、地域連携やボランティア活用が難しくなってしまうのです。
ですから、地方の体育施設の指定管理者となっている財団や中小企業の方は、ぜひ、今まで以上に地域連携やボランティア活用に力を入れるようにしてください。インターンシップを受け入れたり、清掃や植樹でボランティアが活動しているのは当たり前で、これだけで、大手企業に対抗するのは難しいかもしれません、もっと他の分野での連携やボランティア活用もぜひ検討してみてください。(2017.1.3)
3月は、次年度の事業計画書や収支計画書を作成しているからでしょうか、収支計画書上での利益について、ご質問をいただきます。具体的には、「収支計画書で利益を計上してもよいか、また、計上できるのであれば、どの程度が妥当か」 という内容です。結論から申し上げると、収支計画書では利益は 「ゼロ」 にすべきです。
「収支計画と決算が大きく異なることは問題がある」 と考える方がいますが、収支計画はあくまで「見積り」に過ぎず、基本的には、日本の商取引で一般的に発行されている 「見積書」と同じ性格のものです。(自治体も毎年予算を策定していますが、当初予算と決算が大きく異なることも珍しくありません。ただし、自治体は、2月補正を実施し、ほぼ予算と決算が一致するように決算期直前に予算を修正しています。)
一般に、日本の商取引で使われる 「見積書」 には 「利益」 という項目はありません (みなさんも 「見積書」 に 「利益」 という項目を見たことはないと思います。)。けれども、多くの企業の決算には、利益が計上されており、「見積書」 にはない項目が発生している、言い換えると、見積書の各項目(人件費、原材料費など)の中に「利益」が含まれているということです。
したがって、見積書と同様、指定管理の収支計画書にも「利益」という項目を計上しないのはある意味当然です。「収支計画段階で利益がゼロなのに、決算では 「利益」 が出るのはおかしい」 などと考える必要は全くありませんし、また、収支計画書段階で、「利益」 が「ゼロ」であったのに、収支決算書では 「利益」 を計上したことを直接的な根拠 (理由) にして、指定管理者の評価が下がることもありません。(ただし、十分な 「利益」 が出ているにもかかわらず、実施すべき修繕を行っていない等、やるべきことをやっていない場合は別です)
ただし、「利益」 を計上しすぎると、自治体から 「次期公募での指定管理料上限を、利益の金額相当分下げます。」 と言われる可能性がかなりの確率でありますので、次期公募のことを考えると、多すぎる利益は好ましくありません。指定管理業務をバックアップした本社の経費を計上するなど、「虚偽と言われない範囲」 で費用を増やし、「利益」 をできる限り少なくすることも大切だと思います。(2019.3.17)
あけましておめでとうございます。今年も、月1回程度は、コラムの更新を行いますので、時間のあるときにご覧いただければ幸いです。
東京オリンピックが開催される今年の指定管理で、留意しなければならないことのひとつは、公募日程です。当社本社がある徳島県がドイツのハンドボールチームおよび柔道選手団、カンボジアの水泳選手団の開催前・開催中のキャンプ地に内定しているように、首都圏だけでなく、全国各地で、開催前・開催中のナショナルチーム(選手団)のキャンプが行われます。(このほかにも、調整のための練習試合等も全国各地で開催されます)
国民体育大会でも、開催自治体職員は多忙を極めるのですから、オリンピックの関連業務の量が半端ないことは間違いありません。したがって、オリンピック関係のキャンプ等が内定している自治体で、7月、8月に指定管理の公募を行うことが,難しい自治体担当課 (特に体育施設の担当課) がかなりあるのではないかと考えられます。
7月、8月の公募が難しいとすれば、6月以前に前倒しするか、9月以降に先送りすることが検討されるでしょう。したがって、「前回は8月に公募があったのに今回は5月だった」 というように、公募日程が前回と大幅に異なる可能性があります。
おそらく、現指定管理者の方は、どこかの段階で、自治体から、「今年は公募日程を早める(遅くする)」 というような連絡があるでしょうが、新たな施設に挑戦される方は、「前回と同様の日程と考えていたら、いつの間にか公募が終了していた」 というようなことにもなりかねません。このような事態を防止するためにも、3月か4月に、「オリンピックの関係で公募が早まる可能性があるかどうか」 を自治体担当課に確認するべきです。「早まる可能性が高い」とか「ほぼ前回と変わらないと思う」のような程度の回答はしてもらえると思います。(2020.1.2)
→[事業計画書作成のポイント]に戻る
事業計画書作成の際、現指定管理者の方から、たまにご質問をいただくのは、動詞の形態です。例えば、「個人情報は鍵のかかるキャビネットに保管します」 と記載するのがよいのか、それとも、これまでも実施しているので、「・・・・・保管しています」 と記載するのがよいのかという趣旨です。
結論から言うと、「します」 と、未来に向けての表現で記載するのが基本です。理由は、事業計画書は、あくまで、これから実施しようとすることを記載する書類だからです。よく似ているのが選挙の公約で、例えば、昨年の参議院選の某与党の公約には 「力強い外交・防衛で国益を守ります」 との記載がありました。与党なので、これまでも、「力強い外交・防衛政策」 を行っていたと考えているはずですが、それでも、「国益を守っています」とは記載していません。選挙も、基本的には、未来の政策を語る場なので、未来に向けての表現を使っているのだと思います。
ただし、「これまでも卓越した取り組みを行っている」 ということを強調したい場合は例外です。例えば、「当社では、ボランティアを積極的に活用しています。特に、昨年度は延べ500名のボランティアにご協力いただき、○○○○、○○○○等を実施しました」 というように 「しています」 の後に、優れた実績を記載できるなら 「しています」 という表現を、むしろ使う方がよいと思います。
なお、「表現の不一致」 を気にする、すなわち、ある部分は 「します」 と記載し、ある部分は 「しています」 と記載するのはおかしいという意見を持つ方がいます。間違いではないのですが、気にすることはないと私は考えています。事業計画書は文学作品ではなく、管理運営について、考えていることが伝わればよいからです。(2020.1.22)
→[事業計画書作成のポイント]に戻る
緊急事態宣言の解除からあまりの日が経過していませんが、特に、文化施設・体育施設を中心に、水面下で動く全国的規模で指定管理を展開する企業の情報が、例年の数倍規模で入ってきます。もちろん、緊急事態宣言発令中には動けなかった分の遅れを取り戻すためという理由もあるのでしょうが、文化施設・体育施設での動きが活発ということから、別の理由もあるのではないかと、個人的には感じています。
文化施設・体育施設の全国規模の民間企業指定管理者の多くは、コンサート、スポーツジム運営などが本業です。これらは、緊急事態宣言が発令される前から、イベント中止や休業を余儀なくされており、収益が悪化している企業が少なくありません。また、今後もしばらくは、感染症対策で、チケット販売や利用制限などで収益の回復が見込めないばかりか、今年の冬期に再度、感染が拡大してイベント中止や休業となる可能性もあるわけで、今までにはなかったような高い経営リスクを抱えています。
指定管理業務は、決して利益率は高くありませんが、安定的な収入が見込める (万が一、施設が休業となっても、ある程度は自治体から補てんがある) ことから、リスクヘッジ的な観点で、指定管理業務を拡大しようという経営戦略にシフトしている全国的規模の民間企業が増えている兆候なのではないかと思います。
今年度に公募がある施設の多くは5年前 (平成27年度) からの更新でしょう。平成27年度は、アベノミクスが絶頂期のころで、企業の収益力も高く、全国規模の企業の指定管理への関心はあまり高くない時期であったことから、公募で相手がなかった施設も多かったのではないかと思いますが、今年度は、前回とは違う可能性もあります。コロナ対策などで忙しいとは思いますが、競合先がある前提で、公募対策にも万全を期してください。(2020.6.4)
→[事業計画書作成のポイント]へ戻る
今年度はじめて指定管理者に選定された当社クライアントの準備作業を3月にお手伝いした関係で、HPの更新ができませんでしたが、ようやく平常業務にもとったので更新を再開します。
指定管理者が交代する際、ほとんどのケースで、前の指定管理者から何人か職員を引き継ぎます。私は、このような職員の方から、できる限りお話を聴いて、敗因を探っています。理由は、敗因を知ることが、当該自治体で、継続して指定管理者に選定されるための重要な情報になる可能性が高く、クライアントとって有益だからです。
敗因は様々で、簡単には説明できないのですが、多くの方々からお話をお伺いする中で、ほぼ共通しているのは、本社 (本部) と現場の関係がよくないことです。はじめて話をする方が、私に本社 (本部) 批判をするのですから、言葉以上に関係が悪化していたことが容易に想像できます。(敗れた指定管理者の) 本社 (本部) の方とお話ししたことはほとんどないのですが、本社 (本部) 側も、現場に対して、悪い感情を持っていることは多分間違いないでしょう。
指定管理者のレベルは毎年向上しており、公募で勝つことは決して簡単ではありません。にもかかわらず、内部の関係が悪化し、組織が一丸となっていないようでは、勝つ確率が低くなってしまうのはやむを得ないことなのかなあと思います。
おそらく、同じプロ野球チームの選手同士でも、良好な関係ばかりではないと思います。けれども、例えば 「あのピッチャーは嫌いだから今日は真剣にプレーしない」 と考えている野手はいないでしょう。どんなに味方チームのピッチャーが嫌いでも、ゲームに出場したら、バッターボックスでは懸命にボールに食らいつき、守備ではヒット性の打球にも必死にダイビングキャッチをしているはずです。
みなさんも同様で、どんなに本社 (本部) や現場の職員との関係が悪化していても、それはいったん棚上げして、チーム一丸となって事業計画書作成に取り組む体制を構築することが、公募で勝つ第一歩だと思います。(2022.4.11)
「一般的な事業計画書の作成作業スケジュールが知りたいのですが。」 という趣旨のご質問を結構いただきます。「自治体の公募がいつから始まるか」 によって異なるのは、もちろんですが、例えば、公募時期を繁忙期が重なる施設であれば、(公募時期にあまり事業計画書作成に時間を取れないため) 早い時期から作業に着手する必要があるというように、施設や法人の繁忙期などによっても変わりますので、正直、「個々の事情によって全く異なります」としか回答できません。
スケジュールを決める際には、前回の自治体の公募スケジュールを参考にしていると思いますが、私が一番注目しているのは、質問の日程です。なぜかというと、どんなに遅くても、質問の締切日前までには、事業計画書第1案 (収支計画書も含む) をほぼ完全な形で完成させたいと考えているからです。
事業計画書や収支計画書を作成していると、わからないことや確認したいこと等が多数出てきます。ところが、締切日を過ぎてしまうと、これらを質問することができません。もちろん、第1案が完成していなくても質問はできますが、実際に作業してみないと気がつかないことも少なくなく、漏れなく質問しようとすれば、質問の締切日までに、第1案が完成していることが不可欠だからです。
したがって、質問の締切日 (前回の日程を参考にしているのですから、締切日よりも多少の余裕を確保しておくべきでしょう) までに事業計画書や収支計画書の第1案を完成させ、質問の回答によって、内容を調整するということを前提に、全体の作成スケジュールを組むということが基本になるのでしょう。
なお、今年度は、新型コロナや東京オリンピック・パラリンピックの関係で、前回と公募日程が大幅に変わる可能性があります。そろそろ公募日程を確定させなければならない時期ですので、5月中旬から末くらいに確認すれば、「早く(遅く)なる可能性が高い」とか「前回と変わらないと思う」程度の回答はしてもらえると思います。(2021.5.6)
あけましておめでとうございます。今年も、月1回程度はコラムの更新を行いいたいと思っていますので、時間のあるときにご覧いただければ幸いです。新型コロナウイルス感染症の話題に隠れてあまり注目させていませんが、総理大臣の重要政策のうち、指定管理者の選定や評価にも影響がありそうな項目が2点あります。
1点目は、デジタル化です。デジタル庁という新たな組織を設置するのですから、日本政府はもちろん自治体にも、目に見える結果が求められます。このため、小さなことでも、実効性がある提案ができれば、評価を得られる可能性が高まります。昨年の公募では、新型コロナ対策として、利用料金のキャッシュレス決済やオンラインによる会議などを提案した指定管理者が増えましたが、今後は、デジタル化という観点から、さらなる取り組み強化 (例えば、単にキャッシュレス決済を行うだけではなく、キャッシュレス決済で得た情報を分析して、利用促進やサービス向上に活用するなど) を検討すべきかもしれません。
また、2点目は、2050年までに温室効果ガス排出量を「実質ゼロ」 にすることを表明したことです。報道では、民間部門の技術開発支援が全面に出ていますが、総理が表明した日(令和2年11月23日)からわずか1か月(12月25日)で、全国の201自治体で「実質ゼロ」に向けた宣言や議会でも決議が行われるなど、行政部門においても、新たな施策が展開されることがほぼ確実と考えるべきです。
これまで、指定管理事業計画書の「環境配慮」では、「リユース・リサイクル」などの4Rや「節電・節水」等を細かく記載することで、ほとんどの場合、競合先に点差をつけられることはなかったでしょうが、今後は、もう少し踏み込んだ記載が必要になるでしょう。「SDGs」 や「ゼロエミッション」 と関連づけた記載や「施設内への太陽光発電の設置」 なども検討すべきに時期に来ているように思います。
なお、「太陽光発電の設置」 には、自治体の許可がなしで行うことはできません。事業計画書に記載する場合は、「自治体の了解が得られれば」 という条件付きの記載にしてください。(2021.1.4)
事業計画書に記載する経営理念
事業計画書の様式の冒頭に(施設の管理運営方針ではなく) 「企業 (団体) の経営理念」の記載を求められることが結構あります。このような様式の際、事業計画書の検討の場で、長い時間を掛けて、当該法人の経営理念の記載内容について議論が行われていることがよくあります。企業 (団体) のトップが経営理念に 「こだわり」 を持っていることが多く、事業計画書の決裁をトップに持って行った際に、チェックされる可能性が高いので、慎重に検討してるのでしょう。気持ちはよくわかりますが、これは、効率的とは言えません。
審査する側の立場で考えてみてください。「利益が最優先」 のような、公の施設として全くふさわしくない理念でない限り、「A社とB社では、A社の経営理念の方が優れている」 というような結論を出すことはできません。経営理念は企業 (団体) にとって憲法のような存在で、とても大切なものです。これに行政が優劣をつけることは、よほどのことがない限り無理というものでしょう。(点差をつけて、万一、明確な理由を説明できなければ、審査の公平性にまで疑問符がつきかねません。)
したがって、どんなに時間をかけても、ほとんど時間をかけなくても、競合先と差がつくことはほとんどありません。手を抜いてよいとは言いませんが、少なくとも、「経営理念の記載の検討に時間をかけすぎて、他の記載部分の検討時間があまりなかった」 という事態だけは絶対に避けるべきです。
今年度に公募がある施設の方は、そろそろ事業計画書の記載内容の検討に入っていると思います。企業 (団体) の企業 (団体) のトップの方やトップに近い方は、この点を考慮し、勝つことを最優先し、 点差がつきやすい部分を優先して検討するように指示してください。(2022.5.15)
→[事業計画書作成のポイント]に戻る
令和5年度公募における指定管理料
明けましておめでとうございます。旧年中は、年末ぎりぎりまで、PFIや(本業ではないのですが)事業再構築補助金のお手伝いをさせていただいた関係で、ホームページの更新ができませんでした。やっと落ち着いてきたので更新を再開します。
昨年公募で、私が特徴的だと感じたのは、指定管理料の金額です。人件費や燃料費などの高騰で、従来よりも少しは指定管理料を上げて公募している施設が多かったのですが、私の把握している限りでは、選定結果のほとんどで、指定管理料の提案額は、上限額一杯、もしくは、千円単位の端数をカットしているだけでした。
指定管理者制度の導入目的には「経費削減」が入っていますので、これまでは、厳しい状況の中でも、年間5~15万円程度、指定管理期間が5年であれば、25~75万円程度はカットするケースが多かったのですが、最近の人件費やエネルギー価格等の高騰で削減余地が全くなくなっているということなのでしょう。この流れは大きくは変わらないと思います。令和5年度に公募がある施設のみなさんは、令和4年度の状況から、以下の2つの点に留意してほしいと思います。
1点目は、これまで以上に事業計画書の内容が勝敗を決めるということです。つまり、少なくとも、全国規模の大手企業の提案額は、上限額一杯の可能性が高く、みなさんも上限額一杯で提案するとすると、金額では点差がつかないので、内容勝負になります。言い方を変えると「指定管理料をいくらにするか」ということで悩む必要はなく、上限額で提案することを前提に、事業計画書の内容をいかに充実させるか尽力することがこれまで以上に重要になります。
2点目は、指定管理料の上限額が上がった施設で、指定管理料を従来と同額にすることがマイナスに働く可能性があるといことです。昨年の当社の某クライアントの話ですが、公募で次期指定管理料上限額が年間約300万円上がっていました(5,000万円→5,300万円)が、大手企業が応募するとの情報があった関係で、従来と同様、年間5,000万円で提案するという意向でした。
私は、少なくとも、少しは金額をアップして提案するべきだとアドバイスしました。理由ですが、自治体内で指定管理料の上限が「簡単に上がる」ということは(首長のトップダウン以外は)あり得ません。担当課が時間をかけて資料を作成し、財政当局と何度も協議・交渉して「やっと上がった」というケースがほとんどすべてです。
指定管理料の上限が上がったのに、従来と同じ金額で提案すれば(担当課は財政当局に、上限金額を引き上げないと応募者がいないと説明しているので)、担当課の面目が丸つぶれになります。このような事態を避けるためにも、少しでも指定管理料を上げた方がよいとアドバイスし、結果として、約5,250万円で応募し、無事、指定管理者に選定されました。
施設によって状況はまちまちなので、一概には言えませんが、令和5年度の公募では、特別な理由がない限りは、指定管理料を上限額からは下げない方がよいと場合が多いと思います。人件費、燃料費等の高騰がいつまで続くかわかりませんし、この状況で、役所が算定した金額を下回る額を提案するのは、指定管理料に余裕があると自治体に誤解される可能性もあるからです。(2023.1.5)
→[事業計画書作成のポイント]に戻る
申請書の受理
沖縄県内のある市で、業務委託の公募プロポーザルの申請書を締切日の17時30分に提出した企業が採択されたことが市議会で問題になりました。報道によると、締切日の17時15分までに企画提案書を提出することが定められていたところ、当日の市内の渋滞が激しく、締切時間前に(応募企業から)電話があったので、やむを得ない事情と市側が判断し、受理したようです。
渋滞の具合がどの程度だったのかがわからないので何とも言えませんが、少なくとも、想定をはるかに超える激しい渋滞であることが、締切日・締切時間を伸ばす最低条件だと私は思います。
指定管理や補助金の申請でも、締切日当日に、誤字脱字チェックやコピーを行い、締め切り時間ぎりぎりに役所に持参するという方が案外たくさんいますが、非常にリスクが高いやり方です。
法的な話になりますが、申請書などの提出(持参)があった場合、自治体職員は「受理するかどうか」という判断をその場で行う必要があります(「準法律的行政行為」と呼びます)。自治体が受理すると、形式上は適法な申請と見なされ、仮に、後に書類不備等が発覚しても、これを理由に失格にはできません (期限を定めて追加提出または修正するよう申請者に指示する必要があります。蛇足ですが、申請内容が採択に値しなければ、審査して不採択することはできます。つまり、受理すれば、定められた期限までに申請者が対応しない場合を除き、内容を審査する義務が自治体に生じます)。
慎重な自治体の担当者は、申請書等の持参があれば、その場で入念にチェックし、書類不備等があれば「不受理」とし、締切期限内までに再提出することを求めます。もし、締め切り間際に持参して書類不備等で「不受理」になってしまえば、再提出する時間的余裕がありませんから、申請できなかったことになってしまいます。ですから、締め切りぎりぎりの提出は非常にリスクが高いのです。
万一、作業が遅れて締切日・時間に提出できない状況になった場合ですが、「締切日を延ばしてほしい」という要望が認められることは、まずありません。冒頭の事例でも、締切時間を延長したことを知っているのは、(当事者を除けば)市役所の同じフロアにいる職員だけです。つまり(おそらく担当職員のことをよく思っていない)同僚がマスコミに情報を流したのでしょう。一般の方には信じられないかもしれませんが、同僚がマスコミに情報を持ち込むということは、役所ではあり得ない話ではなく、ほぼすべての自治体職員はこのように高いリスクのある判断は行いません。
締め切りに間に合わないということになった場合には、自治体担当者に対し、書類不備等があることを電話で報告した上で、完成している部分のみを期限内に提出するので「とりあえず受理してほしい」と要請するのが可能性がある唯一の対応です。自治体担当者と良好な関係があることが前提ですが、締切日に内容を審査することはまずないので、多くの場合、不備の部分を翌日中に必ず提出すると約束すれば、受理してもらえる可能性が高いと思います。受理後に、書類不備等の追加・修正を指示することは、役所業務では日常茶飯事ですから、これが問題になることはまずないからです。
なお、締切日に間に合わない場合でなく、締め切り時間ぎりぎりにまで作業に追われている場合も、渋滞や交通事故などに巻き込まれる可能性もあるのですから、少なくとも締切の数時間前には完成しているのみを印刷を行い、作業と並行して、電話でこれを「とりあえず受理してほしい」と要望する保険をかけた方がよいと思います。(2013. 5.7)
→[事業計画書作成のポイント]に戻る
審査内容の確認
毎年同じことを書くのですが、特に、今年は、指定管理だけでなく、PFIや事業再構築補助金の事業計画書作成のご依頼も数多くいただいた関係で、ホームページの更新が難しい状況が続きました。ようやく落ち着いてきたので再開します。
令和5年度の指定管理公募の大部分が終了し、結果が出ている施設が多いと思います。指定されたみなさんには、お喜びを申し上げるとともに、残念な結果となった方々には、ぜひ、リベンジしてほしいと思います。
何らかの形で審査委員会の内容が公表されていると思いますが、特に、2者以上の応募があった施設では、参考にならないケースがほとんどです。理由は、落選した応募者からの反発に対応できるようにすることを最大の目的としているからです。
例えば、「職員のマルチスタッフ化」が落選した応募者の事業計画書には記載されていなかったがなかったとすれば、審査委員会の議論の中心ではなかったにもかかわらず、「選定された応募者は、職員のマルチスタッフ化などの提案が高く評価された」というように公表されるケースがよくあります。
「など」があるので虚偽ではありませんし、落選した応募者からの反発があった場合にも「マルチスタッフ化が記載されていなかったので差がついてしまった」と言えば、実際に記載がないのですから、これ以上反発することが難しくなります。このように、審査では枝葉末節であった事項を「落選者に説明しやすい」という理由で、あえて、選定理由の中心的な事項であったかのように公表されることが結構あるのです。
したがって、公表された審査内容を鵜呑みにして、次期公募や同じ自治体の他施設の公募で「マルチスタッフ化」を強調した事業計画書することはあまり意味がなく、公表された審査内容ではなくて、できる限り、審査委員会で実際に行われた具体的な議論の中心、特に、審査委員が高く評価した点、低かった点の具体的項目や理由を収集することが望ましいです。
収集方法ですが、審査委員に直接接触するは、その審査委員(次回公募で審査委員に委嘱されることも少なくない)の心証を悪くするリスクが高いので避けた方がよいでしょう。「次回応募の参考にしたい」 という理由で自治体職員(課長以下)に尋ねるのが良いと思います。自治体職員も議会の議決を得るまでは慎重ですが、選定された応募者には「高い水準の管理運営をほしい」と、また、落選した応募者にも「高いレベルの競争者がいることで現指定管理者が緊張感を持って管理運営する」と考えていることから、議会の議決後であれば、ある程度は教えてくれるはずです。
また、少し先になりますが、4月の人事異動で他の部署に転出することが決まった職員は(もう自分の業務ではなくなるので)詳しく教えてくれる可能性が高いです。3月下旬に発表される自治体の人事異動にも、留意しておくとよいと思います。(2023.11.5)
→[事業計画書作成のポイント]に戻る
地域に密着したネットワーク
地域密着型の指定管理者が、参入しようする大手に対抗する手段のひとつとして「地域に密着したネットワーク」をアピールすることが結構あると思います。例えば「施設のリーフレットやイベント・各種教室のチラシ等は、地域に密着した活動を展開している当法人のネットワークを活用し、地元の商店街・飲食店・金融機関・診療所・ガソリンスタンドなどに無料で設置していただきます。」という趣旨を事業計画書に記載することです。
もちろん有力な手法ですが、大手にも対抗策があり、特に、ここ数年、よく見かけるようになったのが「地域と幅広い交流を持つ現在の職員を雇用することで、現在の地域とのネットワークを維持します。」という記載です。
現在の指定管理者が有するネットワークが「指定管理者」と「地域」ではなく、「指定管理者の職員」と「地域」、すなわち、職員の個人的な「つながり」に過ぎないことを指摘し、自らの弱点を緩和しようとする趣旨で記載しており、結果が出ている(= 地域連携の得点が現指定管理者と同点以上になっている)ケースも少なくありありません。
このような記載に対抗するには、(職員個人ではなく)「指定管理者である法人」と「地域」間、つまり「組織」対「組織」のネットワークであることを強調する必要があります。具体的には、地域の多くの法人・団体・組織等と、事業活動や広報などで、書面による連携協定を締結することが効果的なのではないかと思っています。
大手は、組織が大きいが故に、法人代表印を押すような書面を作成するには、何段階もの上司への根回し・説明が必要で、(管理運営している施設であればまだしも)これから参入ようとする施設に、協定書を作成・押印するための莫大な手間・時間をかける余裕があるとは考えにくい(=大手が多くの地元連携先候補と協定書を締結することは難しい)からです。
地域の多くの企業・団体等と連携して管理運営を行っている法人の方は、連携内容を文書にし、双方が押印することで「協定化」する(そして事業計画書の参考資料として添付する)ことを、公募対策として検討してみてもよいのではと思います。(2024.3.24)
→[事業計画書作成のポイント]に戻る
事業計画書の作成体制
ここ数年、「事業計画書の提出締切直前の6月(7月)に、中心となる職員が突然退職した」という趣旨を聞くことが増えつつあります。当社のクライアントでも、令和5年度に1法人、令和6年度に2法人でこのようなケースがありました。特に、令和6年度は、情報として私の耳に入った事例まで含めると11施設もあり、うち4施設では、退職代行業者を活用してまで強硬に「引き留め」を拒んだとのことです。
指定管理者の幹部の方から「一番重要な時期に退職するのは信義に反する」というような相談をいただくことがあるのですが(そもそも私は労働法令の専門家ではありませんし)法的には、原則として2週間前に意思表示すればよいそうなので、現実問題として「引き留め」は困難でしょう。
したがって、リスク回避策は「事業計画書作成の負担を1人の担当者に集中させないこと」しかないように思います。このように記載すると「うちは事業計画書作成チームを編成しているから大丈夫」と考える幹部の方がいるのですが、私がお手伝いしている施設でも「チームが編成されているが、負担は1人に偏っていて、残りのメンバーは会議に出席して意見を述べているだけ」というケースが少なくありません。
特に、会議に出席するだけのメンバーが「できない」・「無理」のように、新たな提案に否定的な意見を連発していると、中心となる職員のモチベーションが下がってしまい、やがて「ボーナスをもらって辞めよう」というような結果になることがあるのだと思います。
このようにならないためにも、チームを編成する場合には、きちんと機能するように注意を払う必要があります。手法はいろいろあると思いますが、私は「① ライティングを(1人に任すのではなく)分担すること。」 「② 出席者全員が前向きな提案を1つ以上行うことをルール化すること。」「③ 否定的な意見を述べる場合には、代替案の提案をルール化すること。」の3点はあった方がよいと考えています。
世間一般の給与大幅アップや深刻な人手不足により(給与を大幅に上げることが難しい)指定管理施設職員の転職リスクが高いという状況は今後もしばらくは続くでしょう。多くの指定管理の職場では、優秀な職員ほど業務量が増える傾向にあり、これを放置して退職に至るという事態だけは回避することが幹部の重要な役割だと思います。(2025.3.27)
→[事業計画書作成のポイント]に戻る
応募者名「黒塗り」の事業計画書
募集要項などで、副本の事業計画書の応募者名を「黒塗り」にするように指示がある場合があります。理由は「審査過程で応募者名による先入観を排除するため」ということなのですが、この際、「応募者名が容易に推測できる記載」、例えば「長年○○○〇(施設の固有名詞)の指定管理者として業務を行っており」とか「市内で唯一の○○〇○(製品の固有名詞)の特約代理店で・・・」のような記載を「黒塗り」する必要があるのか」という質問をいただくことがあります。
結論ですが、「応募者名を「黒塗り」すること」との指示があった場合、応募者名以外を「黒塗り」する必要はありません。「黒塗り」の指示は「公平に審査を行っている」との「アリバイづくり」にすぎないからです。
ですから当社がお手伝いした案件でも、「当社はショッピングセンター○○○〇(固有名詞)運営しており」と、当該地域で唯一のショッピングセンターの固有名詞(=容易に応募者名が推測できる)を黒塗りしないで提出しましたが、何も言われていません。万一、自治体が「問題がある」と考えた場合でも、いきなり失格にすることは、行政手続条例などの関係でほぼ不可能で、追加で「黒塗り」するよう指示されるだけなので、「黒塗り」の指示には、文字から解釈できる最低限度のみを「黒塗り」して対応すればよいと考えてください。
なお、黒塗りの指示がある際は、むしろプレゼンの際(特に質疑の際)に、誤って応募者名を言うことがないよう留意してください。プレゼンの質疑は自治体が録音していることが多く、記録が残るので「なかったことにする」のが難しい場合があるからです。もっとも最近は、録音ではなく、AIによる自動記録が普及しつつあり(自動記録は手動で修正できるので)、これも数年後には、あまり問題にならないようになると思います。(2025.7.6)
→[事業計画書作成のポイント]に戻る